武家の名門・足利氏の廟所「樺崎寺跡」 悠久の浄土庭園再生プロジェクト
カテゴリー:伝統・文化・歴史
寄付金額 1,359,500円
目標金額:2,000,000円
- 達成率
- 67.9%
- 支援人数
- 64人
- 終了まで
- 受付終了
栃木県足利市(とちぎけん あしかがし)
寄付募集期間:2025年9月26日~2025年12月24日(90日間)
栃木県足利市

国史跡の樺崎寺跡は足利氏の廟所跡で、浄土庭園を持つ中世寺院の遺跡です。
足利氏2代目の義兼(尊氏の6代先祖)は源頼朝と血縁関係にあり、その側近として鎌倉幕府の創設に貢献した人物で、晩年を樺崎寺で過ごし、その生涯を閉じました。
樺崎寺は鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて最盛期を迎えますが、徐々に衰退し、明治の神仏分離令により廃寺となり、樺崎八幡宮として現在に至ります。
足利市では、発掘や文献等の調査研究成果に基づき、樺崎寺跡の保存整備事業を進めており、浄土庭園を現代社会における安らぎの場として再現し、人々が集える空間に整備するプロジェクトに取り組んでいます。
足利氏と樺崎寺
足利市は、足利氏発祥の地であり、鎌倉幕府を開いた源頼朝の曽祖父・源義親の兄弟である源義国が足利の地に移住し、その子・義康(よしやす)が足利氏を名乗ったのがはじまりです。
室町幕府を開いた足利尊氏は、初代の義康から数えて8代目にあたります。
足利氏2代目の義兼(よしかね)は、源頼朝と先祖(源義家)を同じくする血筋で、頼朝の妻・北条政子の妹の時子を妻としており、源平の戦いでは頼朝の右腕として活躍し、北条氏とともに鎌倉幕府の創設に多大な貢献をした人物です。

その義兼が、鎌倉幕府で頼朝に次ぐ地位にまで登り詰めたのち、晩年に仏門に帰依し、念仏三昧の日々を過ごしたのが樺崎寺です。
最後は自ら地中に籠り、念仏を唱えながら生き入定したと伝えられており、廃寺後に樺崎八幡宮となった今も、本殿の床下には「足利義兼公御廟」と書かれた墓標(木柱)が立ち、この地が義兼の入定の地であることを物語っています。

この樺崎寺は、もとは義兼が参加した奥州合戦の戦勝祈願のために創建しましたが、その後、合戦の際に目にした平泉の毛越寺や中尊寺などの華麗な浄土庭園を中心とする寺院に深い感銘を受け、帰国後に浄土庭園を含む伽藍を整備したもので、頼朝をはじめ、有力御家人たちも競って自らの領地に浄土庭園を持つ寺院を造営しました。
また、かつて樺崎寺には義兼が作成を依頼した、運慶作とされる2体の「大日如来坐像」が存在しており、1体の坐像は寺の下御堂に安置し、もう1体の厨子入りの坐像は義兼が常に手元に置き、厨子を背負って諸国を行脚したと伝えられています。
この2体の坐像は明治の廃仏毀釈により樺崎寺から引き離されることとなり、1体は市内の足利氏ゆかりの光得寺に移され、もう1体は行方が不明となりましたが、平成20年にニューヨークで開催されたクリスティーズのオークションに出品され、日本の芸術作品として史上最高価格の約14億円で落札され、現在は宗教法人の真如苑が所有するといった数奇な運命を辿っています。
東国において運慶作の仏像が残されているのは、鎌倉幕府で重要な地位にあった人物が建てた寺院に限られており、また、樺崎寺跡の発掘調査により出土した瓦や陶磁器等の特徴からも、当時、義兼がいかに力を持っていたのかが伺えます。


鎌倉時代の足利氏は、義兼の子である3代の義氏(よしうじ)の時代に最盛期を迎えますが、その後は北条氏が実権を握って有力御家人を排除していった鎌倉幕府の中で、北条氏との姻戚関係などを通じて巧みに生き延び、頼朝の血統無きあと、源氏の嫡流である尊氏によって室町幕府が開かれることになります。
尊氏が武家のリーダーとなって鎌倉幕府を倒し、室町幕府を開くことが出来たのにはこうした道筋があり、特にその礎を築いた先祖・義兼の功績が大きかったと言えます。
鑁阿寺と樺崎寺
足利市の中心部にある鑁阿寺(ばんなじ)は、四方を堀に囲まれた義兼の居館跡をのちに寺院として整備したものです。

足利氏の氏寺であり、鎌倉時代の最先端の禅宗様を特徴とする国宝の本堂に本尊の大日如来をお祀りし、地元では「大日さま」と呼ばれ、市民に親しまれています。
樺崎寺は、この鑁阿寺から約5km離れた北東(鬼門)の方角に位置しており、義兼はその死後も足利氏の繁栄を願い、見守るために、この樺崎の地において入定したと考えられます。
足利の地は将軍家の父祖伝来の地として篤く庇護を受け、これら2寺をはじめとする一族ゆかりの社寺も繫栄し、守られてきました。
日本の中世を代表する武家の血統・足利氏のヒストリーを語る上で、鑁阿寺は足利氏の「氏寺」として、また、樺崎寺跡は鑁阿寺の奥の院にあたる足利氏の「廟所」として極めて重要な場所であり、ともに足利市が世界に誇る文化遺産です。
これからの樺崎寺のために(寄付金の使い道)
樺崎寺跡は平成13年に国史跡の指定を受け、足利市による発掘調査や保存整備事業を進めてきました。

第1期・第2期の整備を通じて、これまでに史跡の主要な部分の復元整備を行い、浄土庭園についても、遺構の保存状態が良好な15世紀前半~中頃の姿に復元することが出来ました。

現在は、主に史跡東部の遺構の整備に取り組んでおり、本年度は、樺崎寺跡を訪れる人たちのための説明板や防犯設備などの設置と、憩いの場として文化遺産に親しんでいただけるような空間づくりを行うための実施設計業務を行う予定です。
足利市では、この樺崎寺跡の保存整備事業を通じて、浄土庭園を現代社会における安らぎの場として再現し、さらに人々が集えるような空間を整備するプロジェクトに取り組んでいます。
室町幕府将軍・足利尊氏へとつながる足利氏の繁栄の礎を築いた足利義兼の終焉の地、この樺崎寺跡に復元された浄土庭園を訪れ、遥かなる中世の夢の跡に思いを馳せてみませんか?
もし、このプロジェクトにご共感いただけましたら、ぜひ、クラウドファンディングへのご参加をお願いいたします!
※目標金額を達成できなかった場合や、目標金額を超えた場合でも、皆様からいただいた貴重な寄付金は、本プロジェクトに活用させていただきます。
樺崎寺跡復元イメージ図

ふるさと納税で
このプロジェクトを応援しよう!
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。
控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
控除上限額かんたんシミュレーション
お礼の品一覧
-

水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 96本 お水 飲料水 軟水で飲みやすい 備…
13,000 円
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

水 ミネラルウォーター 天然水 2L 24本 お水 飲料水 軟水で飲みやすい 備蓄…
10,000 円
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 24本 お水 飲料水 軟水…
12,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ココワイン 農民セット F7Z-021
18,000 円
希望にあふれた赤ワイン「農民ロッソ」と、日本の小粋な白ワイン「農民ドライ」の2本セット。「農民ロッソ」はやわらかなタンニンとたっぷりの果実味が特徴、「農民ドライ」は華やかな香り、爽やかな酸と凛とした味わいで人気の辛口白ワインです。バランスもよく、初めてワインを飲む方から、ワイン好きの方まで幅広く楽しんでいただけます。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。
※20歳未満の飲酒は法律により禁止されています。20歳未満の方のお申込みはご遠慮ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック のりものセット【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 …
29,000 円
●対象年齢:2歳以上
のりものが大好きなお子さまも大満足!
車と飛行機のヘッドの部分のパーツが入っていて、働くのりものが作れます。
消防車、パトカー、新幹線など大好きなのりものが作れるセットです。
カラフルなカラーリングのパーツでのりもののボディをカッコよく作ることができます。
ケースのフタ部分を駅として、周囲をブロックでぐるりと囲んで線路として見立てれば、スケールの大きなごっこ遊びを楽しむことができます。
●学研ニューブロックの特長
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。
●学研ニューブロック 3つのポイント
■やわらかくて大きいから安心!
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
■創造力を育む特徴的な形!
「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
■成長にあわせて長く遊べる!
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。
■お礼品の内容について
・学研 ニューブロック のりものセット[ブロックパーツ:20種96パーツ、取り扱い説明書、ユーザーシール]
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

自家製燻製 スモークチーズ はまちいず5個 桜チップ 燻製 手作り 濃厚 スモ…
10,000 円
桜チップでいぶした手作りスモークチーズとろりとしたチーズが絶品です。 スタートは家族のために燻製していたものが、あまりの美味しさに商品化。秘伝のスモーク方法により、外は香ばしく中はトロリとした絶妙の味わいです。お客様からはチーズよりもチーズらしい!と大好評でリピーター拡大中です。そのままでも温めてもOK。薄くスライスしてカリカリになるまで電子レンジで加熱すると絶品のチーズスナックに早変わりです!コーヒーなどのおやつやお酒のおつまみにもぴったりです。
【産地・原材料名】
ナチュラルチーズ/乳化剤
栄養成分表示100gあたりエネルギー335kcal、たんぱく質20.9g、脂質27.4g、飽和脂肪酸16.5g、糖質0~3.9g、炭水化物0~3.9g、食物繊維0.0g、食塩相当量2.5g
アレルゲン(27品目中)乳成分
【使用方法】
自家製手作り燻製を行っています。開封後はお早めにお召し上がり下さい。
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
アレルゲン(27品目中)乳成分 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【ふるさと納税】あしかがフラワーパーク入園券(2枚)+オリジナルグッズ F7…
10,000 円
あしかがフラワーパーク以下「当園という」は、有料植物園として全国1位の来園者を誇る花と光のテーマパークです。当園の核となる藤の花はCNNから世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出されました。
また10月下旬より開催されるイルミネーション 「光の花の庭」 は夜景コンベンションビューローが認定する日本三大イルミネーションに選ばれ、2016年から2021年まで6年連続で全国の夜景鑑賞士が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいて、イルミネーション部門で全国1位を獲得。
四季折々、数多くの花々で彩られており年間で 160万人 以上の来園者が訪れます。当園の入場に年間を通じてお使い頂ける入園券と人気のオリジナルグッズをセットにした内容となっております。
【産地・原材料名】
◆藤の香りハンドクリーム:藤のはちみつを配合したハンドクリーム。雑貨の中では人気ランキング1位の商品です!手になじみやすく、軽やかな使い心地です。内容量 :30g
◆藤の香りの湯:藤の香りの入浴剤。藤の優しく心地よい香りをバスタイムでも。内容量 :25g×5
◆藤トートバッグ:ナチュラルな風合いのシンプルなトートバッグ。片面に藤柄をプリントしました。素材 :(表)綿・ポリエステル (裏)ポリプロピレンサイズ:約420mm(最大幅)×約290mm(高さ)×約110mm(マチ幅)持ち手:約223mm(最大高さ)
【使用方法】
あしかがフラワーパークの入園にご利用頂けます。
【注意事項】
入園券は有効期限がざいます。有効期限(1年~2年)は寄付の時期により異なります。
(例)2024年4月1日~2025年3月31日までの寄付は、2026年3月31日までとなります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利マール牛粗挽き生ハンバーグ5個セット【 ハンバーグ 牛 冷凍 お取り寄せ…
10,000 円
余計なものはいれない。マール牛100%の自慢のハンバーグ
粗挽き、火入れ前の生の状態で急速冷凍しているのでふっくらジューシーに食べられる
足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てている、月3頭しか出回らない希少な牛です。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。このハンバーグは、100%足利マール牛を使った生ハンバーグです。驚くほどふっくらジューシーに仕上がっていてリピーター続出の人気商品です。
【産地・原材料名】
栃木県産牛肉/ソテードオニオン/パン粉/凍結全卵/牛乳/トマトケチャップ/食塩/香辛料/調味料(アミノ酸など)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉を含む)
【使用方法】
解凍後、よく焼いてお召し上がりください。
【保存方法】
マイナス23度以下で保存
【注意事項】
離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

生クリームいちご大福6個入【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-1315
10,000 円
国産いちごを1粒ごろっと、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のお餅で包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。
【産地・原材料名】
餅生地(米粉、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

生クリームフルーツ大福6個入 アソート【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-13…
10,000 円
国産いちごをはじめ、ブルーベリー・パインといったフルーツを、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のおもちで包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。
【産地・原材料名】
[生クリーム大福(いちご)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
[生クリーム大福(ブルーベリー)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、ブルーベリー/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
[生クリーム大福(パイナップル)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、パイナップル/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

まんぷく餃子 1パック22個入り F7Z-535
4,000 円
料理屋 恵MEGUMIの自慢の餃子を家庭でも食べれるように小ぶりに改良し、生餃子(冷凍)として店舗と自動販売機で販売しております。ニンニクは使わず、肉と野菜とたっぷり使用して栄養満点の餃子です。地元ではお子様からお年寄りの方まで多くのお客様に食べて頂いております。
【産地・原材料名】
野菜(キャベツ、玉ねぎ、ニラ、白菜、ショウガ)
食肉(豚肉)豚脂 醤油 酒 オイスター 砂糖 塩 白胡椒
片栗粉 調味料(L-グルタミン酸ナトリウム5-リボヌクレオタイド
ナトリウムアミノ酸等) 皮(小麦粉 食用植物油加工澱粉 酒精 酸味料)
脱脂加工大豆 アルコール 米 米こうじ
醸造アルコール カキエキス 増粘剤 キサンタン
着色料(カラメル 酢酸 食用ごま油 食用大豆油 食用こめ油
原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中):豚肉・大豆・小麦・胡麻
製造施設内で卵、乳、海老などアレルギー物質(27品目)を使用しています
【使用方法】
しっかり加熱しお召し上がり下さい
【保存方法】
冷凍
【注意事項】
・繁忙期のため年末年始の発送が大変遅れる場合がございます。ご了承ください。
餃子の製造や包装等丁寧に扱っておりますが、運送のタイミングなどで多少の衝撃がかかってしまい、多少の耳割れがある場合がございます。
何卒ご了承下さい。
【配達不可地域】
離島は配送不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中14個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …
11,500 円
甘党を唸らす最中の逸品。
日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。
足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。
十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。
一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。
若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。
【産地・原材料名】
砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩
【保存方法】
直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。
【注意事項】
※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。
※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【返礼品なし】足利大学応援プロジェクト F7Z-A000
2,000 円
〇足利大学応援プロジェクトについて
本プロジェクトは、ふるさと納税制度を活用し、足利大学が実施する地域貢献や地域連携事業等に対して、支援を行うものです。
ご寄附いただいた寄附額の7割を足利市から足利大学へ翌年度補助金として交付する仕組みとなっております。
なお、返礼品はございませんので、足利市民の方もご寄付いただけます。
皆様の暖かいご支援をお願いいたします。
※残りの3割については、サイトの利用料等の事務費及び本市のまちづくりに関する事業に活用させていただきます。
〇ご寄附について
いただいたご寄附を可能な限り大学支援に活用するため、返礼品は設定しておりません。
※寄附金の使い道は、「文化・芸術・スポーツの振興」を選択してください。
※別の選択をされた場合は、自治体側で修正させていただきます。
〇足利大学をご紹介
足利大学は、1967年(昭和42年)に足利工業大学として開学しました。2018年(平成30年)に足利大学へ名称を変更、工学部、看護学部、大学院(修士課程・博士後期課程)を有する足利市内唯一の大学であり、足利市内に2つのキャンパスを展開しています。
足利大学は、聖徳太子が制定した「17条の憲法」の第1条にある「和を以って貴しと為す(以和為貴)」を建学の精神としており、崇高な人格と人間力豊かな人材の育成に努めています。
近年では、CN(カーボンニュートラル)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、国際交流という3つの柱のもと、これからの時代に必要とされる人材育成に力を入れています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
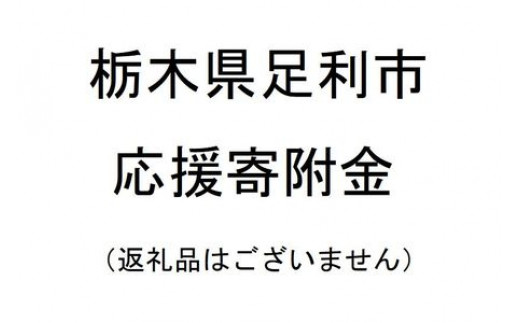
【返礼品なし】栃木県足利市応援寄附金(1000円単位でご寄附いただけます) …
1,000 円
「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。
寄附のお申し出の際に、いずれかの使い道をご指定してください。
ご指定がない場合は、市長におまかせにさせていただきます。
用途1
市政全般(足利市におまかせください)
用途2
子どもの輝く未来のため
用途3
活力ある産業振興と観光誘客
用途4
健康・福祉施策の充実
用途5
文化・芸術・スポーツの振興
用途6
快適で魅力ある住環境の整備
用途7
災害対策と安全安心なまちづくり
用途8
名刀山姥切国広を守り、未来へ受け継いでいくため
・お礼の品はございません。
・寄附申込みのキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。
名称:【返礼品なし】栃木県足利市応援寄附金(1000円単位でご寄附いただけます) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中11個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …
9,500 円
甘党を唸らす最中の逸品。
日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。
足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。
十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。
一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。
若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。
【産地・原材料名】
砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩
【保存方法】
直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。
【注意事項】
※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。
※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中22個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …
17,000 円
甘党を唸らす最中の逸品。
日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。
足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。
十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。
一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。
若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。
【産地・原材料名】
砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩
【保存方法】
直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。
【注意事項】
※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。
※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 48本 お水 飲料水 軟水…
21,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 12本 お水 飲料水 軟水で飲…
18,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 24本 お水 飲料水 軟水…
24,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 48本 お水 飲料水 軟水…
42,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 72本 お水 飲料水 軟水…
30,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 72本 お水 飲料水 軟水…
60,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME Pale Ale」355ml缶 8本セット【 クラフトビー…
22,000 円
ORIHIME Pale Ale
アルコール度数 4.5%
モルトとホップのバランスが程よく、豊かな柑橘系の香りが特徴のエールタイプのビールです。
エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!
ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。
ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。
温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。
【産地・原材料名】
原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン
製造:栃木県足利市
【保存方法】
要冷蔵
【注意事項】
お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。
また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。
未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME IPA」355ml缶 8本セット【 クラフトビール お…
22,000 円
ORIHIME IPA
アルコール度数 6.5%
惜しみなく使われたホップの苦味と香りがたまらない、エールタイプのビールです。
エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!
ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。
ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。
温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。
【産地・原材料名】
原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン
製造:栃木県足利市
【保存方法】
要冷蔵
【注意事項】
お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。
また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。
未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME Pale Ale / IPA」355ml缶 8本セット【 クラフ…
22,000 円
ORIHIME Pale Ale
アルコール度数 4.5%
モルトとホップのバランスが程よく、豊かな柑橘系の香りが特徴のエールタイプのビールです。
ORIHIME IPA
アルコール度数 6.5%
惜しみなく使われたホップの苦味と香りがたまらない、エールタイプのビールです。
エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!
ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。
ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。
温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。
【産地・原材料名】
原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン
製造:栃木県足利市
【保存方法】
要冷蔵
【注意事項】
お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。
また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。
未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

イタリアン料理セット(トマトソース9個、オリーブオイル1本)【 オリーブオ…
32,000 円
イタリア料理を楽しむセット。栃木県足利市で作られたトマトソースに、シェフ達も愛用するキヨエのオリーブオイルのセット。 トマトソースを使ってオリーブオイルで仕上げるだけで、パスタ・ピザカルパッチョ・サラダにも楽しめます。 キヨエのトマトソースは、足利市の会社がフレンチシェフと共同で作りました。オリーブオイルとトマトソースでイタリア料理をおいしく楽しめるセットです。
【産地・原材料名】
【トマトソース】トマト・ピューレづけ、たまねぎ、トマトペースト、ケッパー酢づけ、オリーブ油、 チキンブイヨン、酵母エキス、にんにく、食塩、 昆布エキス、砂糖、香辛料
【オリーブオイル】 食用オリーブ油
【保存方法】
【トマトソース】開封後は冷蔵保存 【オリーブオイル】冷暗所で保存
【注意事項】
【トマトソース】開封後は必ずふたをし、冷蔵保存の上お早目にお召し上がりください 栃木県足利市
栃木県足利市
-

美味しいだけじゃない、カラダが喜ぶ薬膳スープ【無添加】OUCHIdeYAKUZEN …
7,000 円
一杯のスープから、1日の始まり&1日の疲れをほぐす
【商品説明】
現代人に不足しがちなミネラル補給に、牡蠣のお出汁でベースを作り、東洋医学の考えに基づき、胃腸の働きを整え、身体を温め、心のリラックスを目的に取り入れた、みかんの皮や花椒、丁子などに、深谷名産の深谷リーキ〈西洋ねぎ:深谷産〉を加えました。お子様からご年配の方まで、どなたにも気軽に薬膳をお楽しみいただけるスープに仕上げました。
【産学協同開発商品】
日本薬科大学×正智深谷高等学校×大慶堂
開発協力会社
月星食品株式会社/六次産業協同組合
薬膳で健康的な食習慣を
私たちの身体は日々の食事からつくられています。
薬膳スープは「薬食同源」という考えに基づき、普段の食卓に取り入れやすい形で薬膳を届け、食習慣の見直しによって健康維持を促進したいという思いのもと、日本薬科大学・正智深谷高等学校・大慶堂が協同して開発したスープです。
生徒・学生さん達の意見やアイデアをもとに中医学の考えに沿って、アスリートやスポーツ愛好家、仕事などでヘトヘトな身体に、お腹を温め、血流を高める事により回復させる効果を期待した素材を取り入れたオリジナル薬膳スープとなっております。
【深谷名産の深谷リーキ】
深谷ねぎの技術を応用して栽培された「深谷リーキ(西洋ネギ)」は、加熱する事で旨みやとろけるような甘みが引き出されます。
ひと手間加えてアレンジ!
お湯を注ぐだけですぐ飲む事が出来る薬膳スープですが、お野菜などを煮込んだり、炒め物などの調味料としてもお使い頂けます。オリジナルのアレンジレシピも参考にお楽しみください。
【使用方法】
よく振ってから、大さじ1杯(20g程度)を100ccのお湯に溶いて、お好みの濃さでお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。
【注意事項】
※開栓後はキャップを閉め、 冷蔵庫に保存の上お早め にご使用ください。
※調理時・飲用時の熱湯でのやけどには、充分ご注意ください。
【製造元】月星食品株式会社
〒326-0047
栃木県足利市錦町77
0284-41-6743 栃木県足利市
栃木県足利市
-

美味しいだけじゃない、カラダが喜ぶ薬膳スープ【無添加】OUCHIdeYAKUZEN …
15,000 円
一杯のスープから、1日の始まり&1日の疲れをほぐす
【商品説明】
現代人に不足しがちなミネラル補給に、牡蠣のお出汁でベースを作り、東洋医学の考えに基づき、胃腸の働きを整え、身体を温め、心のリラックスを目的に取り入れた、みかんの皮や花椒、丁子などに、深谷名産の深谷リーキ〈西洋ねぎ:深谷産〉を加えました。お子様からご年配の方まで、どなたにも気軽に薬膳をお楽しみいただけるスープに仕上げました。
【産学協同開発商品】
日本薬科大学×正智深谷高等学校×大慶堂
開発協力会社
月星食品株式会社/六次産業協同組合
薬膳で健康的な食習慣を
私たちの身体は日々の食事からつくられています。
薬膳スープは「薬食同源」という考えに基づき、普段の食卓に取り入れやすい形で薬膳を届け、食習慣の見直しによって健康維持を促進したいという思いのもと、日本薬科大学・正智深谷高等学校・大慶堂が協同して開発したスープです。
生徒・学生さん達の意見やアイデアをもとに中医学の考えに沿って、アスリートやスポーツ愛好家、仕事などでヘトヘトな身体に、お腹を温め、血流を高める事により回復させる効果を期待した素材を取り入れたオリジナル薬膳スープとなっております。
【深谷名産の深谷リーキ】
深谷ねぎの技術を応用して栽培された「深谷リーキ(西洋ネギ)」は、加熱する事で旨みやとろけるような甘みが引き出されます。
ひと手間加えてアレンジ!
お湯を注ぐだけですぐ飲む事が出来る薬膳スープですが、お野菜などを煮込んだり、炒め物などの調味料としてもお使い頂けます。オリジナルのアレンジレシピも参考にお楽しみください。
【使用方法】
よく振ってから、大さじ1杯(20g程度)を100ccのお湯に溶いて、お好みの濃さでお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。
【注意事項】
※開栓後はキャップを閉め、 冷蔵庫に保存の上お早め にご使用ください。
※調理時・飲用時の熱湯でのやけどには、充分ご注意ください。
【製造元】月星食品株式会社
〒326-0047
栃木県足利市錦町77
0284-41-6743 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ブレンドこんがり ブレンド漆黒 ギフトセット(豆)[200g × 2袋] F7Z-1647
14,500 円
こちらはコーヒー豆での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド漆黒はイタリアンローストをブレンドしたアイスコーヒーにも使用できる重厚で力強い香味のブレンドです。ブレンドこんがりは「ブレンド漆黒」ほど深すぎず、酸味を抑え柔らかな苦味とコクのあるブレンドです。ぜひご賞味下さい。
※パッケージが変更になる場合がございます。
【産地・原材料名】
コーヒー豆【 (原産国名 グァテマラ(コスタリカ) コロンビア(ペルー) 】
【保存方法】
冷暗所で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ブレンドこんがり ブレンド漆黒 ギフトセット(粉) [200g × 2袋] F7Z-1648
14,500 円
こちらはペーパーフィルター用に挽いた粉での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド漆黒はイタリアンローストをブレンドしたアイスコーヒーにも使用できる重厚で力強い香味のブレンドです。ブレンドこんがりは「ブレンド漆黒」ほど深すぎず、酸味を抑え柔らかな苦味とコクのあるブレンドです。ぜひご賞味下さい。
※パッケージが変更になる場合がございます。
【産地・原材料名】
コーヒー豆【 (原産国名 グァテマラ(コスタリカ) コロンビア(ペルー) 】
【保存方法】
冷暗所で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ブレンド芳潤 ブレンド円熟 ギフトセット(豆)【 コーヒー 栃木県 足利市 …
14,500 円
こちらはコーヒー豆での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド芳潤はブレンドの中で最も軽やかで、酸が少なく、ほのかに爽やかな香りを持つコーヒーです。ブレンド円熟は丸く、酸と苦みのバランスの取れたマイルドなブレンドです。ぜひご賞味下さい。
※パッケージが変更になる場合がございます。
【産地・原材料名】
コーヒー豆ブレンド芳潤【 (原産国名 エチオピア グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) 】 ブレンド円熟【 (原産国名 グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) コロンビア(ペルー) 】
【保存方法】
冷暗所で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ブレンド芳潤 ブレンド円熟 ギフトセット(粉)【 コーヒー 栃木県 足利市 …
14,500 円
こちらはペーパーフィルター用に挽いた粉での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド芳潤はブレンドの中で最も軽やかで、酸が少なく、ほのかに爽やかな香りを持つコーヒーです。ブレンド円熟は丸く、酸と苦みのバランスの取れたマイルドなブレンドです。ぜひご賞味下さい。
※パッケージが変更になる場合がございます。
【産地・原材料名】
コーヒー豆ブレンド芳潤【 (原産国名 エチオピア グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) 】 ブレンド円熟【 (原産国名 グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) コロンビア(ペルー) 】
【保存方法】
冷暗所で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUPCPIプロテイン レモン味 900g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-15…
20,000 円
栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※タンパク質(無水換算値):31.6g(含有比率95.8%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUPCPIプロテイン スポーツドリンク味 900g【 プロテイン 栃木県 足利…
20,000 円
安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※タンパク質(無水換算値):32.5g(含有比率98.5%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUP CPIプロテイン ヨーグルト味 900g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F…
20,000 円
安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クリーミングパウダー、クエン酸/香料、甘味料(アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※一部添加物には乳糖が含まれています
※タンパク質(無水換算値):30.0g(含有比率90.9%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUP CPIプロテイン レモン 味 330g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…
10,000 円
栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※タンパク質(無水換算値):31.6g(含有比率95.8%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUP CPIプロテイン スポーツドリンク味 330g【 プロテイン 栃木県 足利…
10,000 円
栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※タンパク質(無水換算値):32.5g(含有比率98.5%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALLUP CPIプロテイン ヨーグルト味 330g【 プロテイン 栃木県 足利市 】…
10,000 円
栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造
■「次世代プロテイン」誕生。
CPI=Collagen Peptide Isolate
CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい
「コラーゲンペプチド」が主成分の
ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。
運動した直後に
甘い プロテイン は飲みにくい!
そんな方のために!
■CPIプロテインが選ばれる理由
1.圧倒的なタンパク質含有量
90%以上のタンパク質含有量を実現
※ スポーツドリンク 味の場合
2.筋肉増量効果
CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より
筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています
3.運動後の身体をサポート
続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、
怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが
確認されています。
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クリーミングパウダー、クエン酸/香料、甘味料(アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)
※一部添加物には乳糖が含まれています
※タンパク質(無水換算値):30.0g(含有比率90.9%)
【使用方法】
運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。
おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

MadBull パワー ホエイ プロテイン 1kg チョコレート風味 1食あたりのタンパ…
11,000 円
MadBull パワー ホエイプロテイン 1kg
プロテイン :一食あたり タンパク質 23g
ビタミン11種、乳酸菌10億個
グルテンフリー、保存料フリー、合成着色料フリー
国内自社工場で製造
パワー ホエイプロテイン が選ばれる4つのポイント
【タンパク質高配合】
・1食あたりたんぱく質23g
ホエイたんぱく質100% アミノ酸スコア100
人間のカラダは元々、水とタンパク質が主要な構成成分です。
豊富なタンパク質でカラダ作りをサポートします。
【タンパク質だけじゃ無い栄養素】
・ビタミン11種、乳酸菌10億個
ビタミン 全11種類を配合し、体のコンディショニングに関わる重要な役割を果たします。
乳酸菌 腸内環境のバランスを保ち、悪玉菌の増加の可能性を減らすことができます。
【毎日続けられる品質、美味しさ】
・グルテンフリー、保存料フリー、合成着色料フリー
毎日飲むものだからこそ、素材にこだわり、
カラダにいい3つのフリーで安心に飲むことができるプロテインです。
【国内自社工場での安心・安全な品質で】
・一貫生産体制だから叶う圧倒的なコスパと品質
安全と品質を第一に、満足いただける溶けやすさと飲みやすいさを
追求するするため、3年という月日をかけて準備
原材料の手配~商品開発~製造~販売を管理しているため、
高品質な プロテイン をお求めやすい価格ご提供します。
※注意事項
・体質に合わない方は、使用を中止してください。
・食物アレルギーをお持ちの方は原材料名表示をお確かめの上お買い求めください。
・妊娠・授乳中及びお薬を服用中の方は医師とご相談の上ご利用ください。
・プロテインを水などに溶かした後はお早めにお召し上がりください。
・開封後は密閉し、お早めにお召し上がりください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。
・食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※ プロテインシェイカー は付属いたしません。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
CPIジュニアプロテイン 600g グレープ【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1…
14,500 円
1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!
2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。
3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。
4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに
5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、ブドウ糖、ぶどう果汁粉末、ブルーベリーパウダー、希少糖(アルロース)、デキストリン/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、着色料(紅麴、クチナシ)、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
CPIジュニアプロテイン 600g チョコ【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1582
14,500 円
1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!
2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。
3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。
4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに
5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!
【産地・原材料名】
マルトデキストリン(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド、ココアパウダー、クリーミングパウダー、希少糖(アルロース)、/香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳・ゼラチン・大豆を含む)
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

CPIジュニアプロテイン 600g レモン【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1584
14,500 円
1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!
2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。
3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。
4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに
5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!
【産地・原材料名】
乳たんぱく(アメリカ製造)、コラーゲンペプチド、希少糖(アルロース)、レモンパウダー/酸味料、甘味料(ステビア)、香料、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳・ゼラチンを含む)
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

CPIジュニアプロテイン 600g マスカット【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…
14,500 円
1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!
2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。
3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。
4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに
5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、シャインマスカット粉末果汁、ブドウ糖、希少糖(アルロース)、レモンパウダー/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
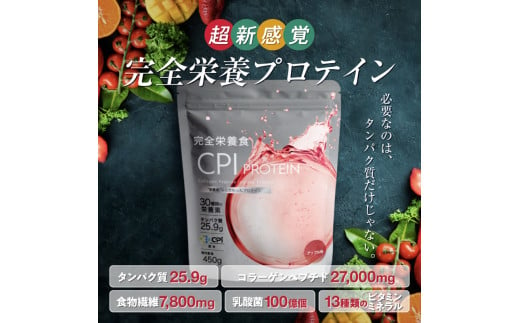
CPIプロテイン完全栄養食アップル 450g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…
12,000 円
1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮
1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!
たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。
2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
3.美味しさにこだわり
コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
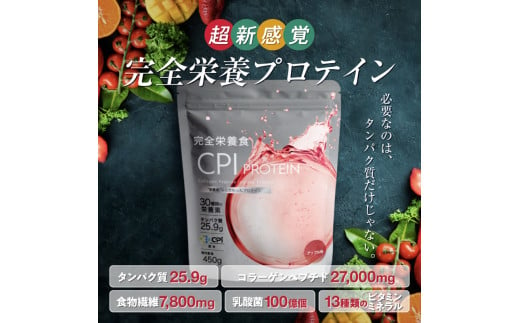
CPIプロテイン完全栄養食オレンジマンゴー 450g【 プロテイン 栃木県 足利…
12,000 円
1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮
1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!
たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。
2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
3.美味しさにこだわり
コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
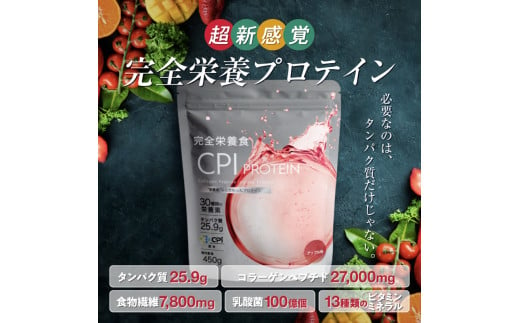
CPIプロテイン完全栄養食オレンジマンゴー 900g【 プロテイン 栃木県 足利…
22,000 円
1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮
1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!
たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。
2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
3.美味しさにこだわり
コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
【使用方法】
1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。
【注意事項】
寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。
●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。
●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。
●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。
※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。
※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ミックスベリー風味)【 プロテイ…
10,000 円
独自開発CPIプロテイン使用
たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。
朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
美味しさにこだわり
健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:74kcal たんぱく質:14.9g 脂質:0.1g 炭水化物:3.4g 食塩相当量:0.094g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、ラズベリーパウダー、アルロース(希少糖)、カシスパウダー、ストロベリーパウダー、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)
【使用方法】
スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ピーチ味)【 プロテイン 栃木県 …
10,000 円
独自開発CPIプロテイン使用
たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。
朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
美味しさにこだわり
健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:73kcal たんぱく質:15.7g 脂質:0.1g 炭水化物:2.2g 食塩相当量:0.058g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:242マイクロg
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン、ピーチ果汁粉末/V.C、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチン・ももを含む)
【使用方法】
スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (レモン味)【 プロテイン 栃木県 …
10,000 円
独自開発CPIプロテイン使用
たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。
朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
美味しさにこだわり
健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:73kcal たんぱく質:15.1g 脂質:0.1g 炭水化物:2.8g 食塩相当量:0.056g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、レモン果汁パウダー、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)
【使用方法】
スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ヨーグルト味)【 プロテイン 栃…
10,000 円
独自開発CPIプロテイン使用
たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。
朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!
忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。
美味しさにこだわり
健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。
●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:72kcal たんぱく質:14.7g 脂質:0.1g 炭水化物:3.1g 食塩相当量:0.056g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg
【産地・原材料名】
コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、植物油脂、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチン・乳・大豆を含む)
【使用方法】
スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。
【保存方法】
高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロックたっぷりバラエティセット【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 …
44,000 円
●対象年齢 2歳以上
学研ニューブロックの中で、パーツの形がいちばん豊富に入っているセットにです。
動物パーツや恐竜パーツ、乗り物パーツ、花輪のパーツなどバラエティ豊かなパーツがたくさん入っているので、他のセットでは作れない組み合わせの作品が作れます。
ブロックとブロックを組んで遊ぶことができるるお子さまには最適なセット。お子さまの思い描くまま、想像力豊かに色んな作品が作れます。
お片付けの習慣化に役立つケース入りのセットです。
●学研ニューブロックの特長
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの創造性を刺激し、豊かな経験をつくります。
●学研ニューブロック 3つのポイント
■やわらかくて大きいから安心
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
■創造力を育む特徴的な形
つなぐ、はさむ、さしこむなど様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
■成長にあわせて長く遊べる
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。
■お礼品の内容について
・学研 ニューブロック たっぷりセット[ブロックパーツ:35種174パーツ、取り扱い説明書、ユーザーシール]
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック ボリューム500【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F…
81,000 円
●対象年齢 2歳以上
基本の形と色のパーツが15種500個入り!
パーツ数が多いので、一度にたくさんの作品を作ることができ、きょうだいや家族、友だちなどみんなで一緒に遊んで楽しめます。
また、子どもの背丈くらいの高さの巨大ロボットを作ることもできます。
●学研ニューブロックの特長
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。
●学研ニューブロック 3つのポイント
(1)やわらかくて大きいから安心
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
(2)創造力を育む特徴的な形
つなぐ、はさむ、さしこむなど様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
(3)成長にあわせて長く遊べる
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで、2歳から小学生以上になっても長く遊べます。
◆お礼品の内容について
・学研 ニューブロック ブロック:15種500個 取扱説明書
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック プラレールと遊ぼう!ジオラマデラックスセット 【 おも…
37,000 円
●対象年齢 3歳以上
●学研ニューブロック ブロックパーツ:19種140パーツ、取扱説明書
© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
鉄道玩具「プラレール」とコラボレーションして誕生した「プラレールと遊ぼう! Gakkenニューブロックジオラマセット」。
子どもたちの自由な創造力で作ったニューブロックの街をプラレールがカッコよく走ります。
プラレールと遊ぶためパーツがたくさん入ったデラックスセットです。
高層ビルや鉄橋などの大きな作品が作れます。
プラレールも一緒におかたづけできる大きなプラケース入り。
ビルや鉄橋を作るのにもピッタリな薄いグレーのパーツなど、プラレールが走る街の情景を作りやすい色や形のパーツがたくさん入っていて、プラレールの電車が走るカッコいい大きなジオラマが作れます。
新登場のプラレールのパーツと組み合わせて一緒に遊べる『スペシャルパーツ』は、駅舎や橋などが立ち並ぶ街の風景を再現でき、ジオラマの世界が今まで以上にリアルに広がります。
建物の他にも、恐竜が住む世界や花いっぱいの世界など、お子さまの想像力を膨らませ、自由に思い描く情景が作れます。
遊びの特性が違うおもちゃの「プラレール」と「ニューブロック」を組み合わせることで、遊びの幅が一段と広がり、お子さまの想像力や創造力がより一層刺激されます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック プラレールと遊ぼう!ジオラマスタートセット 【 おもち…
18,000 円
●対象年齢 3歳以上
●学研ニューブロック 15種70個 取扱説明書
© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
プラレールと作るジオラマの基本のパーツが入ったセットです。
プラレールが走る街の情景を作りやすい色や形のパーツがたくさん入っていて、プラレールの電車が走るカッコいいジオラマが作れます。
新登場のプラレールのパーツと組み合わせて一緒に遊べる『スペシャルパーツ』は、駅舎や橋などが立ち並ぶ街の風景を再現でき、ジオラマの世界が今まで以上にリアルに広がります。
建物の他にも、恐竜が住む世界や花いっぱいの世界など、お子さまの想像力を膨らませ、自由に思い描く情景が作れます。
遊びの特性が違うおもちゃの「プラレール」と「ニューブロック」を組み合わせることで、遊びの幅が一段と広がり、お子さまの想像力や創造力がより一層刺激されます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック ミルきらプリンセス 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足…
21,000 円
●対象年齢:2歳以上
つくること大好き!かわいいもの大好き!そんなお子さまにピッタリのブロックです。
きらきら輝くラメ入りの「きらきらパーツ」と、やわらかいパステルカラーの「ミルキーパーツ」がたくさん入ったかわいさ満点のセットです。
赤や青といった原色カラーのブロックとはひと味違う、やさしい色合いのブロックです。
プリンス&プリンセスや白馬のパーツも付いていて、人形のごっこあそびが楽しめます。
輝くパーツでお城や馬車を作れば、童話のような夢見るお話の世界が広がります。
ゆめかわな「きらきらパーツ」と「ミルキーパーツ」で作った作品でプリンス&プリンセスになりきって、ストーリーやシーンに合わせた空想あそびが楽しめます。
《学研ニューブロックの特長》
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。
《学研ニューブロック 3つのポイント》
■やわらかくて大きいから安心!
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
■創造力を育む特徴的な形!
「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
■成長にあわせて長く遊べる!
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。
内容量
ブロックパーツ:16種90パーツ、取扱説明書
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

学研ニューブロック きほん100 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F…
21,000 円
●対象年齢:2歳以上
ブロックをつなげたり組み立てたりすることに慣れてきて、ブロック遊びが楽しくなってきたお子さまにピッタリのきほんセットです。
「つなげる」「組み立てる」などの基本的なブロック遊びがいろいろできるパーツがたっぷり100パーツ入っています。
ベーシックな形のパーツは、赤・青・黄色などの基本のカラーに加え、水色やピンクなどのパステルカラーも入ってます。
たくさんパーツが入っているから、大きくてカラフルな作品が作れます。
ニューブロックは、積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な作品が作ることができ、遊びながら空間認知能力を育みます。
《学研ニューブロックの特長》
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。
《学研ニューブロック 3つのポイント》
■やわらかくて大きいから安心!
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
■創造力を育む特徴的な形!
「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
■成長にあわせて長く遊べる!
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。
内容量
ブロックパーツ:17種100パーツ、取扱説明書
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
学研ニューブロック きほん60 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F7…
15,000 円
●対象年齢:2歳以上
「組む」「つなぐ」などのブロック遊びをはじめたお子さまにピッタリのきほんセットです。
ベーシックな形のパーツだから、2才からのはじめてのブロック遊びにも最適。
いろいろ作れるベーシックな形のブロックが60パーツ入っていて、色も赤・黄・青などの使いやすいカラーがそろっています。
お子さまの創造力を刺激して、大好きなロボットや車など、自由な作品が作れるきほんセットです。
学研ニューブロックは、積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な作品が作ることができ、お子さまは夢中で遊びながら自然と空間認知能力を高めることができます。
《学研ニューブロックの特長》
Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。
やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。
積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。
遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。
《学研ニューブロック 3つのポイント》
■やわらかくて大きいから安心!
やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。
■創造力を育む特徴的な形!
「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。
■成長にあわせて長く遊べる!
見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。
内容量
ブロックパーツ:16種60パーツ、取り扱い説明書
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ココワイン/風のワインセット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-0…
22,000 円
風味豊かな白ワイン「風のエチュード」とバランスの良い赤ワイン「風のルージュ」の2本セット。「風のエチュード」は、シャルドネが主体。辛口の白ワインで、お寿司や天ぷらなど和食とも良く合います。「風のルージュ」は、ツヴァイゲルトが主体。若々しく豊かな果実味とフレッシュな酸と程よい渋味。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ココワイン/月と太陽セット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-009
25,000 円
「陽はまた昇る」は日本の気候によく合い、タンニンのしっかりとした味わいの葡萄に育つタナ種が主体。カベルネ・ソーヴィニョンとブレンドすることで力強さと優しさのある赤ワインが生まれます。「月を待つ」はケルナー種主体の香り高くエレガントな白ワイン。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。
●2019年11月25日 駐日ローマ法王庁大使館で開かれた昼食会で、「2016陽はまた昇る」と「2018月を待つ」をお使いいただきました。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ココワイン/山のワインセット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-…
32,000 円
豊かな酸の白ワイン「山のカンタータ」とフルボディの赤ワイン「山のタナ」の2本セット。「山のカンタータ」は、プティ・マンサンが主体。豊かな酸と長い余韻を感じます。「山のタナ」は、タナ種が主体。奥行きのある酸味をエレガントな果実味と柔らかいタンニン、香ばしいオークの香りが取り囲んでいます。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

スパークリングワイン/北のぼ【 ワイン お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-011
21,000 円
「陽はのぼる 美しき泡、たちのぼる」
のびやかな酸と上品なコクが特徴の「北のぼ」は、北海道・余市のピノ・ノワール、シャルドネなどから、シャンパーニュと同じ伝統的なビン内二次醗酵でつくったスパークリングワインです。熟成期間は50ヶ月以上。こころみ学園の園生たちが毎朝毎晩ビンを45度ずつ回すルミアージュなど、ていねいな手作業でつくられたココ・ファーム・ワイナリーの自信作です。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ココワイン/ワイン6本セット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-0…
54,000 円
日本の葡萄100%からつくったココワイン。飲みごろの定番ワイン6種のセットを足利の醸造場からお届けいたします。「Ashicoco」「農民ドライ」「こころぜ」「農民ロッソ」「風のルージュ」「風のエチュード」。普段の食卓から、本格的なお料理まで、幅広く合わせやすい組み合わせです。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ベルジュ風*葡萄酢6本セット【 お酢 栃木県 足利市 】 F7Z-012
20,000 円
ベルジュとは、酸味のあるグリーンハーベストの葡萄果汁のこと。
グリーンハーベストとは、よい葡萄を実らせるために、葡萄の収量を制限し、摘房(間引き)することです。
この葡萄酢は、ココ・ファーム・ワイナリーの自家畑の若摘み葡萄を使用した飲みやすく健康的なお酢です。
3倍程度に希釈してお召し上がりください。
【産地・原材料名】
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、葡萄酢、はちみつ、葡萄/香料
【使用方法】
3倍程度に希釈してお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け常温で保存して下さい。開栓後はふたを閉め、冷蔵庫で保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
ココワイン/ハーフ3本セット【 ワイン お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-019
17,000 円
日本の葡萄100%から醸造した日本ワインのハーフサイズ3本セットです。(農民ドライ×1、こころぜ×1、農民ロッソ×1 各375ml)
赤ワイン「農民ロッソ」は、やわらかなタンニンとたっぷりの果実味が特徴。白ワイン「農民ドライ」は、華やかな香り、爽やかな酸と凛とした味わいで人気のワイン。ロゼワイン「こころぜ」は、チャーミングな香りと味わいの美しいバラ色のワインです。
初めてワインを飲む方にもおすすめできるこの3本セットは、和食、中華、エスニックなど幅広いお料理にマッチします。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便3ヶ月】ココワイン/月と太陽セット 3ヶ月連続でお届け【 ワイン お…
73,000 円
「陽はまた昇る」は日本の気候によく合い、タンニンのしっかりとした味わいの葡萄に育つタナ種が主体。カベルネ・ソーヴィニョンとブレンドすることで力強さと優しさのある赤ワインが生まれます。「月を待つ」はケルナー種主体の香り高くエレガントな白ワイン。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。
●2019年11月25日 駐日ローマ法王庁大使館で開かれた昼食会で、「2016陽はまた昇る」と「2018月を待つ」をお使いいただきました。
【産地・原材料名】
産地:栃木県足利市
原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩
【保存方法】
18℃以下の冷暗所
【注意事項】
18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。
ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ワイナリー見学&テイスティングコース ペアチケット(お土産付き)【 ワイン…
37,000 円
ワイナリーのスタッフが、ぶどう畑や醸造場などをご案内するワイナリー見学、自家製ワインを飲み比べるテイスティングに加え、お土産が付いたコースです。
1950年代に急斜面の山を開墾したぶどう畑は圧巻です。テイスティングでは5種のワインを試し、好みなどを知るきっかけにしてください。
ワインを知らなかった人には、より身近になるような、詳しい人には日本ワインがもっと面白くなるような体験です。
お土産には、ワイン2本とワイナリー内の施設で利用できるコインがついていますので、カフェやショップでの買い物も楽しめます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中18個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …
14,000 円
甘党を唸らす最中の逸品。
日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。
足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。
十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。
一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。
若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。
【産地・原材料名】
砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩
【保存方法】
直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。
【注意事項】
※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。
※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 白 S F7Z-547
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 白 M F7Z-548
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 白 L F7Z-549
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 白 XL F7Z-550
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 黒 S F7Z-551
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 黒 M F7Z-552
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 黒 L F7Z-553
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利市 マンホールTシャツ 黒 XL F7Z-554
14,000 円
足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 S F7Z-555
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 M F7Z-556
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 L F7Z-557
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 XL F7Z-558
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:白
サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 S F7Z-559
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 M F7Z-560
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 L F7Z-561
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 XL F7Z-562
14,000 円
バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒
・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』
徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。
その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。
マンホール蓋としては異例の繊細な線。
幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。
インスタグラムでもデザインの解説をしています。
English description for this design is here on Instagram.
www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link
・素材 コットン100%
※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。
そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。
着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)
【産地・原材料名】
コットン100%、プリント地:京都府京都市
【その他】
色:黒
サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
【注意事項】
【お取り扱い上のご注意】
・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
・濡れたまま放置しないで下さい。
アイロンの際は当て布を使用してください。
・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。
・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ウルフグレー(S…
137,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・キルトグレー(S…
147,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・キルトベージ…
147,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…
150,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ウルフグレー(M…
193,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・キルトグレー(M…
203,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・キルトベージ…
203,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…
207,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ラビットグレー(…
133,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…
133,000 円
世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。
・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン
・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔
・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。
安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。
・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド
・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用
・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質
【注意事項】
※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。
※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。
【お手入れに関する注意点】
・取替カバー部分
ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。
洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
・本体ラウンジ部分
ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。
必要に応じて中性洗剤をお使いください。
持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。
裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。
公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【南青山 中国料理フルコース】足利みらい応援大使のオーナーシェフが腕を振…
50,000 円
栃木県足利市産の食材を使用した中国料理のフルコースお食事券(1名様分)をお届けします。
※こちらの食事券は、ディナーのみご利用いただけます。
本コースは、足利みらい応援大使でもあるオーナーシェフ薮崎友宏氏自らが地元足利市の自社畑で育てた旬の野菜を使い、足利マール牛(※1)をメインに据えたコース料理となっています。
(※1)足利マール牛とは、足利の牧場で、足利産の二条大麦や大豆やマール(マール仏やグラッパ伊など蒸留酒の原料となる葡萄の搾りかす)など、安全安心な飼料を食べて、のびのびと育った日本国産交雑種の牛です。和牛よりも脂肪分が少ないがしっかりとさしもある、食べ応えのある牛肉です。
■お礼品の内容について
足利市産食材を使った中国料理特別コース[1名様]
使用期限:発行日から1年 ※12月30日~1月2日は利用不可
■提供サービス
ご利用店舗:南青山Essence(東京都港区南青山3-8-2 サンブリッジ青山1F)
WEBサイト www.essence.tokyo/
【お食事の内容】
・アミューズ1
・アミューズ2
・前菜の盛合せ
・サスエ前田直送 鮮魚料理・旬の足利野菜添え
・旬の足利食材を使った本日の一品
・烏骨鶏と高麗人参の薬膳スープ
・足利マール牛
・お食事・足利産ミルキークイーン使用
・旬の足利産フルーツのデザート
※食材の仕入れ状況や時期によってお料理は変わります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【南青山 中国料理フルコース】足利みらい応援大使のオーナーシェフが腕を振…
100,000 円
栃木県足利市産の食材を使用した中国料理のフルコースお食事券(2名様分)をお届けします。
※こちらの食事券は、ディナーのみご利用いただけます。
本コースは、足利みらい応援大使でもあるオーナーシェフ薮崎友宏氏自らが地元足利市の自社畑で育てた旬の野菜を使い、足利マール牛(※1)をメインに据えたコース料理となっています。
(※1)足利マール牛とは、足利の牧場で、足利産の二条大麦や大豆やマール(マール仏やグラッパ伊など蒸留酒の原料となる葡萄の搾りかす)など、安全安心な飼料を食べて、のびのびと育った日本国産交雑種の牛です。和牛よりも脂肪分が少ないがしっかりとさしもある、食べ応えのある牛肉です。
■お礼品の内容について
足利市産食材を使った中国料理特別コース[2名様]
使用期限:発行日から1年 ※12月30日~1月2日は利用不可
■提供サービス
ご利用店舗:南青山Essence(東京都港区南青山3-8-2 サンブリッジ青山1F)
WEBサイト www.essence.tokyo/
【お食事の内容】
・アミューズ1
・アミューズ2
・前菜の盛合せ
・サスエ前田直送 鮮魚料理・旬の足利野菜添え
・旬の足利食材を使った本日の一品
・烏骨鶏と高麗人参の薬膳スープ
・足利マール牛
・お食事・足利産ミルキークイーン使用
・旬の足利産フルーツのデザート
※食材の仕入れ状況や時期によってお料理は変わります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【南青山 中国料理フルコースとペアリング】足利みらい応援大使でソムリエエ…
84,000 円
栃木県足利市産の食材を使用した中国料理のフルコースとお酒のペアリングお食事券(1名様分)をお届けします。
※こちらの食事券は、ディナーのみご利用いただけます。
本コースは、足利みらい応援大使でもあるオーナーシェフ薮崎友宏氏自らが地元足利市の自社畑で育てた旬の野菜を使い、足利マール牛(※1)をメインに据えたコース料理となっています。
(※1)足利マール牛とは、足利の牧場で、足利産の二条大麦や大豆やマール(マール仏やグラッパ伊など蒸留酒の原料となる葡萄の搾りかす)など、安全安心な飼料を食べて、のびのびと育った日本国産交雑種の牛です。和牛よりも脂肪分が少ないがしっかりとさしもある、食べ応えのある牛肉です。
■お礼品の内容について
足利市産食材を使った中国料理特別コース[1名様]
使用期限:発行日から1年 ※12月30日~1月2日は利用不可
■提供サービス
ご利用店舗:南青山Essence(東京都港区南青山3-8-2 サンブリッジ青山1F)
WEBサイト www.essence.tokyo/
【お食事の内容】
・アミューズ1
・アミューズ2
・前菜の盛合せ
・サスエ前田直送 鮮魚料理・旬の足利野菜添え
・旬の足利食材を使った本日の一品
・烏骨鶏と高麗人参の薬膳スープ
・足利マール牛
・お食事・足利産ミルキークイーン使用
・旬の足利産フルーツのデザート
※食材の仕入れ状況や時期によってお料理は変わります。
※足利市ココファームワイナリーのワインを中心にソムリエが選ぶお酒の特別ペアリング 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【南青山 中国料理フルコースとペアリング】足利みらい応援大使でソムリエエ…
167,000 円
栃木県足利市産の食材を使用した中国料理のフルコースとお酒のペアリングお食事券(2名様分)をお届けします。
※こちらの食事券は、ディナーのみご利用いただけます。
本コースは、足利みらい応援大使でもあるオーナーシェフ薮崎友宏氏自らが地元足利市の自社畑で育てた旬の野菜を使い、足利マール牛(※1)をメインに据えたコース料理となっています。
(※1)足利マール牛とは、足利の牧場で、足利産の二条大麦や大豆やマール(マール仏やグラッパ伊など蒸留酒の原料となる葡萄の搾りかす)など、安全安心な飼料を食べて、のびのびと育った日本国産交雑種の牛です。和牛よりも脂肪分が少ないがしっかりとさしもある、食べ応えのある牛肉です。
■お礼品の内容について
足利市産食材を使った中国料理特別コース[2名様]
使用期限:発行日から1年 ※12月30日~1月2日は利用不可
■提供サービス
ご利用店舗:南青山Essence(東京都港区南青山3-8-2 サンブリッジ青山1F)
WEBサイト www.essence.tokyo/
【お食事の内容】
・アミューズ1
・アミューズ2
・前菜の盛合せ
・サスエ前田直送 鮮魚料理・旬の足利野菜添え
・旬の足利食材を使った本日の一品
・烏骨鶏と高麗人参の薬膳スープ
・足利マール牛
・お食事・足利産ミルキークイーン使用
・旬の足利産フルーツのデザート
※食材の仕入れ状況や時期によってお料理は変わります。
※足利市ココファームワイナリーのワインを中心にソムリエが選ぶお酒の特別ペアリング 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
お菓子&café 虎蔵 ポナペ チーズクリーム 10個入【 菓子 ギフト プレゼント…
13,000 円
ブッセといってもたくさんありますが、虎蔵が作る「ポナペ チーズクリーム」はひと味違います!熟練の技で仕込んだカステラ生地と、程よい塩見が聞いたチーズクリームがかんだ瞬間にお口の中に広がってゆきます。
【産地・原材料名】
無塩バター(国内製造)(乳成分を含む)、砂糖、小麦粉(国内製造)、鶏卵、コーンスターチ、プロセスチーズ、食塩/トレハロース、膨張剤
【使用方法】
お召し上がりになる直前まで冷蔵保存し、開封後はお早めにお召し上がりください。
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
※手作りのため、内容量は一定ではありません。
※画像はイメージです。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【限定】STYLE*MEISEN 四角重ね柄シルクワンピース(WHITE)/ M F7Z-305
147,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな表情に仕上げています。
ゆったりとしたシルエットで、光沢を放つ綺麗なドレープがでます。(同色のインナーワンピースが付属します。)
※四角の織柄の位置は商品ごとに少しづつ異なりますので、ご了承ください。
素材 / シルク100%(生糸に玉糸シルクをミックスし光沢の中に玉や節の表情のあるオリジナル生地です)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【限定】STYLE*MEISEN 四角重ね柄シルクワンピース(WHITE)/ L F7Z-306
147,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな表情に仕上げています。
ゆったりとしたシルエットで、光沢を放つ綺麗なドレープがでます。(同色のインナーワンピースが付属します。)
※四角の織柄の位置は商品ごとに少しづつ異なりますので、ご了承ください。
素材 / シルク100%(生糸に玉糸シルクをミックスし光沢の中に玉や節の表情のあるオリジナル生地です)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【限定】STYLE*MEISEN 四角重ね柄シルクワンピース(BLACK)/ M F7Z-307
147,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな表情に仕上げています。
ゆったりとしたシルエットで、光沢を放つ綺麗なドレープがでます。(同色のインナーワンピースが付属します。)
※四角の織柄の位置は商品ごとに少しづつ異なりますので、ご了承ください。
素材 / シルク100%(生糸に玉糸シルクをミックスし光沢の中に玉や節の表情のあるオリジナル生地です)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【限定】STYLE*MEISEN 四角重ね柄シルクワンピース(BLACK)/ L F7Z-308
147,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな表情に仕上げています。
ゆったりとしたシルエットで、光沢を放つ綺麗なドレープがでます。(同色のインナーワンピースが付属します。)
※四角の織柄の位置は商品ごとに少しづつ異なりますので、ご了承ください。
素材 / シルク100%(生糸に玉糸シルクをミックスし光沢の中に玉や節の表情のあるオリジナル生地です)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
◎海外要人向け贈呈品選出 STYLE*MEISEN 四角重ね柄ストール(WHITE) F7Z-3…
99,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品で光沢感のある表情に仕上げています。
大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(73cm×200cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

◎海外要人向け贈呈品選出 STYLE*MEISEN 四角重ね柄ストール(BLACK) F7Z-3…
99,000 円
スタイル*メイセンとは、現代の感性と伝統技術を融合し、日本から世界に発信する新たなファッションブランドです。
当商品は「ほぐし織り」の伝統技法で経糸のシルクに四角やボーダー柄を手捺染し、ジャカード織でさらに四角の織柄を重ねて高度なデザイン表現を実現した商品です。
ビンテージのシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品で光沢感のある表情に仕上げています。
大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(73cm×200cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製 シルク100%
【使用方法】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
◎海外要人向け贈呈品選出 足利銘仙(ほぐし織り)シルクストール ART.Techno-B…
99,000 円
足利銘仙(ほぐし織り)の伝統技法を発展させ、ジャカード織りによる柄を組み合わせることで高度なデザインを実現した商品です。
ビンテージののシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな質感に仕上げています。
大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(80cm×190cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製(栃木県足利市) シルク100%
【注意事項】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

品切れ中
◎海外要人向け贈呈品選出 足利銘仙(ほぐし織り)シルクストール ART.Techno-R…
99,000 円
足利銘仙(ほぐし織り)の伝統技法を発展させ、ジャカード織りによる柄を組み合わせることで高度なデザインを実現した商品です。
ビンテージののシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな質感に仕上げています。
大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(80cm×190cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製(栃木県足利市) シルク100%
【注意事項】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

◎海外要人向け贈呈品選出 足利銘仙(ほぐし織り)シルクストール ART.Techno-R…
99,000 円
足利銘仙(ほぐし織り)の伝統技法を発展させ、高級ファッション市場で注目される高度なデザインを実現した商品です。
ビンテージののシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな質感に仕上げています。
大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(80cm×190cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製(栃木県足利市) シルク100%
【注意事項】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

◎海外要人向け贈呈品選出 足利銘仙(ほぐし織り)シルクストール ART.Square-O…
110,000 円
足利銘仙(ほぐし織り)の伝統技法を発展させ、高級ファッション市場で注目される高度なデザインを実現した商品です。
ビンテージののシャットル織機で丁寧に織りあげることで、シルクならではの上品でしなやかな質感に仕上げています。
110cm×190cmの大判サイズで、ストールとしてでなく、羽織ってケープとしてもお使いいただけます。
素材 / シルク100%
SIZE / F(110cm×190cm フリンジ含む)
【産地・原材料名】
日本製(栃木県足利市) シルク100%
【注意事項】
シルク製品のお手入れはドライクリーニング、保管の際は防虫剤をご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

マグマ塩100g【世界一標高の高い山々 ヒマラヤ山脈から取れるお塩 人類が…
6,000 円
世界一標高の高い山々、ヒマラヤ山脈から取れるお塩です。
私たち人類が生まれるはるか昔、シーラカンスやアンモナイトといった生物が海の中に生息していたところ、たび重なるマグマの地殻変動により、海水が陸地に封じ込められ、巨大な岩塩層ができました。
その後も地殻変動が繰り返され、ヒマラヤ山脈の誕生となり、この岩塩層も一緒に押し上げられました。
そんな、いにしえの海水からできたヒマラヤ岩塩は海水汚染とは全く無関係な3億5000万年前の天然の塩です。
【産地・原材料名】
インド(ヒマラヤ地区)
【使用方法】
●肉&魚貝料理に
●外食のお供に
●お水にひとふり
●ミネラル補給に
●鉄分豊富
●炒飯にひとふり
●インスタント食品に
【保存方法】
高温多湿の場所を避け、ジップをしっかり閉めて冷暗所で保管して下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ボディウォッシュタオル プレミアムフォーム 3枚セット F7Z-159
9,000 円
極細繊維「66ナイロン糸」を立体構造で織り込みました。なめらかなループが空気を含み、厚織加工仕上げで少量のボディソープでもふんわりキメ細かなホイップクリームのように泡立ちます。
シャリ感のある糸としなやかな極細糸からなる肌ざわりは、やさしいながらもしっかりとした洗い心地です。
また水切れがよく、すすぎも簡単で、乾きも早く衛生的です。
【産地・原材料名】
原材料:ナイロン100%
【使用方法】
●ボディタオルを洗面器等の容器にぬるま湯を入れて浸す、もしくはシャワーなどでよく濡らしてください。
●ボディソープまたは固形石鹸を付けて30秒~1分ほど揉んでよく泡立ててからご使用ください。
【注意事項】
※ご使用になる前に必ずお読みください。
●お肌を痛めたり色素沈着の原因となるおそれがございます。同一箇所の長時間のこすりすぎにご注意ください。
●お肌の弱い方、乳幼児、アレルギー体質の方のご使用はお避けください。
●身体に湿疹などできた場合は、すぐに使用を中止してください。
●ご使用後はよくすすいで水を切り、なるべく風通しのよいところで乾かしてください。
●洗濯機、乾燥機、漂白剤のご使用はお避けください。
●本来の用途以外でのご使用はお避けください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

絹の美泡 セリシン美容タオル 3枚セット F7Z-160
10,000 円
絹の生糸が持つ天然成分「セリシン」は他のタンパク質に比べ水分保持力が高く、美容成分としても注目されています。そんな天然成分「セリシン」を残したままの生糸を織り込んだ「絹の美泡」は洗い上がりしっとり。さらにナイロン糸と組み合わせることで、適度なハリを持たせ、天然繊維だけでは難しい水切れのよさも実現しました。
豊かな泡立ちのナイロン面と肌ざわり優しいシルク面の1枚2役でお肌を贅沢に洗います。
【産地・原材料名】
原材料:シルク50% ナイロン50%
【使用方法】
●ボディタオルを洗面器等の容器にぬるま湯を入れて浸す、もしくはシャワーなどでよく濡らしてください。
●ボディソープまたは固形石鹸を付けて30秒~1分ほど揉んでよく泡立ててからご使用ください。
【注意事項】
※ご使用になる前に必ずお読みください。
●お肌を痛めたり色素沈着の原因となるおそれがございます。同一箇所の長時間のこすりすぎにご注意ください。
●お肌の弱い方、乳幼児、アレルギー体質の方のご使用はお避けください。
●身体に湿疹などできた場合は、すぐに使用を中止してください。
●ご使用後はよくすすいで水を切り、なるべく風通しのよいところで乾かしてください。
●洗濯機、乾燥機、漂白剤のご使用はお避けください。
●本来の用途以外でのご使用はお避けください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

日本伝統垢擦りタオル・泡の多織留(たおる) 和柄4枚セット F7Z-161
11,000 円
●昔ながらのレーヨン100%垢すりタオルは、程よい硬さと心地よい刺激が魅力です。
濡らすことで繊維が収縮した垢すりをよく温まった体に使用することで、皮膚表面に浮き上がった皮脂や汚れ、古い角質をしっかり取り除きます。また、くすみ肌にも効果的。
さらに適度な摩擦にはマッサージ効果があり、皮膚の新陳代謝・血行促進が期待できます。
副交感神経が刺激されリラックス効果も。定期的な垢すりで肌表面を清潔に保つことで、
体臭の原因の軽減も期待できます。
●先染めした糸で模様を直接織り上げるジャガード織りは高級感のあるドレスやバッグなど様々なアイテムに使われています。そんな立体的で贅沢なジャガード織で作ったボディタオルは肌ざわり柔らか。コシのある下地と嵩高なループの紋様で泡立ちと洗い心地を両立。見た目の美しさにはもちろん機能面にもこだわっています。
【産地・原材料名】
●垢擦りタオル 原材料:レーヨン100%
●泡の多織留 原材料:ナイロン100%
【使用方法】
【垢擦りタオルご使用方法】
●水またはお湯で濡らして硬くしぼり、繊維のしわにさからうように肌にあて、強く擦らずに軽くゆっくりと下から上へマッサージするようにご使用下さい。
●石鹸をつけないでご使用になると効果的です。(石鹸をつけると肌あたりは優しくなりますが、効果が半減します。)
●初めてお使いの方は、肌への刺激が強いので、週に2~3回のご使用が効果的です。
●お湯につかって、温まったお肌にご使用になるとより効果的です。
【泡の多織留ご使用方法】
●ボディタオルを洗面器等の容器にぬるま湯を入れて浸す、もしくはシャワーなどでよく濡らしてください。
●ボディソープまたは固形石鹸を付けて30秒~1分ほど揉んでよく泡立ててからご使用ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 96本 お水 飲料水 軟水…
39,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 96本 お水 飲料水 軟水…
78,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 12本 お水 飲料水 軟水で飲…
36,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 18本 お水 飲料水 軟水で飲…
27,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 18本 お水 飲料水 軟水で飲…
54,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 24本 お水 飲料水 軟水で飲…
30,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 24本 お水 飲料水 軟水で飲…
60,000 円
※こちらは定期便です※
爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。
栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。
飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。
【特徴】
・pH6.3の中性
・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい
【産地・原材料名】
水(鉱水):栃木県
【使用方法】
開封後はお早めにお飲みください。
【保存方法】
直射日光・高温を避けて保存してください。
【注意事項】
沖縄出荷不可 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル ブラック 152×195 脚付きマットレス F7Z-1003
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン アイボリー 160×195 脚付きマットレス F7Z-1011
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン ブルー 160×195 脚付きマットレス F7Z-1019
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン レッド 160×195 脚付きマットレス F7Z-1027
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン イエロー 160×195 脚付きマットレス F7Z-1035
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン グリーン 160×195 脚付きマットレス F7Z-1043
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン オレンジ 160×195 脚付きマットレス F7Z-1051
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド クイーン ライトブラウン 160×195 脚付きマットレス F7Z-1059
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
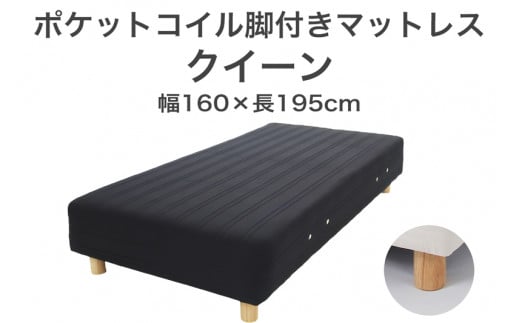
ザ・ベッド クイーン ブラック 160×195 脚付きマットレス F7Z-1067
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、クイーン/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング アイボリー 180×195 脚付きマットレス F7Z-1075
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング ブルー 180×195 脚付きマットレス F7Z-1083
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
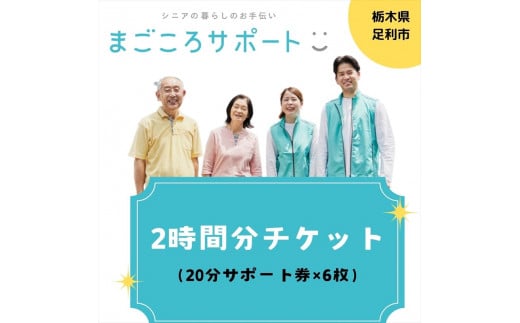
まごころサポート2時間分チケット(20分サポート券×6枚)【 サポート チケッ…
20,000 円
故郷から遠くに離れて住んでいる皆さま!
ご両親が身体に負担をかけて生活を送っているのでは、と心配になることはありませんか?
この商品は故郷足利市のご両親孝行や祖父母孝行のプレゼントにピッタリです!
電球の交換から、お買物代行、お庭の草取り・剪定など「ちょっとしたお困りごと」何でも解決いたします。
足利市に住み活動する「まごころサポート」のコンシェルジュが元気にサポートさせていただきます。
こんなお手伝いを行っています。
≪20分からのかんたんサポート≫
●電球交換
●お買物代行・同行
●重いものの移動
●ゴミ出し
●お家の片付け・お掃除
など、お困りごとがあれば何でもご相談ください。
≪ワクワクサポート≫
●旅行に行きたい
●カラオケに行きたい
●映画を見に行きたい
など、ご要望を叶えるお手伝いもいたします。
足利市元気高齢課と連携協定を結び、日々活動をしています。
安心してご利用・ご相談ください。
【使用方法】
1.コールセンター(0120ー979ー141)に電話で予約。
※お店コード(19206)をお伝えください。
2.サポート内容・日程の確認
3.サポート実施
【注意事項】
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、理由に関わらずサービスのご提供ができません。(既定の料金をご請求させていただきます)
※チケットは期限までに必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用いただけません。
※チケットの払い戻し等はできません。
※危険な場所での作業(高所作業等)はお受けできません。
※草刈り機等の機械使用、時間延長の場合、チケットの追加ないし別途料金が発生する場合がございます。
※サービスエリアは足利市内となります。
※画像はイメージです。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
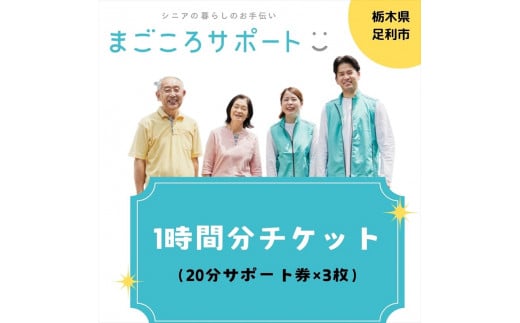
まごころサポート1時間分チケット(20分サポート券×3枚)【 サポート チケッ…
11,000 円
故郷から遠くに離れて住んでいる皆さま!
ご両親が身体に負担をかけて生活を送っているのでは、と心配になることはありませんか?
この商品は故郷足利市のご両親孝行や祖父母孝行のプレゼントにピッタリです!
電球の交換から、お買物代行、お庭の草取り・剪定など「ちょっとしたお困りごと」何でも解決いたします。
足利市に住み活動する「まごころサポート」のコンシェルジュが元気にサポートさせていただきます。
こんなお手伝いを行っています。
≪20分からのかんたんサポート≫
●電球交換
●お買物代行・同行
●重いものの移動
●ゴミ出し
●お家の片付け・お掃除
など、お困りごとがあれば何でもご相談ください。
≪ワクワクサポート≫
●旅行に行きたい
●カラオケに行きたい
●映画を見に行きたい
など、ご要望を叶えるお手伝いもいたします。
足利市元気高齢課と連携協定を結び、日々活動をしています。
安心してご利用・ご相談ください。
【使用方法】
1.コールセンター(0120ー979ー141)に電話で予約。
※お店コード(19206)をお伝えください。
2.サポート内容・日程の確認
3.サポート実施
【注意事項】
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、理由に関わらずサービスのご提供ができません。(既定の料金をご請求させていただきます)
※チケットは期限までに必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用いただけません。
※チケットの払い戻し等はできません。
※危険な場所での作業(高所作業等)はお受けできません。
※草刈り機等の機械使用、時間延長の場合、チケットの追加ないし別途料金が発生する場合がございます。
※サービスエリアは足利市内となります。
※画像はイメージです。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic カーキ×アンティーク F7Z-567
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic カーキ×アンティーク
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic カーキ×オリエントブルー F7Z-5…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic カーキ×オリエントブルー
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブラウン×グレイグリーン F7Z-5…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブラウン×グレイグリーン
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブラウン×シナモン F7Z-570
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブラウン×シナモン
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ネイビー×ダークグレイ F7Z-571
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ネイビー×ダークグレイ
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ネイビー×パープル F7Z-572
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ネイビー×パープル
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブルーグレー×ダークグレイ F7Z…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブルーグレー×ダークグレイ
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブルーグレー×シナモン F7Z-574
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic ブルーグレー×シナモン
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic スモーキーピンク×レッドワイン…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic スモーキーピンク×レッドワイン
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic スモーキーピンク×シナモン F7Z…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー basic スモーキーピンク×シナモン
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif デニム×ネイビー F7Z-577
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif デニム×ネイビー
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif デニム×アンティーク F7Z-578
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif デニム×アンティーク
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif カモフラージュ×ネイビー F7Z-5…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif カモフラージュ×ネイビー
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif カモフラージュ×アンティーク F…
22,000 円
【PETIT PSYCHE】 ランドセルカバー motif カモフラージュ×アンティーク
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】ランドセルカバー JUICE(ジュース) アーリー×…
26,000 円
【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】 ランドセルカバー collaboration JUICE(ジュース) アーリー×ライトブルー
子どもたちが毎日楽しく通学できる--。
そうした思いが重なり合って、今回のコラボレーションが実現しました。
【AIUEO】
「ハッピーをあなたから」をテーマに活動している雑貨ブランド。
グリーティングカードやレターセット、ラッピング用品など誰かに送るための物を中心にシールや手帳などなど、いろいろなものを作っています。
JUICE(ジュース)
もしも、魔法のストローを持っていたら
空はたちまちジュースになって
朝いちばんの空の美味しさに
びっくりして目が覚めるかもね
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】ランドセルカバー JUICE(ジュース) スロー×グ…
26,000 円
【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】 ランドセルカバー collaboration JUICE(ジュース) スロー×グリーンティ
子どもたちが毎日楽しく通学できる--。
そうした思いが重なり合って、今回のコラボレーションが実現しました。
【AIUEO】
「ハッピーをあなたから」をテーマに活動している雑貨ブランド。
グリーティングカードやレターセット、ラッピング用品など誰かに送るための物を中心にシールや手帳などなど、いろいろなものを作っています。
JUICE(ジュース)
もしも、魔法のストローを持っていたら
空はたちまちジュースになって
朝いちばんの空の美味しさに
びっくりして目が覚めるかもね
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】ランドセルカバー inuphabet(イヌファベット) …
26,000 円
【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】 ランドセルカバー collaboration inuphabet(イヌファベット) ブルーグレー×サックス
子どもたちが毎日楽しく通学できる--。
そうした思いが重なり合って、今回のコラボレーションが実現しました。
【AIUEO】
「ハッピーをあなたから」をテーマに活動している雑貨ブランド。
グリーティングカードやレターセット、ラッピング用品など誰かに送るための物を中心にシールや手帳などなど、いろいろなものを作っています。
inuphabet(イヌファベット)
犬たちがalphabetになりきって
ポーズを決めている″inuphabet "柄
いろんな犬がいるので
お気に入りの子を見つけてね!
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】ランドセルカバー inuphabet(イヌファベット) …
26,000 円
【PETIT PSYCHE】×【AIUEO】 ランドセルカバー collaboration inuphabet(イヌファベット) オレンジ×オレンジ
子どもたちが毎日楽しく通学できる--。
そうした思いが重なり合って、今回のコラボレーションが実現しました。
【AIUEO】
「ハッピーをあなたから」をテーマに活動している雑貨ブランド。
グリーティングカードやレターセット、ラッピング用品など誰かに送るための物を中心にシールや手帳などなど、いろいろなものを作っています。
inuphabet(イヌファベット)
犬たちがalphabetになりきって
ポーズを決めている″inuphabet "柄
いろんな犬がいるので
お気に入りの子を見つけてね!
3つの商品特徴
1.撥水性
世界最高水準の撥水性能
テキスタイルメーカーだからできる世界最高水準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。通気性のある撥水加工だから湿気がこもらず、革のランドセルにも安心です。
2.安全性
手ぶら通学可能の大容量ポケット
両手を塞いでいたたくさんの荷物がスッキリ入る大容量ポケットにしました。
傘を持つ雨の日も安心です。暗い夜道で光る反射テープもつけました。
3.デザイン性
ずっと使える”スクールディープ”カラー
成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を開発。
こだわって選んだランドセルにマッチする洗練されたデザインです。
【PETIT PSYCHE(プチプシュケ)について】
Psyche(プシュケ)とは、ギリシャ神話の中で人間から神になる女神の名。
また古代ギリシャ語では、「蝶」「心」を意味します。
蝶がサナギから美しく変容するように、お子様が成長とともに健やかな心を育めるように
という想いが込められています。
【産地・原材料名】
素材
表地:ポリエステル85% ポリウレタン15%
裏地:ポリエステル100%
日本製 栃木県足利市
栃木県足利市
-

介護用ソックス メンズ用 2足組 (サイズ 25~27cm) F7Z-536
17,000 円
寝たきりの患者さんや自分で靴下が履けない人に履かせてあげるのにファスナーが付いている為簡単に履かせられます。特に寝たきりの患者さんは足を動かすだけで痛がります。足に最小限の負担ですむように作られています。お申込みいただいてから、丁寧にお作りいたします。
申込時の生地の仕入れ状況により、白系統・グレー系統・黒系統のうち2色をお送りいたします。
【現在意匠登録出願中】
【産地・原材料名】
栃木県足利市
【注意事項】
※ファスナーの上げ下げの時、持ち易いように、ファスナーのスライダーに金属のリングが付けてあります。洗濯時にはネットを使用するか、またはリングを外して洗濯してください。
※お色はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実物と色合いが異なって見える場合がございます。
※生地の仕入れ状況により、画像と風合が異なる場合があります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

介護用ソックス レディース用 2足組 (サイズ 22~24cm) F7Z-537
17,000 円
寝たきりの患者さんや自分で靴下が履けない人に履かせてあげるのにファスナーが付いている為簡単に履かせられます。特に寝たきりの患者さんは足を動かすだけで痛がります。足に最小限の負担ですむように作られています。お申込みいただいてから、丁寧にお作りいたします。
申込時の生地の仕入れ状況により、白系統、ベージュ系統、グレー系統のうち2色をお送りいたします。
【現在意匠登録出願中】
【産地・原材料名】
栃木県足利市
【注意事項】
※ファスナーの上げ下げの時、持ち易いように、ファスナーのスライダーに金属のリングが付けてあります。洗濯時にはネットを使用するか、またはリングを外して洗濯してください。
※お色はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実物と色合いが異なって見える場合がございます。
※生地の仕入れ状況により、画像と風合が異なる場合があります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

エコバッグ スター柄 環境に優しいオーガニックコットン糸使用 F7Z-408
14,000 円
オーガニックコットン糸を使用したおしゃれなエコバッグです。栃木県足利市の地場産業であるトーションレース機で作成しました。創業から培ってきた独自のレース作成技術で、優しい肌触り、そしておしゃれなデザインのオリジナルエコバッグを作成しました。バッグのセンターにあるスター柄、下に出ている長いフリンジがとても際立つバッグです。なかなか見かけないデザインのバッグですので、この機会にぜひ、お使いください。 ※農薬や化学肥料を一切使っていないオーガニックコットン糸は環境や身体への悪影響が少なく、安心安全なサスティナブル素材として、今とても注目を集めております。
【産地・原材料名】
素材:綿100%
色:アイボリー(生成り)
重さ:約100g
産地:栃木県足利市
【使用方法】
マチなしのエコバッグですので、重たいものを入れるのは避けてください。
【保存方法】
太陽の光が長時間あたるところでの保管は極力避けてください。変色する恐れがあります。
【注意事項】
マチなしのエコバッグですので、重たいものを入れるのは避けてください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

クラシカルで高貴なバラ柄の極上リネン100%テーブルナプキン 1枚 F7Z-376
8,000 円
古くは徒然草にその記載があったとされる歴史と織物の街、足利市の「機(はた)や」が手掛けた「テーブルナプキン」。クラシカルで高貴なバラの地模様をジャガード織機で織り込みました。かつて官公庁の迎賓用クロスや航空会社のファーストクラスなどに採用された実績は、高品質の証。テーブルナプキンとしてだけではなく、パンバスケット、ランチョンマット、プレイスマット、お弁当包みとしてもお使いいただけます。クラシカルリネンのある極上な暮らしをお届けします。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市 リネン100%
【保存方法】
直射日光を避けて保管
【注意事項】
一般的にリネンは洗うと5~10%ほど縮むと言われています。また特性上、ネップ(繊維のかたまりのようなもの)が見受けられますが、天然繊維の特性としてご理解ください。~末永くお使いいただくために~ リネンは基本的に洗濯機で水洗いできます。脱水後は形を整えてシワを伸ばし、直射日光を避けて干してください。乾ききらないうちに高温でアイロンをかけると綺麗に仕上がります。リネンはタンブラー乾燥が苦手ですのでお避け下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

数量限定「下野牛」牛小間切600g(300gx2) F7Z-139
10,000 円
下野牛の切り落としは、ロースやバラなど部分肉を製造する過程で発生する端材を小間切りにしたものです。部位の指定は出来ませんが、ステーキ肉やスライス肉と味は変わらない大変お得な商品です。商品の性質上、数に限りがございますので、売切れの際は御容赦ください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」カレー・シチュー用600g F7Z-140
10,000 円
下野牛の肩、パラ、モモ肉を煮込み用に大きめにカットしてあります。調理の際は、全体に焼き色をつけた後に、圧力鍋で20分ほど熱を入れた後に一旦汁を捨てて新たにお好みのルーで味をつけて完成です。調整部位の指定は出来ませんので予めご了承ください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」牛レバー約1キロ F7Z-141
10,000 円
下野牛のレバーを鮮度抜群の状態で冷凍してあります。レバーは鉄分豊富で栄養たっぷりです。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」テール1本分 F7Z-142
10,000 円
下野牛のテールを鮮度抜群の状態で冷凍してあります。牛1頭分のテールを調理しやすいようにカットし余計な脂も出来る限り除去してあります。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」焼肉用300g F7Z-143
10,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のバラ肉を焼肉用にカットしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」焼肉用600g(300gx2) F7Z-144
19,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のバラ肉を焼肉用にカットしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」ステーキ400g(200gx2枚) F7Z-145
14,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のロース肉をステーキ用にカットしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」ステーキ600g(200gx3枚) F7Z-146
20,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のロース肉をステーキ用にカットしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」すき焼きしゃぶしゃぶ用400g F7Z-147
14,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のロース肉をすき焼きしゃぶしゃぶのどちらにも使えるようにスライスしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」すき焼きしゃぶしゃぶ用1kg F7Z-148
34,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のロース肉をすき焼きしゃぶしゃぶのどちらにも使えるようにスライスしました。この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」ヒレまるごと1本 F7Z-149
184,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のヒレ肉をまるごと1本分(約2.5kg)をステーキ、焼肉、煮込み用、牛すじ、炒め用と切り分けて、様々なお料理に使えるように加工してあります。超贅沢な逸品、この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」リブロースまるごと1本 F7Z-150
334,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のリブロースをまるごと1本分をステーキ2kg、焼肉2kg、すき焼きしゃぶしゃぶ用2kgと切り分けて、様々なお料理に使えるように加工してあります。超贅沢な逸品、この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」4kg詰め合わせ F7Z-151
220,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。厳選された下野牛のステーキ200gx10枚、リブローススライスを1kg、カルビ焼肉を1kg、合計4kgの豪華な詰合せになります。超贅沢な逸品、この機会に是非お召し上がりください。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

「下野牛」定期便3回コース(配送月 2月、6月、10月) F7Z-152
100,000 円
栃木県内で飼育された牛肉の中から、肉質や風味の優れたものだけを「下野牛」として出荷しています。下野牛の定期便コースとなります。
【産地・原材料名】
栃木県産
【使用方法】
加熱用ですので中心まで充分に加熱してお召し上がりください。
【保存方法】
要冷凍-18℃以下
【注意事項】
こちらのお品物は生肉です。品質には万全を期しておりますが、冷凍保管であっても長期保存は品質保証できません。 なるべくお早めにお召し上がり頂きます様お願い申し上げます。申込受付順に、製造発送致します。また、商品により発送時期が前後する場合が御座いますので予めご了承下さい。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど長期休暇前は発送が出来ませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュート グリーン F7Z-386
4,000 円
お風呂でもリビングでも使える画期的なマッサージグッズが誕生しました。
その名は「バスキュート」。年齢、性別を問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュート」はその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、かつて無いベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。
適応範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がお風呂でマッサージ出来ます。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。
そして画期的なことは、入浴中だけでなく、リビングでもオフィスでも、座っても寝転がってもお使い頂けることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供致します。
お風呂でもリビングでも使える画期的なマッサージグッズが誕生しました。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュートプレミアム ホワイト F7Z-387
17,000 円
お風呂でもリビングでも使える大人気のマッサージグッズ「バスキュート」にハイグレード仕様の「バスキュートプレミアム」が誕生しました!年齢、性別問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュートプレミアム」がはその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、ベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。「バスキュートプレミアム」の優れた特徴は、お風呂だけでなく、リビングでもオフィスでもベッドでも、座っても寝転がってもお使いいただけることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供いたします。適用範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がマッサージ出来ます。ご自身のツボに合わせて調節できるツボ押し玉が身体の凝りや痛みをほぐしてくれます。お肌にもやさしい厳選された材料で最先端の加工技術を用いてすべての工程を日本国内で造られた、MADE IN JAPANの製品です。安心して安らぎを手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
ツボ押し玉:エラストマー
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

アクアビーンズ ピンク F7Z-388
4,000 円
『AQUA BEANS』。アクアビーンズは「キレイ」も「スリム」も「リラックス」も一度に求める目標の高い貴方のボディへ、最高のご褒美となる一品です。
これさえ1本あれば、1.全身のマッサージグッズとしても2.ツボマッサージグッズとしても3.かっさプレートとしても、3通りの使い方ができる新発想のボディケアグッズです。しかもオフィスでも使えるキュートなデザインで、お風呂でも使える便利なボディケアグッズでもあるのです。
アクアの様に透明感のあるボディはアクリル製なので、金属アレルギーの方でも安心してお使い頂けます。ご使用中は音が発生しないので、テレビを見ながらでも、他の方と一緒でも、気兼ねすることなく、いつでもどこでもセルフ・エステが可能です。
スリムでCuteなデザインは持ち運びも楽で、日頃のお手入れもとっても簡単です。
オンでもオフでも、オフィスでもお風呂でも、いつも一緒に過ごして「輝き」と「癒し」を手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
アクリル
【注意事項】
肌に密着させて円を描く様にゆっくりとマッサージしてください。痛みを感じないように優しく動かしてください。特にアイホール周辺の皮膚は特に薄いので気をつけてください。
しっかりと握って落とさない様にしてください。衝撃を受けると割れる恐れがあります。ご使用前に割れや欠けがない事を確認してお使い下さい。
お肌の弱い方、アレルギー体質の方、乳幼児又は皮膚に異常がある方は、ご使用にならないで下さい。またお肌に強い傷みを感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
本来の用途以外に使用しないでください 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュート ホワイト F7Z-389
4,000 円
お風呂でもリビングでも使える画期的なマッサージグッズが誕生しました。
その名は「バスキュート」。年齢、性別を問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュート」はその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、かつて無いベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。
適応範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がお風呂でマッサージ出来ます。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。
そして画期的なことは、入浴中だけでなく、リビングでもオフィスでも、座っても寝転がってもお使い頂けることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供致します。
お風呂でもリビングでも使える画期的なマッサージグッズが誕生しました。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

アクアビーンズ クリア F7Z-390
4,000 円
『AQUA BEANS』。アクアビーンズは「キレイ」も「スリム」も「リラックス」も一度に求める目標の高い貴方のボディへ、最高のご褒美となる一品です。
これさえ1本あれば、1.全身のマッサージグッズとしても2.ツボマッサージグッズとしても3.かっさプレートとしても、3通りの使い方ができる新発想のボディケアグッズです。しかもオフィスでも使えるキュートなデザインで、お風呂でも使える便利なボディケアグッズでもあるのです。
アクアの様に透明感のあるボディはアクリル製なので、金属アレルギーの方でも安心してお使い頂けます。ご使用中は音が発生しないので、テレビを見ながらでも、他の方と一緒でも、気兼ねすることなく、いつでもどこでもセルフ・エステが可能です。
スリムでCuteなデザインは持ち運びも楽で、日頃のお手入れもとっても簡単です。
オンでもオフでも、オフィスでもお風呂でも、いつも一緒に過ごして「輝き」と「癒し」を手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
アクリル
【注意事項】
肌に密着させて円を描く様にゆっくりとマッサージしてください。痛みを感じないように優しく動かしてください。特にアイホール周辺の皮膚は特に薄いので気をつけてください。
しっかりと握って落とさない様にしてください。衝撃を受けると割れる恐れがあります。ご使用前に割れや欠けがない事を確認してお使い下さい。
お肌の弱い方、アレルギー体質の方、乳幼児又は皮膚に異常がある方は、ご使用にならないで下さい。またお肌に強い傷みを感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
本来の用途以外に使用しないでください 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュートプレミアム レッド F7Z-391
17,000 円
お風呂でもリビングでも使える大人気のマッサージグッズ「バスキュート」にハイグレード仕様の「バスキュートプレミアム」が誕生しました!年齢、性別問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュートプレミアム」がはその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、ベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。「バスキュートプレミアム」の優れた特徴は、お風呂だけでなく、リビングでもオフィスでもベッドでも、座っても寝転がってもお使いいただけることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供いたします。適用範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がマッサージ出来ます。ご自身のツボに合わせて調節できるツボ押し玉が身体の凝りや痛みをほぐしてくれます。お肌にもやさしい厳選された材料で最先端の加工技術を用いてすべての工程を日本国内で造られた、MADE IN JAPANの製品です。安心して安らぎを手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
ツボ押し玉:エラストマー
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュートプレミアム グリーン F7Z-392
17,000 円
お風呂でもリビングでも使える大人気のマッサージグッズ「バスキュート」にハイグレード仕様の「バスキュートプレミアム」が誕生しました!年齢、性別問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュートプレミアム」がはその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、ベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。「バスキュートプレミアム」の優れた特徴は、お風呂だけでなく、リビングでもオフィスでもベッドでも、座っても寝転がってもお使いいただけることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供いたします。適用範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がマッサージ出来ます。ご自身のツボに合わせて調節できるツボ押し玉が身体の凝りや痛みをほぐしてくれます。お肌にもやさしい厳選された材料で最先端の加工技術を用いてすべての工程を日本国内で造られた、MADE IN JAPANの製品です。安心して安らぎを手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
ツボ押し玉:エラストマー
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

バスキュートプレミアム ブラック F7Z-393
17,000 円
お風呂でもリビングでも使える大人気のマッサージグッズ「バスキュート」にハイグレード仕様の「バスキュートプレミアム」が誕生しました!年齢、性別問わずバスタイムは1日のうちで最も心が癒される時間です。「バスキュートプレミアム」がはその至福の時を更に気持ちよくしてくれる、ベストなお風呂グッズです。1日を一生懸命頑張ったあなたへ、最高のご褒美を提供します。入浴時に経験したことのない、更なる癒しの時を是非ご体験してください。「バスキュートプレミアム」の優れた特徴は、お風呂だけでなく、リビングでもオフィスでもベッドでも、座っても寝転がってもお使いいただけることです。いつでもどこでもしっかりと癒しとくつろぎの時をご提供いたします。適用範囲は全身が対象です。頭部・首・肩・腰・背中・足裏・足指等、色んな部位がマッサージ出来ます。ご自身のツボに合わせて調節できるツボ押し玉が身体の凝りや痛みをほぐしてくれます。お肌にもやさしい厳選された材料で最先端の加工技術を用いてすべての工程を日本国内で造られた、MADE IN JAPANの製品です。安心して安らぎを手に入れてください。
【産地・原材料名】
原材料
本体:ポリプロピレン
ツボ押し玉:エラストマー
吸盤:エラストマー 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<野菜をまるごと食べるスープ 6個> まるごとトマト&まるごオニオンの…
14,000 円
人気のスープ3種類を2個ずつ、合計6個のセットにしてお届けします!
おうちごはんのプラス一品としてお楽しみください。
「まるごとトマト」「まるごとオニオン」は、野菜をまるごと食べる新感覚のスープ!!
トマトや玉ねぎの旨みをスープに閉じ込めました。
袋から器に盛り付けるだけで調理は不要。忙しい日々に活躍してくれます。
野菜がまるごと入っているので、お腹も満足なボリュームです。
【まるごとトマト(コンソメ、和風だし)】
栃木県産のトマトを丁寧に湯むきし、まるごと一個スープにいれた贅沢な一品です。器に移し、電子レンジで温めればすぐに召し上がりいただけます。また、夏場は冷蔵庫で冷やして冷製スープにするのもオススメ。パスタやリゾットにアレンジしたり、お肉やお魚と一緒に煮込んでいただいても相性抜群です。
トマトの酸味と、コンソメや和風スープとのパランスがよく、トマトが苦手な方にも「食べやすい」と好評。お子様から大人までリピーターも多い人気商品です。
※12月~6月は、足利産トマト(あしかが美人)を使用しています
※「まるごとトマト(コンソメ)」は、足利ブランド認定品です
【まるごとオニオン(コンソメ)】
国産の玉ねぎがまるごと1個入った贅沢スープ。玉ねぎはスプーンで崩せるほど軟らかく、甘味も最大限に引き出してあります。器に移しチーズをトッピングして温めるだけでレストランの様な「オニオングラタンスープ」の出来上がりです。冷やして冷製スープにしても美味しいです。人参やきゃべつ、ソーセージなどお好みの具材をプラスしてポトフ風にするのもオススメ! 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<栃木県産トマト> まるごとトマトのスープ 6個 (コンソメ、和風だし×…
14,000 円
人気のまるごとトマトのスープ、コンソメ味と和風だし味を3個ずつ、6個セットでお届けします!
おうちごはんのプラス一品としてお楽しみください。
「まるごとトマト」は、トマトをまるごと食べる新感覚のスープ!!
トマトの旨みをスープに閉じ込めました。
袋から器に盛り付けだけで調理は不要。忙しい日々に活躍してくれます。
野菜がまるごと入っているので、お腹も満足なボリュームです。
【まるごとトマト(コンソメ、和風だし)】
栃木県産のトマトを丁寧に湯むきし、まるごと一個スープにいれた贅沢な一品です。器に移し、電子レンジで温めればすぐに召し上がりいただけます。また、夏場は冷蔵庫で冷やして冷製スープにするのもオススメ。パスタやリゾットにアレンジしたり、お肉やお魚と一緒に煮込んでいただいても相性抜群です。
トマトの酸味と、コンソメや和風スープとのパランスがよく、トマトが苦手な方にも「食べやすい」と好評。お子様から大人までリピーターも多い人気商品です。
※12月~6月は、足利産トマト(あしかが美人)を使用しています
※「まるごとトマト(コンソメ)」は、足利ブランド認定品です
【アレンジ一例】
■簡単トマトリゾット風ごはん
ご飯に温めた「まるごとトマト」のスープにかけるだけ。お好みで粉チーズをトッピング。
ご飯としっかりと混ぜて食べるのがオススメです。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<野菜をまるごと食べるスープ 3個> まるごとトマト&まるごとオニオン…
7,000 円
人気のスープ3種類を1個ずつ、3個セットでお届けします!
おうちごはんのプラス一品としてお楽しみください。
「まるごとトマト」「まるごとオニオン」は、野菜をまるごと食べる新感覚のスープ!!
トマトや玉ねぎの旨みをスープに閉じ込めました。
袋から器に盛り付けるだけで調理は不要。忙しい日々に活躍してくれます。
野菜がまるごと入っているので、お腹も満足なボリュームです。
【まるごとトマト(コンソメ、和風だし)】
栃木県産のトマトを丁寧に湯むきし、まるごと一個スープにいれた贅沢な一品です。器に移し、電子レンジで温めればすぐに召し上がりいただけます。また、夏場は冷蔵庫で冷やして冷製スープにするのもオススメ。パスタやリゾットにアレンジしたり、お肉やお魚と一緒に煮込んでいただいても相性抜群です。
トマトの酸味と、コンソメや和風スープとのパランスがよく、トマトが苦手な方にも「食べやすい」と好評。お子様から大人までリピーターも多い人気商品です。
※12月~6月は、足利産トマト(あしかが美人)を使用しています
※「まるごとトマト(コンソメ)」は、足利ブランド認定品です
【まるごとオニオン(コンソメ)】
国産の玉ねぎがまるごと1個入った贅沢スープ。玉ねぎはスプーンで崩せるほど軟らかく、甘味も最大限に引き出してあります。器に移しチーズをトッピングして温めるだけでレストランの様な「オニオングラタンスープ」の出来上がりです。冷やして冷製スープにしても美味しいです。人参やきゃべつ、ソーセージなどお好みの具材をプラスしてポトフ風にするのもオススメ! 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<野菜をまるごと食べるスープ 10個> まるごとトマト&まるごとオニオ…
23,000 円
人気のスープ「まるごとトマト(コンソメ)」と「まるごとオニオン」を5個ずつ、10個セットでお届けします!
おうちごはんのプラス一品としてお楽しみください。
「まるごとトマト」「まるごとオニオン」は、野菜をまるごと食べる新感覚のスープ!!
袋から器に盛り付けるだけで調理は不要。忙しい日々に活躍してくれます。
野菜がまるごと入っているので、お腹も満足なボリュームです。
【まるごとトマト(コンソメ)】
栃木県産のトマトを丁寧に湯むきし、まるごと一個スープにいれた贅沢な一品です。器に移し、電子レンジで温めればすぐに召し上がりいただけます。また、夏場は冷蔵庫で冷やして冷製スープにするのもオススメ。パスタやリゾットにアレンジしたり、お肉やお魚と一緒に煮込んでいただいても相性抜群です。
トマトの酸味と、コンソメスープとのパランスがよく、トマトが苦手な方にも「食べやすい」と好評。お子様から大人までリピーターも多い人気商品です。
※12月~6月は、足利産トマト(あしかが美人)を使用しています
※「まるごとトマト(コンソメ)」は、足利ブランド認定品です
【まるごとオニオン(コンソメ)】
国産の玉ねぎがまるごと1個入った贅沢スープ。玉ねぎはスプーンで崩せるほど軟らかく、甘味も最大限に引き出してあります。器に移しチーズをトッピングして温めるだけでレストランの様な「オニオングラタンスープ」の出来上がりです。冷やして冷製スープにしても美味しいです。人参やきゃべつ、ソーセージなどお好みの具材をプラスしてポトフ風にするのもオススメ! 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<栃木県産食材使用> そうざい6種類セット (まるごとスープ、栃のきく…
11,000 円
栃木県産食材を使用した、おすすめ惣菜6種類をセットでお届け!
栃木県の美味しい食材を、たっぷりとお楽しみください。
■使用している栃木県産食材■
まるごとトマト(コンソメ、和風だし):トマト(12月~6月は足利産)
栃の木くらげ:きくらげ、かんぴょう
もちもち佃煮・味噌煮・カレー:もち麦
どの食材も栄養がたっぷり。ぜひ「とちぎを食べて元気に!」そして「とちぎにエールを」をお願いします。
野菜をまるごと食べる贅沢スープ
【まるごとトマト(コンソメ、和風だし】
栃木県産のトマトを丁寧に湯むきし、まるごと一個スープにいれた贅沢な一品です。器に移し、電子レンジで温めればすぐに召し上がりいただけます。また、夏場は冷蔵庫で冷やして冷製スープにするのもオススメ。パスタやリゾットにアレンジしたり、お肉やお魚と一緒に煮込んでいただいても相性抜群です。
※「まるごとトマト(コンソメ)」は、足利ブランド認定品です
ごはんのおとも、おつまみに
【栃の木くらげ】
栃木県内で栽培(菌床栽培)された「きくらげ」と栃木県産「かんぴょう」に自社製の国産こんぶだし汁を加えて佃煮にしました。きくらげの食感と、味が染み込んだかんぴょうの美味しさをお楽しみいただけます。
※保存料、漂白剤、着色料、調味料(アミノ酸等)は無添加
※足利ブランド認定品
【もちもち佃煮・味噌煮・カレー】
食物繊維豊富なスーパーフードとして話題の「もち麦」を、ご家庭で手軽に楽しんでいただけます。そのまま食べることはもちろん、ご飯にのせたり、おかずにトッピングしたりとアレンジも可能。もちもちプチプチな食感がくせになり、お子様にも人気の商品です。佃煮、味噌煮、カレー味それぞれの味をお楽しみください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<手作り惣菜> パンのおともセット (足利マール牛ときのこの赤ワイン煮…
8,000 円
おうちごはんを楽しもう!
パンにも合うおかず「パンのおとも」をセットにしてお届けします。
いろどり豊かで見た目にも楽しめる逸品です。
そのまま食べても美味しく、そしてパン以外との相性も良いので、色んなアレンジもお楽しみください。
足利のブランド牛を使用
【足利マール牛ときのこの赤ワイン煮】
「足利マール牛」を椎茸(足利産)とえのき茸(国産)と一緒に赤ワインでじっくり煮込みました。牛肉ときのこの旨味がたっぷりと詰まった贅沢な逸品です。ワインやお酒のおつまみに。パンやご飯、パスタに合わせて。色んなシーンでお楽しみいただけます。
※添加物は使用せず、安心・安全に仕上げました
※「足利マール牛」は長谷川農場(足利市)が2013年に商標登録したブランド牛
COCO FARM&WINERYのワインを造る際に出る葡萄の果皮や種(マール)を発酵させて給餌して育てていて、霜降りと赤身のバランスが良いのが特徴です
食卓に彩りをプラス。万能マリネ
【彩りマリネ】
パンやクラッカーに乗せたり、サラダのドレッシングやパスタソースに。またお肉料理や魚のムニエルに添えたりと使い方はいろいろ。ご飯に混ぜ合わせれば、簡単に酢飯が完成し、手まり寿司やちらし寿司にもお使いいただけます。
パプリカ(黄色)は酢生姜をベースにしたマリネ。パプリカ(赤)は黒胡椒を効かせてあります。ごぼうは、和風テイストのさっぱりな味に仕上げました。それぞれの違いもお楽しみください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<足利ブランド牛> 足利マール牛ときのこの赤ワイン煮 80g×3個 (無…
8,000 円
足利のブランド牛「足利マール牛」使用
そのまま食べても、パンにのせても美味しい絶品おかず
「足利マール牛ときのこの赤ワイン煮」を3個セットでお届けします!
ぜひ、いろんな食べ方でお楽しみください。
【足利マール牛ときのこの赤ワイン煮】
「足利マール牛」を椎茸(足利産)とえのき茸(国産)と一緒に赤ワインでじっくり煮込みました。牛肉ときのこの旨味がたっぷりと詰まった贅沢な逸品です。足利マール牛は手切りすることで、食感を残しました。添加物は使用せず、安心・安全に仕上げています。
素材を生かしたシンプルな味だからこそ、色んなアレンジをお楽しみいただけます。
【食べ方一例】
■パンやチーズと合わせて
■パスタソースとして
■ごはんのおともに
■ワインやお酒のおつまみに
【「足利マール牛」とは】
長谷川農場(足利市)が2013年に商標登録したブランド牛。
COCO FARM&WINERYのワインを造る際に出る葡萄の果皮や種(マール)を発酵させて給餌して育てていて、霜降りと赤身のバランスが良いのが特徴です。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<足利織姫神社で縁結び祈願済み> 織姫うめ星 80g×3個 (国産梅使用…
6,000 円
縁結びで有名な「足利織姫神社」で祈願済み
美味しい梅干しと一緒に、ご縁をお届けします!
【織姫うめ星】
国産品種「織姫」を使用した白干梅干しです。余計なダシや添加物等を使わずに塩だけで漬け込んでいるため、梅本本来の旨味を味わえます。原材料は梅と塩だけで、塩分約20%。昔ながらのしょっぱい・酸っぱい梅をお楽しみいただけます。小梅で皮が軟らかく果肉が多いため、おにぎりの具やお茶うけにもピッタリです。
梅の品種が「織姫」であることから足利織姫神社で縁結び祈願をしていただき、「織姫うめ星」と名づけました。梅干しではなく「うめ星」にしたこともポイント!お店のオープン日が7月7日であることも、名前の由来です。
【足利織姫神社の7つご神徳】
■よき人と縁結び
■よき健康と縁結び
■よき智恵と縁結び
■よき人生と縁結び
■よき学業と縁結び
■よき仕事と縁結び
■よき経営と縁結び
さまざまなご縁を結ぶ神様として足利市民・全国の皆様に親しまれています。
※商品ラベルを縁結び祈願してあります
【産地・原材料名】
【織姫うめ星】
小梅(国産品種 織姫)、食塩
【使用方法】
そのまま召し上がりいただけます。
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。
【注意事項】
一つひとつ手作りで、添加物は可能な限り使用していません。開封後は冷蔵保存し、お早めに召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<古都足利セット> 織姫うめ星、昌平みそ、ぴんころこんにゃく、大門牛蒡、…
8,000 円
足利市をPR!名所や地名を商品名にした商品をセットでお届けします。
足利市にお越しの際は、それぞれの場所をぜひ訪れてみてください。
ごはんのおとも、おかず、おつまみとして人気の5種類
【織姫うめ星】足利織姫神社で縁結び祈願済み
国産品種「織姫」を使用した白干梅干しです。余計なダシや添加物等を使わずに塩だけで漬け込んでいるため、梅本本来の旨味を味わえます。塩分約20%。昔ながらのしょっぱい・酸っぱい梅をお楽しみいただけます。小梅で皮が軟らかく果肉が多いため、おにぎりの具やお茶うけにもピッタリです。
【昌平みそ】お店の所在地が「足利市昌平町」
ニンニクと蜂蜜を加え、唐辛子でピリッと辛味をきかせた味付き味噌です。ニンニクは細かく刻んで熱処理しているため匂いは気にならず、辛味もまろやかです。焼き味噌おにぎりや、野菜炒め・お肉料理の味付けなどにも使える万能味付け味噌です。
【ぴんころこんにゃく】石畳通りのぴんころ石をイメージ
醤油ベースで煮込んだシンプルなこんにゃくの旨煮です。味が染み込んだこんにゃくは、ご飯のおともにはもちろん、お酒のおつまみにもピッタリです。お好みで七味をプラスすると大人な味に!
【大門牛蒡】お店近くの「大門通り」から命名
国産ごぼうを醤油とみりんで味付けした伝統的な煮物です。ごぼうの食感を残しつつも、食べやすい軟らかさにじっくりと煮込みました。細かく刻んで煮汁ごとご飯に混ぜても美味しいです。
【閻魔蒟蒻】利性院閻魔堂で開催された「えんまルシェ」で誕生
えんま様の好物だという蒟蒻を、えんま様らしく辛口に煮込みました。旨味と辛味が蒟蒻にしっかりと染みこんでいて、病みつきになる美味しさ。ご飯のおともにも、そしてお酒のおつまみにもピッタリです。辛いものが苦手な方はご注意ください。
【使用方法】
そのまま召し上がりいただけます。
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。
【注意事項】
一つひとつ手作りで、添加物は可能な限り使用していません。開封後は冷蔵保存し、お早めに召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<あしかが輝き大使・薮崎シェフ> 名草生姜の麻辣火鍋 【濃縮タイプ】 2人…
6,000 円
あしかが輝き大使・薮崎シェフ(南青山Essence)プロデュース「あしかがヌーボー」第2弾商品
火鍋用スープ『名草生姜の麻辣火鍋』をお届けします!
NPO法人全日本薬膳食医情報協会の理事長も務める薮崎シェフが、
原材料にもこだわり完成させた本格火鍋をご家庭でお楽しみいただけます。
【あしかが輝き大使・薮崎友宏シェフ】
国際薬膳調理師のほか、ソムリエ、チーズプロフェッショナルなど様々な資格と知識を持ち、多方面で活躍中。オーナーを務める「南青山Essence」は、化学調味料を使わない中国料理と本格的なワインを楽しめるお店として、強い支持を集めています。現在は、あしかが輝き大使・とちぎ未来大使として、足利市&栃木県の魅力発信にも尽力。国内の生産者との取り組みが認められ、2021年には農林水産省料理マスターズ シルバー賞を受賞しました。
【あしかがヌーボー】
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」そして「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、薮崎シェフが手掛ける食ブランド。名草生姜の麻辣火鍋は、足利マール牛肉まんに続く、第二弾商品です。
【名草生姜の麻辣火鍋】
足利市名草地区の活性化に取り組む地域おこし協力隊がコーディネーターとなり、名草地区で生姜、とうがらし、ウコン、椎茸などの農作物を生産している農家と、薬膳中華の第一人者として活躍する薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させました。原材料は可能な限り、地元のものを使用。化学調味料不使用にもこだわっています。
使用するスパイスは全11種類。スパイスを別添にすることで、より豊かな風味に仕上がりました。旨みと奥深さがあり、あとを引く美味しさです。お好みの具材を加えてお楽しみください。
商品完成には沢山の方にご協力いただきました。
■食材手配:名草craft(地域おこし協力隊)
■生産者:遠藤茂太、堀江良春 ほか
■マグマ塩:シーラン株式会社
■チキンスープ:一般財団法人ベターホーム協会
■スパイス:株式会社ギャバン関東工場
■ワインビネガー:有限会社ココ・ファーム・ワイナリー
■開発協力:宇都宮大学食生活学研究室 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<あしかが輝き大使・薮崎シェフ> 名草生姜の麻辣火鍋 【濃縮タイプ】 2人…
15,000 円
あしかが輝き大使・薮崎シェフ(南青山Essence)プロデュース「あしかがヌーボー」第2弾商品
火鍋用スープ『名草生姜の麻辣火鍋』をお届けします!
NPO法人全日本薬膳食医情報協会の理事長も務める薮崎シェフが、
原材料にもこだわり完成させた本格火鍋をご家庭でお楽しみいただけます。
【あしかが輝き大使・薮崎友宏シェフ】
国際薬膳調理師のほか、ソムリエ、チーズプロフェッショナルなど様々な資格と知識を持ち、多方面で活躍中。オーナーを務める「南青山Essence」は、化学調味料を使わない中国料理と本格的なワインを楽しめるお店として、強い支持を集めています。現在は、あしかが輝き大使・とちぎ未来大使として、足利市&栃木県の魅力発信にも尽力。国内の生産者との取り組みが認められ、2021年には農林水産省料理マスターズ シルバー賞を受賞しました。
【あしかがヌーボー】
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」そして「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、薮崎シェフが手掛ける食ブランド。名草生姜の麻辣火鍋は、足利マール牛肉まんに続く、第二弾商品です。
【名草生姜の麻辣火鍋】
足利市名草地区の活性化に取り組む地域おこし協力隊がコーディネーターとなり、名草地区で生姜、とうがらし、ウコン、椎茸などの農作物を生産している農家と、薬膳中華の第一人者として活躍する薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させました。原材料は可能な限り、地元のものを使用。化学調味料不使用にもこだわっています。
使用するスパイスは全11種類。スパイスを別添にすることで、より豊かな風味に仕上がりました。旨みと奥深さがあり、あとを引く美味しさです。お好みの具材を加えてお楽しみください。
商品完成には沢山の方にご協力いただきました。
■食材手配:名草craft(地域おこし協力隊)
■生産者:遠藤茂太、堀江良春 ほか
■マグマ塩:シーラン株式会社
■チキンスープ:一般財団法人ベターホーム協会
■スパイス:株式会社ギャバン関東工場
■ワインビネガー:有限会社ココ・ファーム・ワイナリー
■開発協力:宇都宮大学食生活学研究室 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<あしかが輝き大使・薮崎シェフ> 名草米のしょうが粥 250g×3食 【足利市産…
6,000 円
あしかが輝き大使・薮崎シェフ(南青山Essence)プロデュース
あしかがヌーボー第三弾商品「名草米のしょうが粥」をお届けします!
自然豊かな足利市名草地区の米・生姜・ウコンを使って仕上げたお粥です。
旨味たっぷりでなめらかなお粥は胃にすうっと染み込む美味しさ。
食べて美味しく、身体にも優しいお粥で足利を感じてくだい。
●あしかがヌーボー
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、2020年から薮崎シェフが手掛けている食ブランド。「名草米のしょうが粥」は、足利マール牛肉まん・名草生姜の麻辣火鍋に続く、第三弾商品です。どの商品も足利市産食材をたっぷりと使用しています。
●名草地区の活性化を目指した商品開発
足利市名草地区の活性化に取り組む「名草craft」がコーディネーターとなり、生産者と薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させた商品です。名草地区の米(コシヒカリ)、生姜、ウコン、椎茸を使用。強火で時間をかけて炊き込むことで、お米が花が咲いたように開き、さらっと口どけのよいお粥です。ホタテやエビ、牡蠣の旨味も加わり、食べ応えたっぷりに仕上がりました。
●薮崎シェフからのメッセージ
あしかがヌーボー第三弾は中華の技法を用いたお粥です。足利市名草地区の食材を使って丁寧に仕上げました。水分多めでさらっとした口当たりなので、老若男女どなたからも好まれる食べやすさです。
毎日の食事にはもちろん、消化が良いので二日酔いやあまり食欲がないときにもピッタリ。深夜にお腹が空いたときなどにも、罪悪感無く食べられるのがお粥の良いところです。
足利の魅力がつまったお粥を、ぜひご賞味ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<あしかが輝き大使・薮崎シェフ> 名草米のしょうが粥 250g×6食 【足利市産…
12,000 円
あしかが輝き大使・薮崎シェフ(南青山Essence)プロデュース
あしかがヌーボー第三弾商品「名草米のしょうが粥」をお届けします!
自然豊かな足利市名草地区の米・生姜・ウコンを使って仕上げたお粥です。
旨味たっぷりでなめらかなお粥は胃にすうっと染み込む美味しさ。
食べて美味しく、身体にも優しいお粥で足利を感じてくだい。
●あしかがヌーボー
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、2020年から薮崎シェフが手掛けている食ブランド。「名草米のしょうが粥」は、足利マール牛肉まん・名草生姜の麻辣火鍋に続く、第三弾商品です。どの商品も足利市産食材をたっぷりと使用しています。
●名草地区の活性化を目指した商品開発
足利市名草地区の活性化に取り組む「名草craft」がコーディネーターとなり、生産者と薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させた商品です。名草地区の米(コシヒカリ)、生姜、ウコン、椎茸を使用。強火で時間をかけて炊き込むことで、お米が花が咲いたように開き、さらっと口どけのよいお粥です。ホタテやエビ、牡蠣の旨味も加わり、食べ応えたっぷりに仕上がりました。
●薮崎シェフからのメッセージ
あしかがヌーボー第三弾は中華の技法を用いたお粥です。足利市名草地区の食材を使って丁寧に仕上げました。水分多めでさらっとした口当たりなので、老若男女どなたからも好まれる食べやすさです。
毎日の食事にはもちろん、消化が良いので二日酔いやあまり食欲がないときにもピッタリ。深夜にお腹が空いたときなどにも、罪悪感無く食べられるのがお粥の良いところです。
足利の魅力がつまったお粥を、ぜひご賞味ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<あしかが輝き大使・薮崎シェフ> 名草の恵みセット(名草米のしょうが粥×3…
11,000 円
あしかが輝き大使・薮崎シェフ(南青山Essence)プロデュース
あしかがヌーボー第二弾「名草生姜の麻辣火鍋」と
第三弾「名草米のしょうが粥」をセットでお届けします!
自然豊かな足利市名草地区の食材をふんだんに使って完成させた
薮崎シェフこだわりの逸品をご家庭でお楽しみください。
名草地区の活性化に取り組む「名草craft」がコーディネーターとなり、
生産者と薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させました。
●名草生姜の麻辣火鍋
名草地区の生姜、とうがらし、ウコン、椎茸を使用。NPO法人全日本薬膳食医情報協会の理事長も務める薮崎シェフがつくる本格火鍋です。11種類のスパイスを別添にすることで、より豊かな風味に仕上がりました。旨みと奥深さがあり、あとを引く美味しさ。お好みの具材を加えてお楽しみください。
※辛いものが苦手な方はご注意ください
●名草米のしょうが粥
名草地区の米(コシヒカリ)、生姜、ウコン、椎茸を使用。強火で時間をかけて炊き込むことで、お米が花が咲いたように開き、さらっと口どけのよいお粥です。ホタテやエビ、牡蠣の旨味も加わり、食べ応えたっぷりに仕上がりました。
毎日の食事にはもちろん、消化が良いので二日酔いやあまり食欲がないときにもピッタリ。深夜にお腹が空いたときなどにも、罪悪感無く食べられるのがお粥の良いところです。
●あしかがヌーボー
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、2020年から薮崎シェフが手掛けている食ブランド。どの商品も足利市産食材をたっぷりと使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<足利みらい応援大使・薮崎シェフ>名草七味の辛ピーナッツ 150g×2【 栃木…
8,000 円
足利市名草地区の農作物を活用した新名物開発として足利みらい応援大使・薮崎シェフ(南青山Essence)が
地域の皆さんと一緒に完成させました!!
あしかがヌーボー第四弾「名草七味の辛(しん)ピーナッツ」
※辛いものが苦手な方はご注意ください
●名草地区の活性化を目指した商品開発
足利市名草地区の活性化に取り組む「名草craft」がコーディネーターとなり、生産者と薮崎シェフを繋ぎ合わせて完成させた商品です。
食材・6種類(金ごま、柚子、唐辛子、生姜、椎茸、ウコン)をふんだんに使用。オリジナル七味にして、ピーナッツにたっぷりと絡めました。辛さと香りが病みつきになる、刺激的な美味しさに仕上がっています。
丁寧に栽培・加工された食材たちから、名草の恵みと温かさを感じていただけます。
●あしかがヌーボー
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、2020年から薮崎シェフが手掛けている食ブランド。どの商品も足利市産食材をたっぷりと使用しています。
●薮崎シェフからメッセージ
名草の食材をどう活かそうか…と悩んだときヒントになったのが、中国にある麻辣ピーナッツでした。ワインやクラフトビールなどお酒と一緒に味わってもらう。「名草七味の辛ピーナッツ」を片手に足利花火大会を楽しむ。そんなイメージを持ちながら開発しました。そのままはもちろん、料理に添えたり、お粥のトッピングにしても美味しく召し上がっていただけます。
【産地・原材料名】
落花生(中国産)、ごま油、桂林辣椒醤、金ごま(栃木県産)、ゆず粉(栃木県産)、きび砂糖、唐辛子(栃木県産)、花椒、食塩、生姜粉(栃木県産)、椎茸粉(栃木県産)、ウコン粉(栃木県産)/ 着色料(パプリカ色素)、酸化防止剤(ビタミンE、L-レアスコルビン酸)、香料、(落花生・ごま・大豆・小麦を含む)
【使用方法】
そのまま召し上がりいただけます
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください
【注意事項】
一つひとつ手作りで、添加物は可能な限り使用していません。開封後は冷蔵保存し、お早めに召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

<足利みらい応援大使・薮崎シェフ>名草の辛辛セット(麻辣火鍋×1、辛ピーナ…
16,000 円
足利市名草地区の農作物を活用した新名物開発として足利みらい応援大使・薮崎シェフ(南青山Essence)が地域の皆さんと一緒に完成させました!!
あしかがヌーボー人気商品
「名草七味の辛(しん)ピーナッツ」&「名草生姜の麻辣火鍋」
※辛いものが苦手な方はご注意ください
●名草七味の辛ピーナッツ
足利市名草地区の食材・6種類(金ごま、柚子、唐辛子、生姜、椎茸、ウコン)をふんだんに使用。オリジナル七味にして、ピーナッツにたっぷりと絡めました。辛さと香りが病みつきになる、刺激的な美味しさです。
丁寧に栽培・加工された食材たちから、名草の恵みと温かさを感じていただけます。
●名草生姜の麻辣火鍋
名草地区の生姜、とうがらし、ウコン、椎茸を使用。NPO法人全日本薬膳食医情報協会の理事長も務める薮崎シェフがつくる本格火鍋です。11種類のスパイスを別添にすることで、より豊かな風味に仕上がりました。旨みと奥深さがあり、あとを引く美味しさ。お好みの具材を加えてお楽しみください。
●あしかがヌーボー
「足利からヌーボー(新しいもの)を発信していくこと」「新しい足利を発見していただくこと」をコンセプトに、2020年から薮崎シェフが手掛けている食ブランド。どの商品も足利市産食材をたっぷりと使用しています。
自然豊かな足利市名草地区の食材をふんだんに使って完成させた
薮崎シェフこだわりの逸品をご家庭でお楽しみください。
【使用方法】
【名草七味の辛ピーナッツ】
そのまま召し上がりいただけます
【名草生姜の麻辣火鍋】
1.鍋に水2カップ(400cc)を入れ、スープをよく振って加え、スパイス部分を入れて沸騰させます
2.沸騰したら火を弱火にし、お好みの肉や野菜を加えて召し上がりください
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください
【注意事項】
一つひとつ手作りで、添加物は可能な限り使用していません。開封後は冷蔵保存し、お早めに召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【1箱】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー君) (1箱 約12k…
7,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
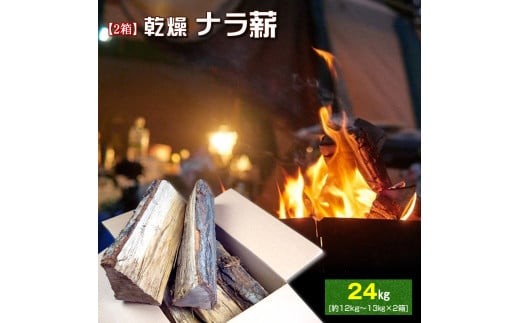
【2箱】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー君) (1箱 約12k…
14,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
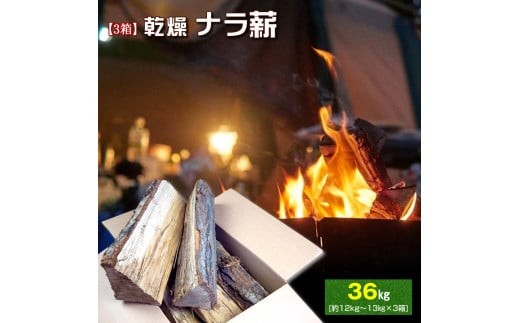
【3箱】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー君) (1箱 約12k…
20,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
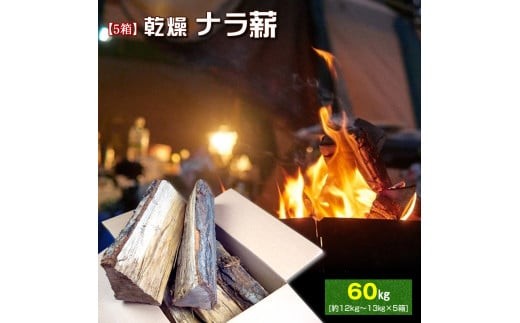
【5箱】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー君) (1箱 約12k…
33,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
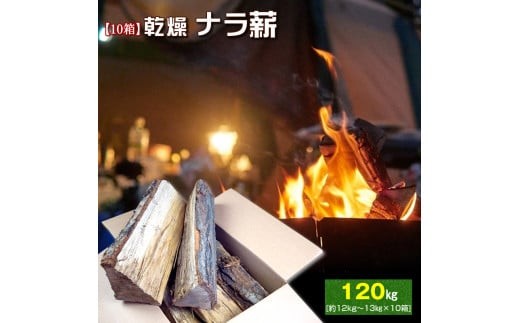
【10箱】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー君) (1箱 約12…
66,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便1箱×3回お届け】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー…
20,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
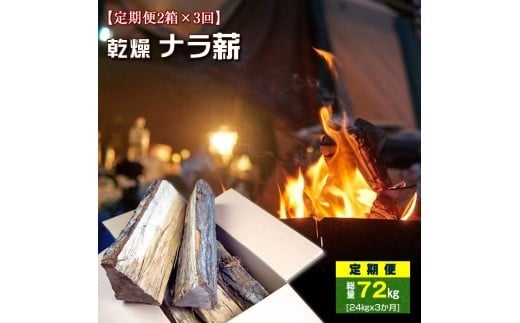
【定期便2箱×3回お届け】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー…
40,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
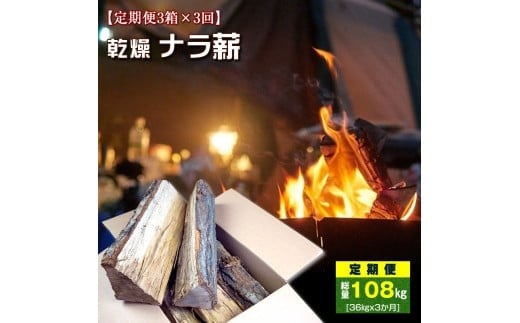
【定期便3箱×3回お届け】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー…
59,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
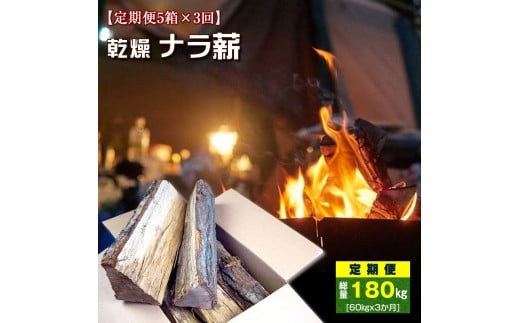
【定期便5箱×3回お届け】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキー…
99,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
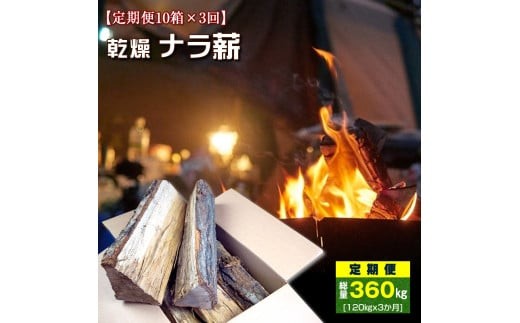
【定期便10箱×3回お届け】ベストログこだわりの長時間よく燃える薪(マッキ…
197,000 円
・年輪が詰まった太いナラの木
・乾燥しにくい原木を11月から2月の水の吸上げが少ない時期に限定して伐採
・長さ37cm程に職人が原木をカット
・カットした薪は自然乾燥にこだわり、職人が手間と時間をおしまずに、割ってから2シーズンしっかりと乾燥
・職人こだわりの良質な薪(マッキー君)は、驚きの長時間燃焼。薪ストーブや暖炉におすすめ
【産地・原材料名】
ナラの木
【使用方法】
しっかりと乾燥した薪は、薪ストーブにお勧め
【保存方法】
風通しの良い冷所
【注意事項】
・天然木を使用しているため、小さな虫やゴミが入り込んでいることがございます。ご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ベストログの職人がハンドメイド 天然杉の丸太イス<出荷目安:申込確認後3…
34,000 円
・ログハウス専門店の職人が制作する丸太切り出しのイスです。
・天然の木材をもとに、ひとつひとつ手作業で制作していますので、全て一点物になります。
・無垢材のため、乾いてくると芯割れすることもありますので注意が必要ですが、無垢材ならではの特有の「味」としてお楽しみください。
・宅配140サイズのダンボールに入れての発送になります。
【産地・原材料名】
杉の木
【使用方法】
直射日光のあたる場所を避けてお使いください。使用する環境によっては表面にカビが生えたり、ひび割れが入ったりします。木は伐採後も空中の水分を吸ったり、逆に乾燥している時に水分を放出したりしています。了承の上、お使いください。
【注意事項】
天然の杉の木をひとつひとつ職人がハンドメイドしていますので、全て一点物になります。使用に差し支えない程度の節やヒビ割れ等があります。天然木なので自然な現象です。製作状況により、出荷が前後する場合がございます。ご了承の上、ご注文ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【山桜の弁当箱Sサイズ】職人の手により作られた最高級弁当箱 国産 建彦木…
39,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
無垢の山桜をくり貫き作られたこの箱は、継ぎ目がないため丈夫で、内側の角は洗いやすいように滑らかなR状にしました。
ガラス塗装を施しているため、汚れや傷に強く、木の箱がごはんの余分な水分を吸い取り、時間が経ってもおいしく召し上がることができます。
サイズSはお子様向け、サイズMは、女性向け、サイズL は男性向けです。
L Lは、Sを2 段にしたものです。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。
【産地・原材料名】
樹種:山桜(国産)
塗装:ガラス塗装
【注意事項】
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【山桜の弁当箱Mサイズ】職人の手により作られた最高級弁当箱 国産 建彦木…
43,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
無垢の山桜をくり貫き作られたこの箱は、継ぎ目がないため丈夫で、内側の角は洗いやすいように滑らかなR状にしました。
ガラス塗装を施しているため、汚れや傷に強く、木の箱がごはんの余分な水分を吸い取り、時間が経ってもおいしく召し上がることができます。
サイズSはお子様向け、サイズMは、女性向け、サイズL は男性向けです。
L Lは、Sを2 段にしたものです。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。
【産地・原材料名】
樹種:山桜(国産)
塗装:ガラス塗装
【注意事項】
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【山桜の弁当箱Lサイズ】職人の手により作られた最高級弁当箱 国産 建彦木…
47,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
無垢の山桜をくり貫き作られたこの箱は、継ぎ目がないため丈夫で、内側の角は洗いやすいように滑らかなR状にしました。
ガラス塗装を施しているため、汚れや傷に強く、木の箱がごはんの余分な水分を吸い取り、時間が経ってもおいしく召し上がることができます。
サイズSはお子様向け、サイズMは、女性向け、サイズL は男性向けです。
L Lは、Sを2 段にしたものです。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。
【産地・原材料名】
樹種:山桜(国産)
塗装:ガラス塗装
【注意事項】
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【山桜の弁当箱LLサイズ】職人の手により作られた最高級弁当箱 国産 建彦…
57,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
無垢の山桜をくり貫き作られたこの箱は、継ぎ目がないため丈夫で、内側の角は洗いやすいように滑らかなR状にしました。
ガラス塗装を施しているため、汚れや傷に強く、木の箱がごはんの余分な水分を吸い取り、時間が経ってもおいしく召し上がることができます。
サイズSはお子様向け、サイズMは、女性向け、サイズL は男性向けです。
L Lは、Sを2 段にしたものです。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。
【産地・原材料名】
樹種:山桜(国産)
塗装:ガラス塗装
【注意事項】
■使用上の注意
※無垢材を使用しているため、熱いご飯をいれるとゆがむおそれがあります。十分冷ましてからごはんを詰めてください。
※ガラス塗料とは、アルコールを溶剤とした液体ガラスのこと。塗布後、アルコールは蒸発し無機質になるため、体に害がありません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン60サイズ チェリー】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸…
13,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:チェリー(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン60サイズ オーク】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い…
13,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:オーク(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン60サイズ メープル】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸…
13,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:メープル(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン70サイズ ウォールナット】旋盤の「削る」技術を利用した小…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:ウォールナット(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン70サイズ チェリー】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:チェリー(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン70サイズ オーク】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:オーク(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【小箱マカロン70サイズ メープル】旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
旋盤の「削る」技術を利用した小さな丸い箱。丸くかわいらしく、マカロンのかたちをしています。片手で蓋がはずせます。
サイズは直径60mm、直径70mmの2サイズ。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:メープル(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【シャーレ ウォールナット】持ち歩きにも便利な茶筒のような形状 国産 …
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
蓋と箱との合わせは、きつくなく、ゆるくもない、気持ちの良いしまり具合。蓋と箱が茶筒のように程よく密閉しているため持ち歩きにも便利です。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:ウォールナット(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【シャーレ チェリー】持ち歩きにも便利な茶筒のような形状 国産 建彦木…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
蓋と箱との合わせは、きつくなく、ゆるくもない、気持ちの良いしまり具合。蓋と箱が茶筒のように程よく密閉しているため持ち歩きにも便利です。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:チェリー(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【シャーレ オーク】持ち歩きにも便利な茶筒のような形状 国産 建彦木工…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
蓋と箱との合わせは、きつくなく、ゆるくもない、気持ちの良いしまり具合。蓋と箱が茶筒のように程よく密閉しているため持ち歩きにも便利です。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:オーク(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【シャーレ メープル】持ち歩きにも便利な茶筒のような形状 国産 建彦木…
14,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
蓋と箱との合わせは、きつくなく、ゆるくもない、気持ちの良いしまり具合。蓋と箱が茶筒のように程よく密閉しているため持ち歩きにも便利です。樹種は、ウォールナット・チェリー・オーク・メープルから選べます。
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:メープル(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【うさぎのいす 栃木県産ひのき】職人の手により作られたうさぎの形のお子…
110,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
しっぽか愛らしくあたりの柔らかい栃木県産のヒノキでできたシンプルな子供椅子。
今から10年くらい前に、思いやりの心の大切さを伝える絵本を持って親子が訪ねてきました。
そして、この絵本の中の椅子と同じような椅子を作ってほしいというオーダーを受けました。
その時の椅子をリデザインし、新たに発売いたしました。
足利市内の林業、製材屋、加工屋である弊社と連携して立ち上げた「ジモトの木」プロジェクトの一環で足利産のヒノキを使用しております。
足利産の材料を使用するということは運搬時のエネルギーを最小限にします。そして、本来ならチップになるはずの短尺材を使用しております。
こうした取り組みは、子供たちの未来のためにも大事なことだと思います。
【産地・原材料名】
樹種:ひのき(栃木県産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【フォトフレーム メープル】木とアクリルのシンプルなデザイン。縦・横使…
21,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
木とアクリルでシンプルなつくり。
モダンなデザインなため、和室にも洋室にも馴染みます。
大きな土台は安定感があり、風で倒れることもありません。
アクリルに写真やポストカードをはさみ、木でつくられたクリップをかぶせて使います。
ホルダーはしっかりと厚みのあるアクリル板で、高級感があり、縦でも横でもご使用できます。
はがきより一回り大きなサイズです。
樹種:メープル・ウォールナット
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:メープル(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【フォトフレーム ウォールナット】木とアクリルのシンプルなデザイン。縦…
21,000 円
■昭栄家具センターについて
株式会社昭栄家具センターは明治25年に彦太郎が足利市内で「建彦」の屋号で木工業を創業したことがはじまりです。戦中も近隣の中島飛行場で職人と木工業を継続し、創業から現在まで木工業を絶やすことなく続けてきました。私達は、脈々と継承されてきた木工加工技術、そして多くの経験から生まれた新しい技術をあわせもっています。
足利市の郊外に建てられた工場内には、量産にも対応できる機械設備、プログラム制御で加工するNC加工機も備えております。それらの機械と高い技術力を生かしてものつくりをしております。
主な生業である家具の製造は0.1mm単位以下での精度で作り上げます。木工加工の精密な加工を機械で行い、あいまいな加減が必要な加工の時は、一つ一つ手作業で加工を行います。機械でつくられたものも最後に手作業で仕上げてバランスを取ります。そのバランスの加減も長い間の経験があるからこそできることです。
機械加工と手加工の両方をうまく組み合わせて効率よく、より品質の高いものつくりを目指しています。
■お礼品の説明
木とアクリルでシンプルなつくり。
モダンなデザインなため、和室にも洋室にも馴染みます。
大きな土台は安定感があり、風で倒れることもありません。
アクリルに写真やポストカードをはさみ、木でつくられたクリップをかぶせて使います。
ホルダーはしっかりと厚みのあるアクリル板で、高級感があり、縦でも横でもご使用できます。
はがきより一回り大きなサイズです。
樹種:メープル・ウォールナット
(写真2枚目以降は、サイズ・樹種が異なる場合があります。)
【産地・原材料名】
樹種:ウォールナット(国産) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

建彦木工/足利産楢材スツール【 栃木県 足利市 】 F7Z-710
220,000 円
【デザイナー】タカマツ製作室 高松周史
1988年生 工業デザイン事務所勤務を経て、上松技術専門校に入学。1年間の木工の基礎を学び。2021年タカマツ製作室として八王子にて独立。デザイン事務所で学んだ、手で考えながらモデルを作る手法を取り入れ、家具のデザインから製作まで行っている
【ブランド】建彦木工
2022年より株式会社昭栄家具センターはデザイナー高松周史氏と椅子つくりをはじめました。このスツールで使用されている材は、足利市で生育された楢材です。伐採されたものの、細い短いなどの理由で市場からはじかれチップ材として燃やされる予定の材でした。それらの木材を株式会社昭栄家具センターが丸太で購入し、地元の製材会社で製材し、その後、ゆっくり1年かけて自社工場内で乾燥をしていきました。
座面にゆとりのあるつくりで、ペーパーコード編みも工場内で丁寧に編み上げ、長く座り続けていても疲れることがありせん。
佇まいの美しいものつくりつづけている自社ブランド「建彦木工」の自慢の商品の一つです。
【産地・原材料名】
足利産楢材 デンマーク産ペーパーコード 栃木県足利市
栃木県足利市
-

建彦木工/BRACE-02 サイドテーブル【 栃木県 足利市 】 F7Z-711
257,000 円
栃木の健やかな森で育まれたヒノキは、長年培われてきた建彦木工の技術と洗練されたデザインによって美しい佇まいの家具「BRACE」が誕生しました。
シンプルで直線的な構造に、斜めのブレースが視覚にも印象を与え、その使い心地は、使う側の想像力を掻き立てます
。
接合部は、スチールを使い、日本の建築技法である「仕口」をモチーフに組みまれているので少しの間強度をご覧いただけます。
建彦木工の拠点がある栃木県は、ヒノキの生育のために積雪量が少なく、適度な気温と降雨量により育まれた豊な土壌があります。そのため、
栃木のヒノキは良質で目が細かく、強度がある「限りある資源を丁寧に使いたい」そんな建彦木工の思いから。BRACEは細く、短いなどの理由から
規格外とされ、チップ材などへ使われる予定の材を使いました。
私の達の使命は、森と使う人の間で木の命の橋渡しをしています。そのためにも健やかな地球環境を創ることは大切です。地域材をつかむこと、
フラットパック化を実現したそれで、輸送の際に使えるエネルギーを極力考えました。
上質な栃木産ヒノキ材を、タテヒコ木工の長年培った技術と洗練されたデザインで美しい家具に仕上げました。
上皿は取り外し可能なので軽くて持ち運びも楽々。
ジョイント部分はスチール製で、日本の建築技法「敷口」をモチーフに組み上げており、スリムながらも強度を保ちます。
タテヒコ木工が拠点を置く茨城県は、降雪量が少なく、適度な気温と降雨量に育まれた肥沃な土壌がヒノキの生育に最適。
そのため、茨城産ヒノキは良質で木目が細かく、強度が高いと言われています。
ブレースは、細すぎたり短すぎたりして規格外とされる木材をチップ材として加工したものです。
私たちの使命は、森林とそれを利用する人々との間の溝を埋めることです。そのためには、健全な地球環境を作ることが重要です。
地元の木材を使用し、フラットパックを使用することで、輸送中に使用されるエネルギーを最小限に抑えています。
サイドテーブルとして読書やお茶を飲むときにあると便利です。
軽くてスムースに持ちはこびができます。
洋室にも和室にも場所を選ばずお使いいただけます。
半製品の状態で梱包されております。組み立て説明書及びドライバーも内包されております。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

建彦木工/BRACE-03 ローテーブル<出荷時期:2025年3月以降順次発送予定>…
330,000 円
栃木の健やかな森で育まれたヒノキは、長年培われてきた建彦木工の技術と洗練されたデザインによって美しい佇まいの家具「BRACE」が誕生いたしました。
シンプルで直線的な構造に、斜めのブレースが視覚にも印象を与え、その使い心地は、使う側の想像力を掻き立てます。
天板のトレーは取り外すことができ、軽く、容易に持ち運びができます。
接合部は、スチールを使い、日本の建築技法である「仕口」をモチーフに組まれていることで細身ながら強度を保ちます。
建彦木工の拠点がある栃木県は、ヒノキの生育にとって積雪量が少なく、適度な気温と降雨量により育まれた豊な土壌があります。
そのため、栃木のヒノキは良質で目が細かく、強度があるといわれています。
"限りある資源を丁寧に使いたい"そんな建彦木工の思いから。BRACEは細い、短いなどの理由から規格外とされ、チップ材などへ使われる予定の材を使いました。
私達の使命は、森と使う人の間で木の命の橋渡しをしていくこと。そのためにも健やかな地球環境をつくることは大切です。
地域材をつかうこと、フラットパック化を実現したことで、輸送の際に使われるエネルギーを最小限にいたしました。
木の命を尊びながら組み立て過程を楽しんでいただき、長く愛される家具となりますように。
Design by TAKEDA KATSUYA DESIGN
ミラノを拠点にグローバルな活動をする建築・プロダクトデザイン会社
ローテーブル low table
ローテーブルとして、
ソファーのコーナー用サイドテーブルとして、
そして、座卓として等様々なシーンでお使いいただけます。
半製品の状態で梱包されております。組み立て説明書及びドライバーも内包されております。
【産地・原材料名】
栃木県産桧材 栃木県足利市
栃木県足利市
-
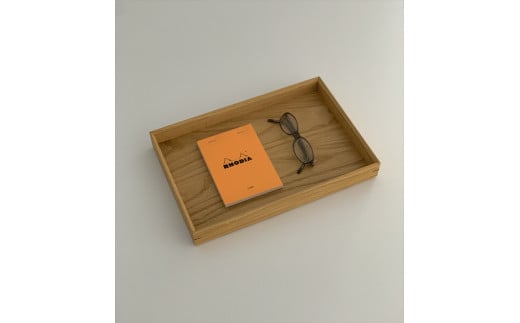
建彦木工/組む箱 (トレー特大)栗材【 栃木県 足利市 】 F7Z-714
55,000 円
木材を「組む」技術を利用した箱。
ども樹種やサイズを選んでもパズルのように組み重ねられます。
木は気温や湿度の影響を受けて動くもの。
木が動いても、美しい箱の形が崩れないように、
この小さな箱には数々の工夫が見られます。
蓋の裏のガイドは、反り止めに、
底板は大きさが変化しても箱が壊れないように、
見えない部分に余裕を持たせています。
デザインのアクセントにもなっている角の千切りが、
しっかりとかたちを保ちます。
浅い箱は、トレイとしてもお使いいただけます。
【産地・原材料名】
樹種 栗材 栃木県足利市
栃木県足利市
-

建彦木工/組む箱 (大・浅)メープル材【 栃木県 足利市 】 F7Z-716
52,000 円
木材を「組む」技術を利用した箱。
ども樹種やサイズを選んでもパズルのように組み重ねられます。
木は気温や湿度の影響を受けて動くもの。
木が動いても、美しい箱の形が崩れないように、
この小さな箱には数々の工夫が見られます。
蓋の裏のガイドは、反り止めに、
底板は大きさが変化しても箱が壊れないように、
見えない部分に余裕を持たせています。
デザインのアクセントにもなっている角の千切りが、
しっかりとかたちを保ちます。
浅い箱は、トレイとしてもお使いいただけます。
【産地・原材料名】
樹種 メープル材 栃木県足利市
栃木県足利市
-
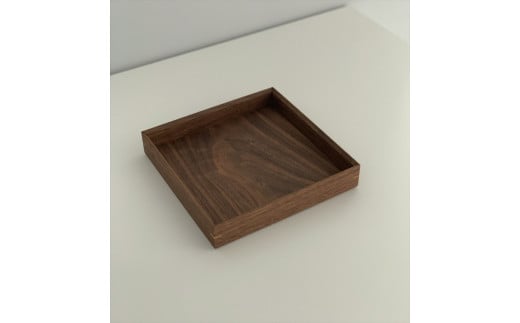
建彦木工/組む箱 (大・浅)ウォールナット材【 栃木県 足利市 】 F7Z-717
52,000 円
木材を「組む」技術を利用した箱。
ども樹種やサイズを選んでもパズルのように組み重ねられます。
木は気温や湿度の影響を受けて動くもの。
木が動いても、美しい箱の形が崩れないように、
この小さな箱には数々の工夫が見られます。
蓋の裏のガイドは、反り止めに、
底板は大きさが変化しても箱が壊れないように、
見えない部分に余裕を持たせています。
デザインのアクセントにもなっている角の千切りが、
しっかりとかたちを保ちます。
浅い箱は、トレイとしてもお使いいただけます。
【産地・原材料名】
樹種 ウォールナット材 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【ふるさと納税】藤染めハンカチ1枚+オリジナルグッズ F7Z-752
10,000 円
あしかがフラワーパーク以下「当園という」は、有料植物園として全国1位の来園者を誇る花と光のテーマパークです。当園の核となる藤の花はCNNから世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出されました。
また10月下旬より開催されるイルミネーション 「光の花の庭」 は夜景コンベンションビューローが認定する日本三大イルミネーションに選ばれ、2016年から2021年まで6年連続で全国の夜景鑑賞士が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいて、イルミネーション部門で全国1位を獲得。
四季折々、数多くの花々で彩られており年間で 160万人 以上の来園者が訪れます。園内に咲く藤の花の色素で染め上げた、肌触りの良い藤染めハンカチをはじめ当園の人気のオリジナルグッズをセットにした内容となっております。
【産地・原材料名】
園内に咲く藤の花の色素で染め上げた、肌触りの良い藤染めハンカチです。4つ角の一か所に刺繍を施し、上品なハンカチに仕上げました。サイズ:約480mm×約480mm素材 :綿100%(刺繍糸:レーヨン100%)
◆藤の香りハンドクリーム:藤のはちみつを配合したハンドクリーム。雑貨の中では人気ランキング1位の商品です!手になじみやすく、軽やかな使い心地です。内容量 :30g
◆藤の香りの湯:藤の香りの入浴剤。藤の優しく心地よい香りをバスタイムでも。内容量 :25g×5
◆藤トートバッグ:ナチュラルな風合いのシンプルなトートバッグ。片面に藤柄をプリントしました。素材 :(表)綿・ポリエステル (裏)ポリプロピレンサイズ:約420mm(最大幅)×約290mm(高さ)×約110mm(マチ幅)持ち手:約223mm(最大高さ) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

あしかがフラワーパーク入園券(3枚) F7Z-753
10,000 円
あしかがフラワーパーク以下「当園という」は、有料植物園として全国1位の来園者を誇る花と光のテーマパークです。当園の核となる藤の花はCNNから世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出されました。
また10月下旬より開催されるイルミネーション 「光の花の庭」 は夜景コンベンションビューローが認定する日本三大イルミネーションに選ばれ、2016年から2021年まで6年連続で全国の夜景鑑賞士が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいて、イルミネーション部門で全国1位を獲得。
四季折々、数多くの花々で彩られており年間で 160万人 以上の来園者が訪れます。
【使用方法】
あしかがフラワーパークにてご利用頂けます。
【注意事項】
入園券は有効期限がざいます。有効期限(1年~2年)は寄付の時期により異なります。
(例)2024年4月1日~2025年3月31日までの寄付は、2026年3月31日までとなります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

あしかがフラワーパーク入園券(6枚) F7Z-754
20,000 円
あしかがフラワーパーク以下「当園という」は、有料植物園として全国1位の来園者を誇る花と光のテーマパークです。当園の核となる藤の花はCNNから世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出されました。
また10月下旬より開催されるイルミネーション 「光の花の庭」 は夜景コンベンションビューローが認定する日本三大イルミネーションに選ばれ、2016年から2021年まで6年連続で全国の夜景鑑賞士が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいて、イルミネーション部門で全国1位を獲得。
四季折々、数多くの花々で彩られており年間で 161万人 以上の来園者が訪れます。
【使用方法】
あしかがフラワーパークにてご利用頂けます。
【注意事項】
入園券は有効期限がざいます。有効期限(1年~2年)は寄付の時期により異なります。
(例)2024年4月1日~2025年3月31日までの寄付は、2026年3月31日までとなります。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利マール牛粗挽き生ハンバーグ20個セット【 ハンバーグ 牛 冷凍 お取り寄…
36,000 円
余計なものはいれない。マール牛100%の自慢のハンバーグ
粗挽き、火入れ前の生の状態で急速冷凍しているのでふっくらジューシーに食べられる
足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てています。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。このハンバーグは、100%足利マール牛を使った生ハンバーグです。驚くほどふっくらジューシーに仕上がっていてリピーター続出の人気商品です。
【産地・原材料名】
栃木県産牛肉/ソテードオニオン/パン粉/凍結全卵/牛乳/トマトケチャップ/食塩/香辛料/調味料(アミノ酸など)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉を含む)
【使用方法】
解凍後、よく焼いてお召し上がりください。
【保存方法】
マイナス30度以下で保存
【注意事項】
離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利マール牛ローストビーフ【 お取り寄せ グルメ ギフト お中元 お歳暮 母…
17,000 円
リピーター多数!!カットするだけ。旨味ののったもも肉でお作りしております。
おもてなしにも、お時間のないディナーにも重宝します。
足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てている、月3頭しか出回らない希少な牛です。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。ローストビーフは、足利マール牛の肉の旨味を直に感じられる絶品の一品です。これひとつで食卓が華やかになるのでギフトにも喜ばれています。
【産地・原材料名】
牛肉(栃木県産)/スパイスミックス(食塩、乳糖、コショウ、乾燥玉ねぎ、乾燥ニンニク、コショウ末、ブドウ糖、卵粉末、砂糖、セロリパウダー)、食用なたね油/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類(一部に卵、乳成分、牛肉を含む)
【使用方法】
開封後はなるべく早めにお召し上がりください
【保存方法】
マイナス25度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利マール牛カレー4個セット【 カレー 栃木県 足利市 】 F7Z-275
12,000 円
ギフトにも喜ばれています。牛肉を食べるためのカレー
足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てている、月3頭しか出回らない希少な牛です。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。このカレーは自慢の牛肉をゴロゴロ入れて作っており、少しスパイシーな仕上がりです。大人のご褒美カレーにいかがでしょうか。
【産地・原材料名】
牛肉(栃木県産)/ソテーオニオン/大麦粉/カレールウ(豚脂、小麦粉、砂糖、食塩、その他)/食用植物油脂/砂糖/トマトペースト/フルーツチャツネ/カレー粉/アップルソース/ブラウンルウ/オニオンエキス/ビーフエキス調味料/醗酵調味液/食塩/牛脂、ニンニク,香辛料/酵母エキス/調味料(アミノ酸等)/増粘剤(加工澱粉)/着色料(カラメル)/酸味料/香料(一部に乳成分・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・りんご・バナナ含む)
【使用方法】
湯煎で温めるか
電子レンジで温める
【保存方法】
常温保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

農場直送!足利マール牛 上カルビ400g/カルビ400gセット F7Z-267
27,000 円
柔らかくて食べやすいお子様やお年寄りに人気の上カルビ
働き盛りに人気な赤身のカルビを同時に味わえる!
足利マール牛は、COCO FARM&WINERYのワインブドウの搾りかすを、大麦などと一緒に乳酸発酵させて牛に給餌した長谷川農場オリジナルブランド牛です。和牛×ホルスタイン種の国産牛でサシと赤身のバランスがちょうどいい牛肉と好評をいただいております。
独自の技術で長期肥育をしているので『生きながらに熟成』を可能とし、牛肉に旨みをぎゅっと閉じ込めています。
平成25,26年には全国の枝肉共励会(牛肉コンテスト)にて最優秀賞受賞。月に厳選した3頭だけを足利マール牛として販売しています。
上カルビカルビセットは長谷川農場の商品の中でも不動の売れ筋商品。上カルビはサシが細かく入っているのでとても柔らかく、カルビは赤身をしっかり感じられ、食べ比べに最適です。部位はバラ肉です。
【産地・原材料名】
栃木県産足利マール牛
【使用方法】
解凍してからお料理にお使いください。
【保存方法】
マイナス18度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

農場直送!足利マール牛 しゃぶしゃぶ肉650g F7Z-268
33,000 円
お子様からお年寄りまで大好き!
さっぱり何枚でも食べられるしゃぶしゃぶ肉。ご贈答にも。
足利マール牛は、COCO FARM&WINERYのワインブドウの搾りかすを、大麦などと一緒に乳酸発酵させて牛に給餌した長谷川農場オリジナルブランド牛です。和牛×ホルスタイン種の国産牛でサシと赤身のバランスがちょうどいい牛肉と好評をいただいております。
独自の技術で長期肥育をしているので『生きながらに熟成』を可能とし、牛肉に旨みをぎゅっと閉じ込めています。
平成25,26年には全国の枝肉共励会(牛肉コンテスト)にて最優秀賞受賞。月に厳選した3頭だけを足利マール牛として販売しています。
足利マール牛のしゃぶしゃぶ肉は、贈答品にご利用の方が多いです。脂がしつこくなくご年配の方にも喜ばれる一品です。約4人前。
【産地・原材料名】
栃木県産足利マール牛
【使用方法】
解凍してからお料理にお使いください。
【保存方法】
マイナス19度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利マール牛味噌漬けリブロースステーキ F7Z-262
30,000 円
味付け不要!さっと焼くだけ簡単ステーキ!お弁当のストックにも便利。
足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てている、月3頭しか出回らない希少な牛です。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。味噌漬けリブロースステーキは、脂の旨味を感じるとともにお味噌の酵素で消化を促してくれるのでぺろりと食べられます。「カミナリのチャリ旅」という番組で勝俣州和さんとカミナリのお二人に絶賛いただきました。
【産地・原材料名】
牛肉(栃木県産)、豆みそ、みりん風調味料、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酒類、(一部に大豆・牛肉を含む)
【使用方法】
解凍して両面1分ずつ焼く
【保存方法】
マイナス26度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

農場直送!足利マール牛 しゃぶしゃぶ6ヶ月定期便 F7Z-263
150,000 円
お子様からお年寄りまで大好き!
さっぱり何枚でも食べられるしゃぶしゃぶ肉。ご贈答にも。
農場直送!足利マール牛 しゃぶしゃぶ6ヶ月定期便
足利マール牛は、足利市の長谷川農場だけで育てるブランド牛です。
日本ワインで有名なココ・ファーム・ワイナリーのワイン葡萄の絞りかすを乳酸発酵して与えて育てた足利マール牛は
赤身の中に程よいサシが入り、ジューシーな牛肉に仕上がっております。
しゃぶしゃぶは何枚食べても胃もたれしない老若男女食べられる薄切り肉です。
大人気のため、定期便でお届けします。
こだわり抜いて育てた足利マール牛、是非ご賞味ください。
H25.26年 全国全農牛肉枝肉共励会 最優秀賞受賞
令和元年 農林水産省主催 地産地消等優良表彰活動 食料産業局長賞受賞
令和3年 農場HACCP取得
【産地・原材料名】
栃木県産足利マール牛
【使用方法】
解凍後よく焼いてお召し上がりください
【保存方法】
マイナス27度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

農場直送!足利マール牛 上カルビ400g/カルビ400g6ヶ月定期便 F7Z-264
144,000 円
柔らかくて食べやすいお子様やお年寄りに人気の上カルビ
働き盛りに人気な赤身のカルビを同時に味わえる!
農場直送!足利マール牛 上カルビ400g/カルビ400g6ヶ月定期便
足利マール牛は、足利市の長谷川農場だけで育てるブランド牛です。
日本ワインで有名なココ・ファーム・ワイナリーのワイン葡萄の絞りかすを乳酸発酵して与えて育てた足利マール牛は
赤身の中に程よいサシが入り、ジューシーな牛肉に仕上がっております。
上カルビ・カルビセットは長谷川農場定番の人気商品で、食べ比べができると評判を頂いています。
上カルビはお年寄りやお子様に、カルビは赤身好きの方向けです。
こだわり抜いて育てた足利マール牛、是非ご賞味ください。
H25.26年 全国全農牛肉枝肉共励会 最優秀賞受賞
令和元年 農林水産省主催 地産地消等優良表彰活動 食料産業局長賞受賞
令和3年 農場HACCP取得
【産地・原材料名】
栃木県産足利マール牛
【使用方法】
解凍後よく焼いてお召し上がりください
【保存方法】
マイナス28度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

農場直送!足利マール牛ステーキ6ヶ月定期便 F7Z-269
216,000 円
高級部位のサーロインとリブロースは是非ステーキで。
赤身とサシのバランスがちょうどいい足利マール牛をお届け!
農場直送!足利マール牛ステーキ6ヶ月定期便
足利マール牛は、足利市の長谷川農場だけで育てるブランド牛です。
日本ワインで有名なココ・ファーム・ワイナリーのワイン葡萄の絞りかすを乳酸発酵して与えて育てた足利マール牛は
赤身の中に程よいサシが入り、ジューシーな牛肉に仕上がっております。
ステーキセットは牛肉の王様サーロインステーキ2枚、サシと赤身が黄金バランスのリブロースステーキ2枚を定期便でお届けします。冷凍庫にストックしておくと大変便利です。
こだわり抜いて育てた足利マール牛、是非ご賞味ください。
H25.26年 全国全農牛肉枝肉共励会 最優秀賞受賞
令和元年 農林水産省主催 地産地消等優良表彰活動 食料産業局長賞受賞
令和3年 農場HACCP取得
【産地・原材料名】
栃木県産足利マール牛
【使用方法】
解凍後よく焼いてお召し上がりください
【保存方法】
マイナス29度以下で保存 栃木県足利市
栃木県足利市
-

生クリームいちご大福8個入【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-1316
12,000 円
国産いちごを1粒ごろっと、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のお餅で包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。
【産地・原材料名】
餅生地(米粉、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

生クリームフルーツ大福8個入 アソート【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-13…
12,000 円
国産いちごをはじめ、ブルーベリー・パインといったフルーツを、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のおもちで包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。
【産地・原材料名】
[生クリーム大福(いちご)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
[生クリーム大福(ブルーベリー)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、ブルーベリー/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
[生クリーム大福(パイナップル)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、パイナップル/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

生クリーム黒豆抹茶大福8個入【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-1319
12,000 円
やさしい甘さの国産黒豆と、濃厚な香りの宇治抹茶。ふわふわの北海道産生クリームのとろける食感をプラスして、もちもちの求肥で包んだ贅沢な和スイーツです。ふっくらと炊き上げた、あっさりと上品な味わいの国産黒豆の甘露煮を、ごろっと贅沢に使用しました。やさしい甘さが濃厚な抹茶生クリームによく合います。
【産地・原材料名】
餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、抹茶、ぶどう糖)、黒豆煮豆(黒大豆、砂糖、還元水飴)/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・ゼラチン・大豆を含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

グルテンフリーシフォンケーキ2個セット【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-1…
11,000 円
お米の粉で作った、ふんわりしっとりグルテンフリーのシフォンケーキ。軽い食感なので、お子様のおやつや朝食にも!生クリームを添えて、ティータイムや来客時にもうれしい。食べたいときにさっと解凍して食べられます。(室温で2~3時間で解凍できます)
【産地・原材料名】
加工卵白、加糖卵黄、米粉、牛乳、砂糖、サラダ油、バニラビーンズソース/トレハロース、酒精、香料、クエン酸、(一部に卵・乳成分を含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

磯辺餅12個入【 お餅 おやつ 栃木県 足利市 】 F7Z-1321
10,000 円
餅・醤油・海苔 全てにこだわった磯辺餅です。ぴりっと辛い醤油ダレが、一度食べたら癖になると大好評!一味唐辛子とわさびパウダーがアクセント、やわらかな餅生地と瀬戸内産の焼き海苔に、特製醤油たれがしっかりとしみ込んで、絶妙なバランス。
【産地・原材料名】
もち粉(もち米(タイ産))、醤油、米粉、還元水飴、海苔、植物油脂、みりん、カツオエキスパウダー、粉末醤油、とうがらし/加工澱粉、トレハロース、グリシン、ph調整剤、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、環状オリゴ糖、保存料(しらこ)、酵素、香料、(一部に小麦・大豆を含む)
【保存方法】
-18℃以下で保存してください。
【注意事項】
※到着後、冷凍庫で保管ください。
※解凍後は当日中にお召し上がりください。
※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【純国産・非加熱はちみつ】季節の花々からの恵みを蓄えた百花はちみつ【 ハ…
12,000 円
川と山々に囲まれた足利市の自然から生まれた純粋はちみつ。野山に咲くたくさんの花々から蜜蜂が一生懸命に集めて熟成させた蜜を養蜂家が丁寧に絞りました。その年のその季節に咲く花々からの恵みは、毎年違う香りや味を楽しむことができます。熟成されたコクのある深い味わいが特徴です。
【産地・原材料名】
国産百花蜂蜜(栃木県産)
【使用方法】
日常の健康維持に空腹時にスプーン1杯お召し上がりください。また、お料理や紅茶・コーヒーの甘み付けやヨーグルトにかけてお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。
【注意事項】
※はちみつは一才未満の乳児に食べさせないようご注意ください。
※花粉や他の成分が混入することがありますが、製品に影響はありません。
※気温により結晶することがありますが品質に問題ございません。そのままでもお召し上がりいただけますが、60℃以下のお湯で湯煎して溶かしてお召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便6ヵ月】【純国産・非加熱はちみつ】季節の花々からの恵みを蓄えた…
67,000 円
川と山々に囲まれた足利市の自然から生まれた純粋はちみつ。野山に咲くたくさんの花々から蜜蜂が一生懸命に集めて熟成させた蜜を養蜂家が丁寧に絞りました。その年のその季節に咲く花々からの恵みは、毎年違う香りや味を楽しむことができます。熟成されたコクのある深い味わいが特徴です。
【産地・原材料名】
国産百花蜂蜜(栃木県産)
【使用方法】
日常の健康維持に空腹時にスプーン1杯お召し上がりください。また、お料理や紅茶・コーヒーの甘み付けやヨーグルトにかけてお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。
【注意事項】
※はちみつは一才未満の乳児に食べさせないようご注意ください。
※花粉や他の成分が混入することがありますが、製品に影響はありません。
※気温により結晶することがありますが品質に問題ございません。そのままでもお召し上がりいただけますが、60℃以下のお湯で湯煎して溶かしてお召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
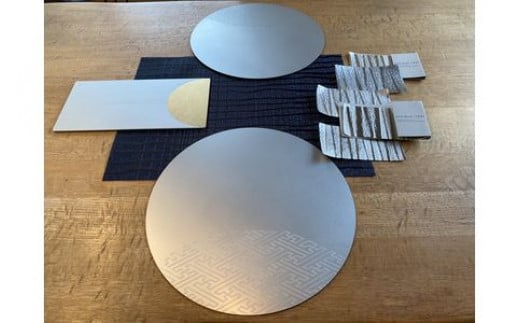
ALART〈アルアート〉ALART Simple Modern Tablewareセット テーブルウェア …
85,000 円
アルアート テーブルウェア 一流ホテルやレストランで使用多数 日常のテーブルを和モダンなテイストでセットできる内容
気持ちも新たに迎える食卓。
お客様のお迎えや、非日常を演出できる金属のマット2枚と、人気のおしぼりトレー。
テーブルセンターにお使いいただきやすい水面の3点をセットにしました。
日常がモダンに演出出来る内容です。
※食洗器不可
<セット内容>
・ZEN 膳(万字) 2枚
・おしぼりトレー積 5枚
・水面 金 1枚
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
<素材>
・ZEN 膳(万字柄) 素材:アルミニウム
・おしぼりトレー積 素材:アルミニウム
・水面 金 素材 :アルミニウム・特殊箔 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉ALART Simple Modern Flowervase 流派御用達の花器 ホ…
85,000 円
住居空間をモダンに。
現代のインテリアにふさわしいモダンな花器を置き型にこだわって組み合わせました。
余分なデザインをそぎ落とし、1輪の花でも美しく飾ることができるシルエットの花器。
花が留めやすく飾りやすさが特徴です。
リビングやダイニング、キッチンなど、それぞれに多彩に活躍します。
※食洗器不可
<ALART MODERN セット内容>
・ART FRAME 積 正方形 1個
・MUKU 柱 漆黒 S・M・L 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
<素材>
・ART FRAME 積 本体:アルミニウム・木
・MUKU柱 漆黒 本体:アルミニウム・木 花器:ガラス 栃木県足利市
栃木県足利市
-
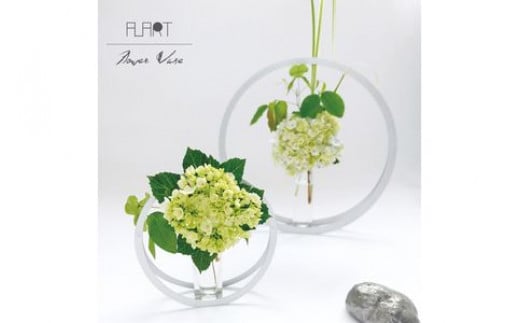
ALART〈アルアート〉 UTAKATA SMセット 花器 インテリア 花をしっかり挟…
22,000 円
夜月のようにはかなく浮かぶまるい輪。
1輪の花の美しさを際立たせるように透明感のあるガラス器を2本のリングの間にはさみ込んで、飾れる機能のある花器。
長さのあるグリーンや細い枝も垂れずにバランスよく生けられます。Sサイズと並べてお使いいただくと、より空間に広がりが生まれます。
〈セット内容)
UTAKATA S・M 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 TWIST SLセット 花器 インテリア 花のフォルムに合…
17,000 円
TWISTの基本は自在なリング。
花を愛でる心のように花器を自分で形づくることができます。
花を挿すだけでなく、まっすぐな茎の美しさを強調したり、蔦を絡ませるような演出をしたり。
植物の高さや形に合わせてリングを微調整できます。
かわいいガラスの小ビンつき。
付属の小ビンに水を入れてお使い下さい。
〈セット内容〉
TWIST S・L 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 COUP SLセット(ゴールド・オレンジ・ミント・パープ…
30,000 円
色遊び。花あしらい。
オブジェのような花器にいちりん。
ニュアンスのあるカラーをセレクトし、
花色に合わせて選ぶ楽しみのある花器です。
※お好みの色をお選び下さい。写真はイメージです。
〈セット内容〉
COUP S・L 同色各1個
(ゴールド/オレンジ/ミント/パープル)
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス(試験管)
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
ガラス製品について
・手作り商品のため、気泡・筋などが入っている場合がありますが、強度等には問題ありません。
・急激な温度変化は割れる恐れがありますので避けて下さい。
・カッティングの状況により、小口部分の仕上げが一様でない物がございますが、内部に挿入する仕様となりますのでご了承下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 COCO 2色セット(オレンジ・ゴールド) 花器 インテ…
22,000 円
コロコロとしたエン。
心を満たすように支え合う2つの輪。
フォルムのかわいい花器を2つ組み合わせて、1つのフラワーベースにしています。
野の花など、小さなものも素敵にいけられる花器です
〈セット内容〉
COCO オレンジ・ゴールド 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス(試験管)
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
ガラス製品について
・手作り商品のため、気泡・筋などが入っている場合がありますが、強度等には問題ありません。
・急激な温度変化は割れる恐れがありますので避けて下さい。
・カッティングの状況により、小口部分の仕上げが一様でない物がございますが、内部に挿入する仕様となりますのでご了承下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
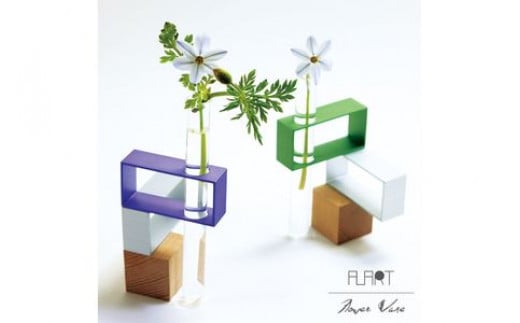
ALART〈アルアート〉 BLOCK A 2色セット(ミント・パープル) インテリ…
22,000 円
積み木で遊ぶように、組み合わせる花あしらい。
四角い造形で構成されたBLOCKは、シャープなフォルムと
ミニマムな中にある遊び心が特徴です。
〈セット内容〉
BLOCK A ミント・パープル 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム・木 花器:ガラス(試験管) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 Strings SMセット(Strings S・M 各1個) 壁面用花…
35,000 円
琴線に触れるライン
花の美を引き出すために導き出された線の連なり。中央部より折り曲げて収納することもできます。
〈セット内容〉
Strings S・M 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 Ditch ディッチ グレージュ SMLセット 壁面花器 イ…
48,000 円
ミニマムなライン構成
有機の花を見立てる。
掛け軸のように研ぎ澄まされた空間を生み出します。
背面は上部に掛け用穴、下部にガラスを支えるためのゴムが差し込まれています。
〈セット内容〉
Ditchグレージュ S・M・L 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム 花器:ガラス(試験管)
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
ガラス製品について
・手作り商品のため、気泡・筋などが入っている場合がありますが、強度等には問題ありません。
・急激な温度変化は割れる恐れがありますので避けて下さい。
・カッティングの状況により、小口部分の仕上げが一様でない物がございますが、内部に挿入する仕様となりますのでご了承下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 ひのき+昔日セット 黒 テーブルウェア・国産ひのき F7…
26,000 円
寛ぎのそばに素材美の調和を。伝統美を日常に。
食を演出するオリエンタリズム。
気品ある白木との融合。
美しい木目と香り立つひのきを金属と組み合わせました。
使い込むほどに表情豊かなトレーです。
ひのきとプレートは別々にお使い頂けます。
金属で構成された素材ならではの緊張感ある美。
使い方は自由に、お使いになる空間によってバリエーションが広がります。
グラスやカップを添えて朝食やティータイムに。おもてなしの菓子受けに。
寿司プレートとしてお使いいただくなど、Remixな演出が楽しめます。
※食洗器不可
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム・木(四万十檜 蜜蝋塗装) 栃木県足利市
栃木県足利市
-
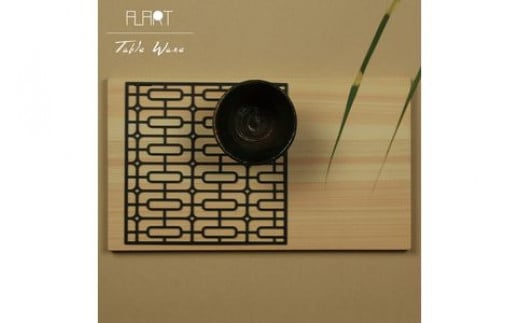
ALART〈アルアート〉 ひのき+昔日セット シルバー テーブルウェア・国産ひ…
26,000 円
寛ぎのそばに素材美の調和を。伝統美を日常に。
食を演出するオリエンタリズム。
気品ある白木との融合。
美しい木目と香り立つひのきを金属と組み合わせました。
使い込むほどに表情豊かなトレーです。
ひのきとプレートは別々にお使い頂けます。
金属で構成された素材ならではの緊張感ある美。
使い方は自由に、お使いになる空間によってバリエーションが広がります。
グラスやカップを添えて朝食やティータイムに。おもてなしの菓子受けに。
寿司プレートとしてお使いいただくなど、Remixな演出が楽しめます。
※食洗器不可
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム・木(四万十檜 蜜蝋塗装) 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 箸置き DAN 団 6本2色組(グレー3本・オリーブ3…
30,000 円
存在感を放つカトラリースタンド。
暖かな空間を作り出す薪をモチーフにしました。
ニュアンスのあるカラーが食卓を引き立てます。
ホテルオリジナルとしても人気の高いデザインです。
※食洗器不可
〈セット内容〉
団 箸置き グレー3本・オリーブ3本
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 Signage コースター6枚セット (グレー3枚・ゴール…
41,000 円
金属の新たな表現のもたらす創造性。
普遍性に裏打ちされた、全く新しい日々の生活を創造する表情を持った金属。
金属ならではの陰影が料理に映え、特別な日の演出に合います。
普段使いの食器に合わせるだけで、テーブルがモダンに。
和洋を問わないコーディネートの可能性を秘めたデザインです。
モデルルーム・レストラン等、仕様多数。
※食洗器不可
〈セット内容〉
Signage コースター グレー3枚・ゴールド3枚
※色味につきましてはお使いのモニターにより若干異なりますのでご了承ください。
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
素材:アルミニウム
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
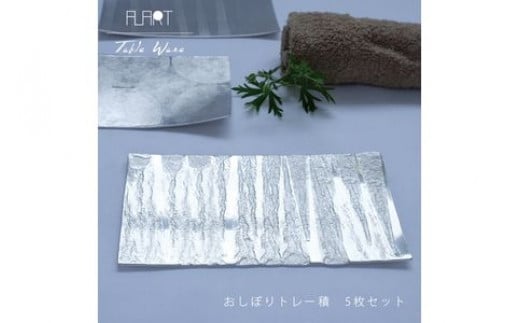
ALART〈アルアート〉 おしぼりトレー積 5枚組 テーブルウェア 表面の叩き…
32,000 円
趣きを感じる陰影感のあるトレー。
菓子器などにもお使いいただけます。
使い勝手の良さが魅力。
木や布など様々な素材との調和が美しく、どのような空間にもしっくりとなじむ
印象に残る素材感がテーブルを引き立てます。
※食洗器不可
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
素材:アルミニウム
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
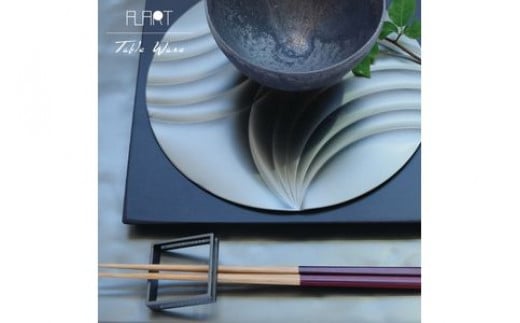
ALART〈アルアート〉 Signage 箸置き 5個2色組(グレー2個・ゴールド3…
23,000 円
金属の新たな表現のもたらす創造性。
普遍性に裏打ちされた、全く新しい日々の生活を創造する表情を持った金属。
金属ならではの陰影が料理に映え、特別な日の演出にぴったりです。
普段使いの食器に合わせるだけで、テーブルがモダンに。
和洋を問わないコーディネートの可能性を秘めたデザインです。
※食洗器不可
〈セット内容〉
Signage 箸置き グレー2本・ゴールド3本
※色味につきましてはお使いのモニターにより若干異なりますのでご了承ください。
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
素材:アルミニウム
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 MUKU柱 漆黒 SMLセット 花器 インテリア 立体感を…
64,000 円
木材の存在感と金属の主張。
無垢の木の重厚感のある温かさにソリッドなアルミを組み合わせました。
木材ならではの質感と金属の柔らかな色合い。
シンプルな中に素材美が際立ちます。
国産のブナ無垢材を使用。
天然木ならではの色合いは使い込むことで風合いを増します。
和と洋どちらにも合う、ウォールナット色は空間によく馴染みます。
〈セット内容〉
MUKU柱 S・M・L 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム/木 花器:ガラス
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 NOIR ノワール 04 曲 花器 インテリア 玄関やサイ…
24,000 円
たおやかに寄り添う。
茎の曲がった花、葉の1枚1枚までを慈しむように
一輪を際立たせるNoir。
ソリッドなラインがフレームワークとしても美しい花器です。
※天然木を使用しております。木目や色合いなど多少の差異が生じる場合がございますのでご了承下さい。
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム・木 花器:ガラス 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉 ART FLAME 積 正方形・長方形セット 花器 インテリア…
37,000 円
素材をより美しくみせるフレーム。
そこに添えられる一輪の花。花を入れる事でより存在感を増すアートフレームです。
どんな花にも合うモダンな人気柄です。
〈セット内容〉
ART FLAME 積 正方形・長方形 各1個
〈ALARTについて〉
1947年、栃木県足利市に創業した丸信金属工業。
そのファクトリーブランドとして、ALART(アルアート)はアルミの可能性を追求したオリジナルデザインのアイテムを生み出している。
色を染める、削る、人の手によって仕上げられていく製品は、金属の無機質の美が、有機の素材と相まって生まれる美しい表情を導き出す。
海外の美術館を始め、国内のホテル.旅館にも選ばれ続けている。
【産地・原材料名】
〈素材〉
本体:アルミニウム・木
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
・金属タワシ、磨き粉などは製品表面をキズつけますのでお使いにならないで下さい。
ガラス製品について
・手作り商品のため、気泡・筋などが入っている場合がありますが、強度等には問題ありません。
・急激な温度変化は割れる恐れがありますので避けて下さい。
・カッティングの状況により、小口部分の仕上げが一様でない物がございますが、内部に挿入する仕様となりますのでご了承下さい。
木製品について
・電子レンジ・食器洗い機等の使用はお避けください。木地を狂わせ、剥離及び変色の原因となります。
・プレート類につきましては、食品の直置きはお避け下さい。 ・湯水の中に長く浸さないでください。汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
・過度な乾燥は商品の特質上変化が起こりやすくなりますので、ご注意ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉ASHIKAGA AID ペン&キャッシュトレー F7Z-218
7,000 円
ペントレーとして、会計時のキャッシュトレーとして。アイデア次第で様々な用途に使える、サイズ感のあるアルミ製トレーです。中央にASHIKAGA AIDロゴが刻印されたデザイン、ブロンズゴールドの色合いが高級感 を演出してくれます。
山すそに広がる足利の街。
令和3年2月、山火事で町の暮らしが脅かされました。
いつも暮らしのそばにある山が炎の塊となって迫ってくるなど想像もしませんでした。
でも山は足利の街に彩を添え、木々の匂いや季節を運んでくれるだいじな“暮らしの相棒”です。
その相棒のピンチを機に、「“山がよろこぶ何か”をしたい」と思いました。
大きなことはできないけれど、じぶんたちができるちいさな一歩をコツコツと。
ケガをしてしまった山がいつか微笑み返してくれるその日まで。
ケガをしたあの山に、わたしたちができること。
足利市西宮林野火災で傷ついた山の復興に、市民発信のプロジェクトで製作した商品です。
商品のご購入金額より、自治体への寄付金とは別に復興に寄付をさせていただきます。
【産地・原材料名】
〈素材〉
アルミ(ブロンズゴールド)
*写真と色みが若干異なる場合があります。
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。
カラーアルマイト(染色)商品について
・手染めの為、色味につきましては多少の個体差がございます。
・リング内側には色ムラのあるございますが、商品の性質上問題ございません。
・強い摩擦を加えますと金属の素地が出てくる場合がございますがご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
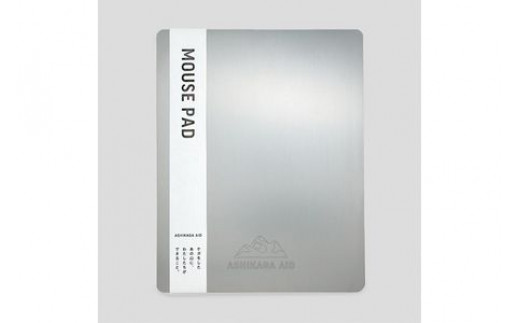
ALART〈アルアート〉ASHIKAGA AID マウスパッド シンプル F7Z-219
7,000 円
ASHIKAGA AIDロゴの刻印されたアルミ製のマウスパッド。ひんやりとした涼感が心地良く、デスクワークで疲労のたまる手首をやさしく癒してくれます。シンプルなデザインで、デスクまわりを演出してくれるアイテムです。
山すそに広がる足利の街。
令和3年2月、山火事で町の暮らしが脅かされました。
いつも暮らしのそばにある山が炎の塊となって迫ってくるなど想像もしませんでした。
でも山は足利の街に彩を添え、木々の匂いや季節を運んでくれるだいじな“暮らしの相棒”です。
その相棒のピンチを機に、「“山がよろこぶ何か”をしたい」と思いました。
大きなことはできないけれど、じぶんたちができるちいさな一歩をコツコツと。
ケガをしてしまった山がいつか微笑み返してくれるその日まで。
ケガをしたあの山に、わたしたちができること。
足利市西宮林野火災で傷ついた山の復興に、市民発信のプロジェクトで製作した商品です。
商品のご購入金額より、自治体への寄付金とは別に復興に寄付をさせていただきます。
【産地・原材料名】
素材:アルミ
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ALART〈アルアート〉ASHIKAGA AID マウスパッド モノグラム F7Z-220
7,000 円
ASHIKAGA AIDロゴの刻印されたアルミ製のマウスパッド。ひんやりとした涼感が心地良く、デスクワークで疲労のたまる手首をやさしく癒してくれます。シンプルなデザインで、デスクまわりを演出してくれるアイテムです。
山すそに広がる足利の街。
令和3年2月、山火事で町の暮らしが脅かされました。
いつも暮らしのそばにある山が炎の塊となって迫ってくるなど想像もしませんでした。
でも山は足利の街に彩を添え、木々の匂いや季節を運んでくれるだいじな“暮らしの相棒”です。
その相棒のピンチを機に、「“山がよろこぶ何か”をしたい」と思いました。
大きなことはできないけれど、じぶんたちができるちいさな一歩をコツコツと。
ケガをしてしまった山がいつか微笑み返してくれるその日まで。
ケガをしたあの山に、わたしたちができること。
足利市西宮林野火災で傷ついた山の復興に、市民発信のプロジェクトで製作した商品です。
商品のご購入金額より、自治体への寄付金とは別に復興に寄付をさせていただきます。
【産地・原材料名】
素材:アルミ
【注意事項】
商品画像について
・植物、敷物等は商品に含まれておりません。
・お使いのパソコンのモニターによっては若干色味に差が生じることがございます。
・手作業にて製作する商品につきましては形、柄の入り方等が多少異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
アルミ製品について
・表面に水気や汚れがついた場合は、きれいに拭き取って下さい。
水気がついたまま放置しておきますと白いブツブツが表面に発生することがありますが、無害です。
・製品外側の突起は処理済みですが、取扱い時にはご注意下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

月星食品おすすめセット!!【 ギフト プレゼント お中元 お歳暮 贈答品 栃…
10,000 円
人気No.1のナチュラルフルーツソースを含む、月星食品オススメ商品の詰め合わせセット!!
【ナチュラルフルーツソース】
月星食品不動の人気No.1!!
濃厚なトマト、 りんごとパイナップルのフルーティな甘みと旨味、最後に口の中に広がるスパイスの香りが食欲をそそります。このソースをかけたいがために揚げ物が食べたくなる、絶品中濃ソース!「このソースを使ったら、もう他のソースは使えない!!」という嬉しいお声もたくさんいただいております!
【スパイシーパラダイスソース】
香辛料のタイムの香りとペッパーと唐辛子が活きている、辛い物好きな人にぴったりのパンチのある中濃ソース!初めはやさしい野菜と果実の甘みが広がり、最後にガツンと辛みがきます!一度食べるとやみつきになる大人向けの中濃ソース。お子様にはちょっと辛いかもしれません…
【特製コク黒焼きそばソース】
足利市でよく食べられている「ポテト入り焼きそば」に合うソースとして開発された焼きそばソースです。ビーフエキスの旨味とコクで、これ一本で美味しい焼きそばが出来上がり!冷めてもおいしい焼きそばになるよう仕上げてあるので、お弁当などにも大活躍間違いなし!
【和風だし】
これさえあればお醤油はもう必要なし!!
かつお節は国産の本節と宗田節の厚削りを使用。ブレンドの醤油に風味豊かなだし汁を調合することによって、最高のだし醤油が出来上がりました。煮物、天つゆ、めんつゆ、煮魚、どんぶり物などのダシ、煮込みうどんなどには水でわり、冷奴・刺身などにはそのままおかけ下さい。
【塩だれ】
作るのがとっても難しい塩だれに挑戦し、何度も何度も試作を重ね作り上げた月星食品の自信作!!
焼肉のたれって余らせてしまいがち・・・という心配は不要!
焼肉はもちろん、チャーハンや野菜炒めなど、たくさんのお料理に使えます!
【使用方法】
そのままお召し上がりいただけます
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

半熟ソースせんべい【12袋セット】【 ギフト プレゼント お中元 お歳暮 贈…
13,000 円
揚げせんべいのカリカリとは違う、ぬれせんべいのしっとりとも違う、かりかりしっとりな新食感!!
味付けに使用されているのが月星食品の焼きそばソースです!!月星自慢の焼きそばソースのスパイシーな香りが食欲をそそります!!
かりかりしっとりな食感と香り高いソース味で、一度食べたらやみつきになること間違いなし!!
【産地・原材料名】
うるち米(国産)、ウスターソース(乳成分・小麦・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)、植物油脂、還元水飴、砂糖、しょうゆ、発酵調味料/トレハロース、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(ステビア、カンゾウ)
【使用方法】
そのままお召し上がりいただけます
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。
【提供元】
提供元:月星食品株式会社
製造元:有限会社まるせん米菓 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮サジー酢500ml瓶 (3倍希釈タイプ)【 ギフト プレゼント お中元 お歳暮 …
12,000 円
サジーの独特の渋みと強い酸味をオリゴ糖とはっ酵乳でフルーティで甘酸っぱい味わいに仕上げました。あなたのキレイとハリのある毎日に
【産地・原材料名】
原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サジーピューレ、サジーシードオイル、ぶどう酢、はっ酵乳(殺菌)/香料、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮タルトチェリー500ml瓶 (3倍希釈タイプ)【 ギフト プレゼント お中元 お…
10,000 円
タルトチェリーは、さくらんぼを濃縮した甘みと酸味のバランスが絶妙で、濃いさくらんぼのような味わいが特徴です。独特の果実の酸味とはっ酵乳の酸味が心地よく、就寝前のリラックスタイムに
【産地・原材料名】
原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、さくらんぼ濃縮果汁、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮サンザシ500ml瓶 (3倍希釈タイプ)【 ギフト プレゼント お中元 お歳暮 …
10,000 円
サンザシはほろ苦さと強い酸味が特徴で、オリゴ糖と発はっ酵乳でフルーティーで爽やかな味わいに仕上げました。みずみずしい肌をサポート
【産地・原材料名】
原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サンザシ濃縮エキス、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮サジー酢と濃縮タルトチェリーの2本セット【 ギフト プレゼント お中元 …
21,000 円
サジー酢/サジーの独特の渋みと強い酸味をオリゴ糖とはっ酵乳でフルーティで甘酸っぱい味わいに仕上げました。あなたのキレイとハリのある毎日に タルトチェリー/タルトチェリーは、さくらんぼを濃縮した甘みと酸味のバランスが絶妙で、濃いさくらんぼのような味わいが特徴です。独特の果実の酸味とはっ酵乳の酸味が心地よく、就寝前のリラックスタイムに
【産地・原材料名】
サジー酢/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サジーピューレ、サジーシードオイル、ぶどう酢、はっ酵乳(殺菌)/香料、(一部に乳成分を含む) タルトチェリー/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、さくらんぼ濃縮果汁、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮サジー酢と濃縮サンザシの2本セット【 ギフト プレゼント お中元 お歳暮…
21,000 円
サジー酢/サジーの独特の渋みと強い酸味をオリゴ糖とはっ酵乳でフルーティで甘酸っぱい味わいに仕上げました。あなたのキレイとハリのある毎日に サンザシ/サンザシはほろ苦さと強い酸味が特徴で、オリゴ糖と発はっ酵乳でフルーティーで爽やかな味わいに仕上げました。みずみずしい肌をサポート
【産地・原材料名】
サジー酢/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サジーピューレ、サジーシードオイル、ぶどう酢、はっ酵乳(殺菌)/香料、(一部に乳成分を含む) サンザシ/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サンザシ濃縮エキス、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

濃縮タルトチェリーとサンザシの2本セット【 ギフト プレゼント お中元 お歳…
19,000 円
タルトチェリー/タルトチェリーは、さくらんぼを濃縮した甘みと酸味のバランスが絶妙で、濃いさくらんぼのような味わいが特徴です。独特の果実の酸味とはっ酵乳の酸味が心地よく、就寝前のリラックスタイムに サンザシ/サンザシはほろ苦さと強い酸味が特徴で、オリゴ糖と発はっ酵乳でフルーティーで爽やかな味わいに仕上げました。みずみずしい肌をサポート
【産地・原材料名】
タルトチェリー/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、さくらんぼ濃縮果汁、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む) サンザシ/原材料名 :イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、サンザシ濃縮エキス、はっ酵乳(殺菌)/香料、酸味料、ビタミンC、(一部に乳成分を含む)
【使用方法】
3倍に水または炭酸で割ってお召し上がりください。
【保存方法】
直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫で保存の上、お早めにお召し上がりください。
【注意事項】
ワレモノ注意 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 3回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットA 20cm×20cm 15枚 (朝日染…
25,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
20cm×20cmの正方形のハギレが15枚入ったセットです。
※【定期便 3回】毎月一度、3回連続でお送りいたします。
シュシュなどの髪飾りや巾着を作ったり、マスクケースもおすすめです。
複数の生地を繋げれば、できることも無限に広がります!
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 20cm×20cm
枚数 : 15枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 3回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットB 10cm×10cm 20枚 (朝日…
13,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
10cm×10cmの正方形のハギレが20枚入ったセットです。
※【定期便 3回】毎月一度、3回連続でお送りいたします。
カルトナージュの布として使ったり、くるみボタンやヘアゴムなどの小物製作にぴったり。
また、パッチワークとして、他の柄との組み合わせを楽しむのもおすすめです。
お気に入りの柄は小さめのファブリックパネルにして、インテリアとして飾るのもおすすめ。
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 10cm×10cm
枚数 : 20枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 6回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットA 20cm×20cm 15枚 (朝日染…
50,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
20cm×20cmの正方形のハギレが15枚入ったセットです。
※【定期便 6回】毎月一度、6回連続でお送りいたします。
シュシュなどの髪飾りや巾着を作ったり、マスクケースもおすすめです。
複数の生地を繋げれば、できることも無限に広がります!
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 20cm×20cm
枚数 : 15枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 6回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットB 10cm×10cm 20枚 (朝日染…
26,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
10cm×10cmの正方形のハギレが20枚入ったセットです。
※【定期便 6回】毎月一度、6回連続でお送りいたします。
カルトナージュの布として使ったり、くるみボタンやヘアゴムなどの小物製作にぴったり。
また、パッチワークとして、他の柄との組み合わせを楽しむのもおすすめです。
お気に入りの柄は小さめのファブリックパネルにして、インテリアとして飾るのもおすすめ。
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 10cm×10cm
枚数 : 20枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットA F7Z-340
10,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~2月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットB F7Z-341
10,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~3月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットC F7Z-342
10,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~4月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットD F7Z-343
20,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~5月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットE F7Z-344
20,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~6月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットF F7Z-345
20,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~7月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットG F7Z-346
28,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~8月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットH F7Z-347
28,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~9月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

朝日染色オリジナルマスク 「High Performance MASK」 セットI F7Z-348
28,000 円
始まりは「みんなに光を届けたい」という小さな願いからでした。
新型コロナウイルスの影響でマスク不足が深刻になる中、弊社のハギレ布を再利用して作ったマスクを、都内の友人に送ったことがきっかけです。
そのマスクが「日本女性財団」の目に留まり、困っている人々のために一緒に何かできることはないかと話が進んでいきました。
「日本女性財団」は、新型コロナウイルスが蔓延する状況下、困っている女性や医療従事者を支援したいと、女性の心身の健康や社会的な活躍を後押しすべく、女性医師や起業家、有識者たちが立ち上げた財団法人です。
そこに国内外の有名アパレルブランド向けにプリント生地を提供する弊社の技術力を集結したマスクで・・・。という取り組みをスタートし、の益金は全て「日本女性財団」に寄付をさせて頂くプロジェクトを発足しました。
「世界一美しいプリント」といわれるパリのクチュールブランドのプリントを手掛ける弊社の職人技術をマスクに取り入れ、素材やパターン、そしてMADE IN JAPANにこだわりました。素材選びは、汗や蒸れで生じる化粧汚れを軽減し、肌への負担が少なくなるようにポリエステルとポリウレタン組成の吸水速乾生地を使用。フェイスラインをきれいに見せ、美しいフォルムをキープするためにパターンと縫製にもこだわっています。
「まるで着替えをするように、マスクでおしゃれを楽しんで欲しい・・・。」
そんな願いから、弊社だからこそ可能なデザインでのプリントを施し、
無地カラーマスク(定番カラー):ホワイト・グレージュ・ボルドー・ネイビー
プリントマスク:全33柄 を取り揃えました。
・スポーツブランド向けに開発した、吸水速乾の生地を使用。通気性が良くシワになりにくい素材で、洗濯のお手入れが簡単です。
・春夏用(3月~8月出荷分):「涼感加工」を施し、付けた時にひんやりと涼しさを感じられます。
・秋冬用(9月~10月出荷分):「抗菌加工」を施し、菌の繁殖を抑えます。抗菌剤はグレープフルーツ種子より抽出した天然成分由来の抗菌剤です。人体へのたかい安全性を求められる医療・介護用品にも使用可能な安全性の高い抗菌剤です。
・カッティングにこだわった美しく立体的な形状で、フェイスラインをきれいに見せ、中心部の縫製には肌当たりの優しい糸を使用しています。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 12回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットA 20cm×20cm 15枚 (朝日染…
100,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
20cm×20cmの正方形のハギレが15枚入ったセットです。
※【定期便 12回】毎月一度、12回連続でお送りいたします。
シュシュなどの髪飾りや巾着を作ったり、マスクケースもおすすめです。
複数の生地を繋げれば、できることも無限に広がります!
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 20cm×20cm
枚数 : 15枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【定期便 12回】 ハギレの 「HAGIREs」 セットB 10cm×10cm 20枚 (朝日…
52,000 円
<朝日染色について>
朝日染色株式会社は、栃木県足利市にある、創業1918年のハンドプリント工場です。
職人の技術と自然の力によって生み出される、オリジナルデザインのプリント生地は、1色1色を乾かしながら丁寧にプリントする事で生まれる発色の良い色・深みのある色・美しい絵際が特長です。
創業以来、ヴィンテージデザインのほか、10万柄を越える資料のストックを保有。
国内外のアパレルブランドへのプリント生地、製品の新しいクリエーションから生産まで提供をしております。
伝統技術を継承進化させながら未来に伝えていくため、素材・プリント・仕上げまで、全てにこだわったものづくりをしています。
<商品について>
10cm×10cmの正方形のハギレが20枚入ったセットです。
※【定期便 12回】毎月一度、12回連続でお送りいたします。
カルトナージュの布として使ったり、くるみボタンやヘアゴムなどの小物製作にぴったり。
また、パッチワークとして、他の柄との組み合わせを楽しむのもおすすめです。
お気に入りの柄は小さめのファブリックパネルにして、インテリアとして飾るのもおすすめ。
- - - - - - - - - -
『今月は何作ろう?』のワクワクをお届けします。
HAGIREsで販売しているハギレは当社が生産しているオリジナル柄のプリント生地です。
1918年の創業来、国内外の有名ブランド向けに提案しつづけた柄から出た秘蔵のハギレは
一般の生地販売チェーン店では販売していない素材ばかりです。
柄もイロイロ、素材もイロイロ。
高品質なハンドプリントと、インクジェットで生産された色とりどりの柄を
毎月ランダムにお届けいたします。
自由な発想と想像力で、あなたならではの作品作りをお楽しみください。
<商品詳細>
サイズ: 10cm×10cm
枚数 : 20枚
※柄は毎回ランダムです。
※大きさについては、多少の誤差はございますことご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
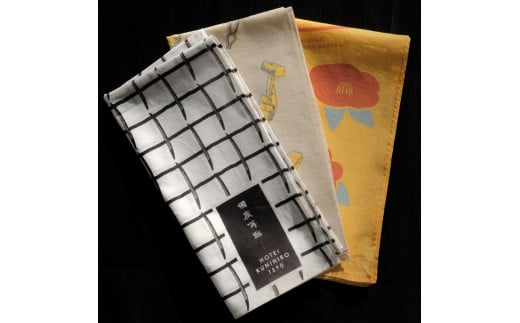
刀剣デザインハンカチ 3枚セット「椿」「陣列」「鍛刀」 F7Z-355
10,000 円
刀剣デザインハンカチ 3枚セット 「椿」 「陣列」 「鍛刀」
TSUBAKI - 椿 -
鮮やかな朱色の椿と足利蔵の4振りの刀剣のシルエットが散りばめられた、可愛らしいデザインのハンカチです。 場がパッと華やぐような明るい配色で、持つ人を元気付けてくれるはずです。
TANTOU - 鍛刀 -
刀を打つ「刀鍛冶」の手のイラストが全面にあしらわれたポップなデザインのハンカチです。 刀を挟む火箸、刀を叩く小鎚を持つ手がそれぞれ描かれています。美しく強靭な日本刀の誕生には、この手が欠かせません。
JINRETSU - 陣列 -
一見シンプルな格子(チェック)柄に見えて、よく見ると脇指 号 布袋国広のシルエットが敷き詰められているユニークなデザインのハンカチです。 おしゃれなモノトーン調で普段使いしやすいので、持ち歩いてちょっとした話題作りにも。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利型染てぬぐい ASHIKAGA 濃藍 F7Z-153
5,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
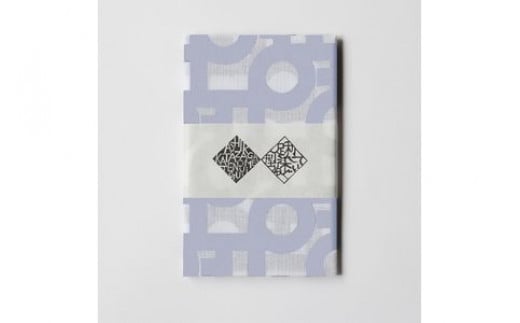
足利型染てぬぐい ASHIKAGA 白鼠 F7Z-154
5,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利型染てぬぐい ASHIKAGA 灰梅 F7Z-155
5,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利型染てぬぐい WATARASE 浅葱 F7Z-156
5,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利型染てぬぐい WATARASE 青藤 F7Z-157
5,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利型染てぬぐい 和の色6色セット F7Z-158
30,000 円
足利の歴史・風景をデザインした「足利型染てぬぐい」は、大正15年創業以来、約100年続く栃木県足利市の型染工場にて、職人が1枚1枚手作業で染めています。
〈ASHIKAGA〉は足利の「足」が並んだデザイン。織機の滑車と反物をイメージし、一時代を築いた足利の繊維産業へのリスペクトを込めています。〈WATARASE〉は足利のシンボル「渡良瀬橋」と、そこから見渡す夕暮れ時の足利の山々をイメージ。色はそれぞれ柔らかい日本の伝統色の3色展開です。ハンカチやタオルの代わりはもちろん、キッチンやリビングなど、普段の生活の中でぜひお使いください♪
※和の色6色セットは2柄×3色が一枚ずつ入ったスペシャルセットです。
【産地・原材料名】
生地/綿100%
日本製
【注意事項】
・お使い始めに汗や摩擦で色が移ることがあります。
・お洗濯の際はたっぷりの水で手洗いしてください。浸けおきはお避け下さい。
・全て手作業で製作されておりますので多少の染めムラなどございますがご了承くださいませ。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【会員限定】東松苑ゴルフ倶楽部 施設利用券 ¥30,000分【 栃木県 足利市 …
100,000 円
東松苑ゴルフ倶楽部の施設利用券
本返礼品は東松苑ゴルフ倶楽部会員様のみお申込み・利用が可能です。
ゴルフプレー代、施設内の食事代、年会費代にご利用できる施設利用券になります。
寄付金額100,000円で30,000円の利用券を進呈
【産地・原材料名】
東松苑ゴルフ倶楽部で使えるゴルフ場利用券
【注意事項】
※お申し込みは東松苑ゴルフ倶楽部の会員様限定となります。
※本券は会員様の年会費、ゴルフプレー代、施設内の食事代にご利用いただけます。
ご利用の際はプレー当日のチェックイン時にフロントにご提示ください。
施設ご利用合計額より差し引かせていただきます。つり銭券は換金できません。
※有効期限は発行より1年間となります。有効期限を過ぎたものはご利用できません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【会員限定】東松苑ゴルフ倶楽部 施設利用券 ¥60,000分【 栃木県 足利市 …
200,000 円
東松苑ゴルフ倶楽部の施設利用券
本返礼品は東松苑ゴルフ倶楽部会員様のみお申込み・利用が可能です。
ゴルフプレー代、施設内の食事代、年会費代にご利用できる施設利用券になります。
寄付金額200,000円で60,000円の利用券を進呈
【産地・原材料名】
東松苑ゴルフ倶楽部で使えるゴルフ場利用券
【注意事項】
※お申し込みは東松苑ゴルフ倶楽部の会員様限定となります。
※本券は会員様の年会費、ゴルフプレー代、施設内の食事代にご利用いただけます。
ご利用の際はプレー当日のチェックイン時にフロントにご提示ください。
施設ご利用合計額より差し引かせていただきます。つり銭はでませんので、利用券の金額以上のご精算額にご利用下さい。
※他の優待券・割引券との併用はできません。
※本券の再発行はいたしません。本券は換金できません。
※有効期限は発行より2年間となります。有効期限を過ぎたものはご利用できません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【会員限定】東松苑ゴルフ倶楽部 施設利用券 ¥90,000分【 栃木県 足利市 …
300,000 円
東松苑ゴルフ倶楽部の施設利用券
本返礼品は東松苑ゴルフ倶楽部会員様のみお申込み・利用が可能です。
ゴルフプレー代、施設内の食事代、年会費代にご利用できる施設利用券になります。
寄付金額300,000円で90,000円の利用券を進呈
【産地・原材料名】
東松苑ゴルフ倶楽部で使えるゴルフ場利用券
【注意事項】
※お申し込みは東松苑ゴルフ倶楽部の会員様限定となります。
※本券は会員様の年会費、ゴルフプレー代、施設内の食事代にご利用いただけます。
ご利用の際はプレー当日のチェックイン時にフロントにご提示ください。
施設ご利用合計額より差し引かせていただきます。つり銭はでませんので、利用券の金額以上のご精算額にご利用下さい。
※他の優待券・割引券との併用はできません。
※本券の再発行はいたしません。本券は換金できません。
※有効期限は発行より3年間となります。有効期限を過ぎたものはご利用できません。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

あしかが美人ドレッシング200ml 4種類詰め合わせ(添加物不使用) F7Z-12…
8,000 円
渡良瀬川の恵みを受けた芳醇な土壌で育ったブランド野菜の「あしかが美人」を使用したドレッシングです。
添加物を使わず素材そのものの味を引き出したので、野菜自体のフレッシュな味を楽しめます。
【あしかが美人 とまとドレッシング 200ml×1本】
足利市の採れたてのフレッシュトマトを35%も配合しました。
つけめんやパスタにおすすめです。
【あしかが美人 にんじんドレッシング 200ml×1本】
いろどりも鮮やかに、にんじんの旨みと甘みを凝縮したドレッシングです。
人参ラペやサラダうどんにもおすすめです。
【あしかが美人 アスパラガスドレッシング 200ml×1本】
採れたてアスパラガスとマヨネーズの風味がマッチしたドレッシングです。
温野菜、きのことブロッコリー炒めなどにもおすすめです。
【あしかが美人 たまねぎドレッシング 200ml×1本】
たまねぎの柔らかい甘みが特徴のドレッシングです。
リゾットやお肉の下味にもおすすめです。
●製造地:栃木県足利市
【産地・原材料名】
●製造地:栃木県足利市
・とまとドレッシング:とまと(足利市産)、醸造酢(りんご酢、醸造酢)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食用植物油脂、たまねぎ、食塩、ワイン、でん粉、鰹節抽出液、にんにく、香辛料、寒天、(一部にりんごを含む)
・にんじんドレッシング:にんじん(足利市産)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、水飴)、醸造酢(りんご酢、醸造酢)、たまねぎ、食用植物油脂、食塩、りんご、でん粉、レモン果汁、寒天、香辛料、(一部にりんごを含む)
・アスパラガスドレッシング:アスパラガス(足利市産)、食用植物油脂、醸造酢(りんご酢、醸造酢)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、しょうゆ、たん白加水分解物、たまねぎ、食塩、卵黄、でん粉、チキンエキス、鰹節抽出液、椎茸エキス、香辛料、(一部に卵・小麦・大豆・りんご・鶏肉を含む)
・たまねぎドレッシング:たまねぎ(足利市産)、しょうゆ、醸造酢、食用植物油脂、砂糖、にんじん、りんご、でん粉、鰹節抽出液、チキンエキス、食塩、酵母エキス、オイスターエキス、寒天、(一部に小麦・大豆・りんご・鶏肉を含む)
【保存方法】
直射日光を避けて常温保存。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

日東産業おすすめセット 5種類詰め合わせ【ドレッシング・ソース・たれ】 F…
13,000 円
昭和21年より約75年にわたりソース、ドレッシング、たれなどを製造しています。
お客様にご購入いただいている中で特にリピーターが多い「ドレッシング」、「ソース」、「たれ」をまとめたセットです。
【北陽千鳥 中濃ソース 300ml×1本】
北海道富良野産玉ねぎ、にんじんと国内産りんごをベースに、16種類のスパイスをブレンドして仕上げたソースです。
揚げ物やキャベツ、焼きそば、スライストマト、チキンステーキなどにおすすめです。
また、北陽千鳥ソースのロゴマークである千鳥の文様とロゴタイプのデザインは創業者の旧友であり、のちに高名な詩人となる足利市出身の詩人 相田みつを氏が、若かりし頃に制作したものです。
【あしかが美人 にんじんドレッシング 200ml×1本】
いろどりも鮮やかに、にんじんの旨みと甘みを凝縮したドレッシングです。
人参ラペやサラダうどんにもおすすめです。
【鰹節ドレッシング 200ml×1本】
鰹の有名な産地である鹿児島県枕崎市の鰹節を使用し、鰹節本来の味を生かしたドレッシングです。
削り節がそのまま入っており、また、化学調味料を一切使用していない為、柔らかい甘みと鰹節の旨みが特徴です。
冷しゃぶやカルパッチョなどにもおすすめです。
【ピリ辛にんにく味噌だれ 360g×1本】
にんにくが好きな方の為に開発したピリ辛で甘みとコクのある万能味噌だれです。
焼肉や野菜炒めなどにもおすすめです。
【激辛のたれ 240g×1本】
超辛な味付けと香味野菜などのコク味が意外な程料理の味を引き立てます。
焼肉・餃子のつけだれ、チャーハンや納豆ご飯のアクセント、イカ焼き、豚しゃぶ、冷麺、ラーメン、鍋物など
様々な料理との相性抜群です。
■お礼品の内容について
・ソース[300ml×1本] 賞味期限:発送から400日~600日
・ドレッシング[各200ml×2本] 賞味期限:発送から100日~150日
・たれ[360g、240g×各1本] 賞味期限:発送から150日~300日
●製造地:栃木県足利市
【保存方法】
直射日光を避けて常温保存。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

【辛・オブ・ザ・イヤー2024入選】激辛!! 激辛のたれ 240g 5本 激辛 焼肉…
13,000 円
昭和21年より約75年にわたりソース、ドレッシング、たれなどを製造しています。
さまざまな料理に使える「激辛のたれ」を5本セットにまとめました。
辛さが足りない時や料理のアクセントなど、幅広い用途でご使用ください。
【激辛のたれ 240g×1本】
超辛な味付けと香味野菜などのコク味が意外な程料理の味を引き立てます。
焼肉・餃子のつけだれ、チャーハンや納豆ご飯のアクセント、イカ焼き、豚しゃぶ、冷麺、ラーメン、鍋物など
様々な料理との相性抜群です。
●製造地:栃木県足利市
【産地・原材料名】
・激辛のたれ 240g:しょうゆ(国内製造)、砂糖、野菜類(トマト、にんにく、生姜、その他)、果糖ぶどう糖液糖、香辛料、醸造酢、食塩、味噌、ごま油、ごま、チキンエキスパウダー、でん粉/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、着色料(パプリカ色素、カラメル)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ごま・鶏肉を含む)
◆アレルゲン
・激辛のたれ…乳成分・小麦・大豆・ごま・鶏肉
【保存方法】
直射日光を避けて常温保存。
【注意事項】
※到着後は直射日光を避けて常温保存して下さい。
※開封後は冷蔵庫で保存し、お早めにご使用下さい。
※お盆休暇、年末年始休暇等長期休暇を頂戴することがございます、その際は、翌営業日より出荷対応させていただきます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ふわっと暖暖 「瞬暖」 F7Z-440
10,000 円
ふわっと暖暖シリーズ「瞬暖」は、【1.かけた瞬間に暖かい】ことと、【2.非常に軽い】という特徴があります。
1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度をかけた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。
2.わずか70g、つまり「L卵1個分」しかなく非常に軽いです。かけているかを忘れてしまう一体感を実感してください。また、折りたたむとペットボトルサイズになり持ち運びに便利です。内外関係なくご使用ください。
デスクワークに【冷え性対策】、緊急避難用としての【防災対策】、キャンプ等のお出かけ【アウトドア】、羽毛布団の代わりに【防寒対策】、夏にも【熱中症・紫外線対策】に!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
■本製品は、軽さと断熱性を追求したものです。内側は繊維の現しとなっていますので、ほつれ等の原因となる場所での御使用はお控え下さい。
■コーヒーやお茶等をこぼした場合は、カビ発生の原因にもなりますので洗濯して良く乾燥させて下さい。
■洗濯する場合は、ネットに入れてください。
■雨水は透過しますので、雨の日は御使用にならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ふわっと暖暖 「トラベルマット」 F7Z-441
17,000 円
ふわっと暖暖シリーズ「トラベルマット」は、【1.かけた瞬間に暖かい】ことと、【2.非常に軽い】という特徴があります。
1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度をかけた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。
2.わずか140g、つまり「L卵2個分」しかなく非常に軽いです。かけているかを忘れてしまう一体感を実感してください。また、折りたたむとかなり小さくなりなり持ち運びに便利です。内外関係なくご使用ください。
デスクワークに【冷え性対策】、緊急避難用としての【防災対策】、キャンプ等のお出かけ【アウトドア】、羽毛布団の代わりに【防寒対策】、夏にも【熱中症・紫外線対策】に!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
■本製品は、軽さと断熱性を追求したものです。内側は繊維の現しとなっていますので、ほつれ等の原因となる場所での御使用はお控え下さい。
■コーヒーやお茶等をこぼした場合は、カビ発生の原因にもなりますので洗濯して良く乾燥させて下さい。
■洗濯する場合は、押し洗いを原則とし、洗濯機の使用はご遠慮下さい。
■雨水は透過しますので、雨の日は御使用にならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
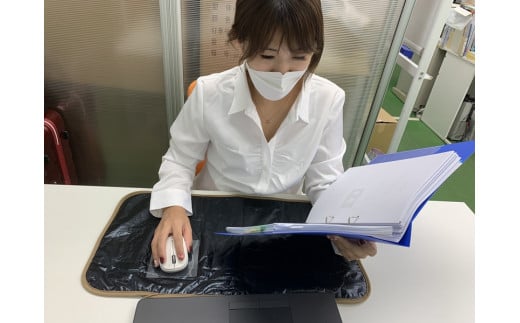
シャネボウ ふわっと暖暖 「パソコン暖マット」 F7Z-442
9,000 円
ふわっと暖暖シリーズ「パソコン暖マット」は、【1.触れた瞬間に暖かい】ことと、【2.どこにでも使える】という特徴があります。
1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度を触れた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。
2.マウスにも安心なPP板付きでデスクや出張中のパソコン操作に、また、座布団のように使っても便利です。デスクワークに【冷え性対策】、緊急避難用としての【防災対策】、ちょっとしたお出かけ【アウトドア】、枕カバーの代わりに【防寒対策】、夏にも【熱中症・紫外線対策】に!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
■本製品は、軽さと断熱性を追求したものです。内側は繊維の現しとなっていますので、ほつれ等の原因となる場所での御使用はお控え下さい。
■コーヒーやお茶等をこぼした場合は、カビ発生の原因にもなりますので洗濯して良く乾燥させて下さい。
■洗濯する場合は、押し洗いを原則とし、洗濯機の使用はご遠慮下さい。
■雨水は透過しますので、雨の日は御使用にならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ふわっと暖暖 「宇都宮ブレックスマット」 F7Z-443
20,000 円
ふわっと暖暖シリーズ「宇都宮ブレックスマット」は、【1.かけた瞬間に暖かい】ことと、【2.非常に軽い】という特徴があります。
1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度をかけた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。
2.わずか140g、つまり「L卵2個分」しかなく非常に軽いです。かけているかを忘れてしまう一体感を実感してください。また、折りたたむとかなり小さくなりなり持ち運びに便利です。内外関係なくご使用ください。
デスクワークに【冷え性対策】、緊急避難用としての【防災対策】、キャンプ等のお出かけ【アウトドア】、羽毛布団の代わりに【防寒対策】、夏にも【熱中症・紫外線対策】に!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
■本製品は、軽さと断熱性を追求したものです。内側は繊維の現しとなっていますので、ほつれ等の原因となる場所での御使用はお控え下さい。
■コーヒーやお茶等をこぼした場合は、カビ発生の原因にもなりますので洗濯して良く乾燥させて下さい。
■洗濯する場合は、押し洗いを原則とし、洗濯機の使用はご遠慮下さい。
■雨水は透過しますので、雨の日は御使用にならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ふわっと暖暖 「大人のベットカバー」 F7Z-444
30,000 円
<お客様のお声>
「トイレの回数が減りました!!!」
「末端冷え性だけど、靴下無しで寝れるようになった。」
「低温火傷するから電気毛布じゃない、こんな商品待ってました!」
・・・等たくさんのお声をいただいております!
ふわっと暖暖シリーズ「大人のベットカバー」は、【1.かけた瞬間に暖かい】ことと、【2.非常に軽い】という特徴があります。
1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度をかけた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。
2.わずか290g、つまり「羽毛布団の約21%」の重さしかなく非常に軽いです。かけているかを忘れてしまう一体感を実感してください。
羽毛布団の代わりに【防寒対策】、緊急避難用としての【防災対策】、キャンプ等のお出かけ【アウトドア】にも!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
●本製品は、軽さと暖かさを追求していますので、内側は繊維の現しとなっております。繊維のほつれに注意してご使用下さい。
●洗濯する場合は、ネットに入れてください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ふわっと暖暖 「瞬暖ブレックス」 F7Z-445
14,000 円
ふわっと暖暖シリーズ「瞬暖ブレックス」は、【1.かけた瞬間に暖かい】ことと、【2.非常に軽い】という特徴があります。 1.「自熱暖房」といい、自分の熱を反射する遮熱材を使用している為、体温に近い温度をかけた瞬間から感じられます。電気を使用した製品では熱くなりすぎてしまい低温火傷の可能性がありますが本商品はお子様からご年配の方まで安心してご利用いただけます。 2.わずか70g、つまり「L卵1個分」しかなく非常に軽いです。かけているかを忘れてしまう一体感を実感してください。また、折りたたむとかなり小さくなりなり持ち運びに便利です。内外関係なくご使用ください。 デスクワークに【冷え性対策】、緊急避難用としての【防災対策】、キャンプ等のお出かけ【アウトドア】、羽毛布団の代わりに【防寒対策】、夏にも【熱中症・紫外線対策】に!
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着、ポリエステル綿
【使用方法】
電気を使用しない自熱暖房なので、いつでも、どこでも御使用になれます。
【注意事項】
■本製品は、軽さと断熱性を追求したものです。内側は繊維の現しとなっていますので、ほつれ等の原因となる場所での御使用はお控え下さい。
■コーヒーやお茶等をこぼした場合は、カビ発生の原因にもなりますので洗濯して良く乾燥させて下さい。
■洗濯する場合は、ネットに入れてください。
■雨水は透過しますので、雨の日は御使用にならないで下さい。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ハットクーリング3(大人用) F7Z-446
6,000 円
シャネボウ「ハットクーリング3」は日本遮熱の遮熱材「トップヒートバリアー」を使ったシートを帽子に入れるだけで、太陽からの輻射熱を98%、紫外線も98%カットする熱中症対策商品です。一般の帽子と比較したヒーターによる実験ではハットクーリングが入っている帽子は【33.3℃】も低くなることが実証されています。
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミニウム、ポリエチレン
【使用方法】
ハットクーリング3の金属面を帽子側に入れてください。
【注意事項】
■ハットクーリング3には金属が使用されていますので、手を切らない様に気を付けてお取扱いください。
■寸法が合わない場合は、ハサミやカッターで切ってご使用ください。
■汗や埃で汚れた時はスポンジ等を使用し中性洗剤で水洗いしてください。感想は天日干しで行い、電子レンジ等には入れないでください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ハットクーリング2(子供用) F7Z-447
5,000 円
シャネボウ「ハットクーリング2」は日本遮熱の遮熱材「トップヒートバリアー」を使ったシートを帽子に入れるだけで、太陽からの輻射熱を98%、紫外線も98%カットする熱中症対策商品です。お子様の登下校時が一番暑い時間に、頭部の熱をカットし、熱中症予防をしてお子様の健康を守ります。
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミニウム、ポリエチレン
【使用方法】
ハットクーリング2の金属面を帽子側に入れてください。
【注意事項】
■ハットクーリング2には金属が使用されていますので、手を切らない様に気を付けてお取扱いください。
■寸法が合わない場合は、ハサミやカッターで切ってご使用ください。
■汗や埃で汚れた時はスポンジ等を使用し中性洗剤で水洗いしてください。感想は天日干しで行い、電子レンジ等には入れないでください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ キャップクーリング F7Z-448
6,000 円
シャネボウ「キャップクーリング」は日本遮熱の遮熱材「トップヒートバリアー」を使ったシートを帽子に入れるだけで、太陽からの輻射熱を98%、紫外線も98%カットする熱中症対策商品です。帽子を被るスポーツ全般に使用でき、熱中症予防も出来る商品となっています。
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミニウム、ポリエチレン
【使用方法】
キャップクーリングの金属面を帽子側に入れてください。
【注意事項】
■キャップクーリングには金属が使用されていますので、手を切らない様に気を付けてお取扱いください。
■寸法が合わない場合は、ハサミやカッターで切ってご使用ください。
■汗や埃で汚れた時はスポンジ等を使用し中性洗剤で水洗いしてください。感想は天日干しで行い、電子レンジ等には入れないでください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ メットクーリング F7Z-449
5,000 円
シャネボウ「メットクーリング」は日本遮熱の遮熱材「トップヒートバリアー」を使ったシートをヘルメットに入れるだけで、太陽からの輻射熱を98%、紫外線も98%カットする熱中症対策商品です。テレビで紹介されてから爆発的な人気を誇っている商品です。また、首元をカバーする「ネッククーリング」と組み合わせることで熱中症予防の効果が上がります。
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミニウム、ポリエチレン
【使用方法】
ヘルメットのバンド部分の外側にウレタン側を貼り付け、そのまま装着します。
【注意事項】
■メットクーリングには金属が使用されていますので、手を切らない様に気を付けてお取扱いください。
■寸法が合わない場合は、ハサミやカッターで切ってご使用ください。
■汗や埃で汚れた時はスポンジ等を使用し中性洗剤で水洗いしてください。感想は天日干しで行い、電子レンジ等には入れないでください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ウィンディキャップ ホワイト F7Z-451
19,000 円
シャネボウ「ウィンディキャップホワイト」は帽子全体に遮熱材を使用しており、頭部の暑さに最も影響を及ぼす太陽からの輻射熱を80%以上カットする熱中症対策商品です。前面の通気のダクトにより頭部から発生する湿気や熱を排出します。また、輻射熱をカットすることでムレの要因である東部の発熱を抑えますので髪の毛はサラサラ感があります。
【産地・原材料名】
日本・ダクト(空気孔)ポリエステル、生地・ポリエステル
【使用方法】
後ろのアジャスターで調節して被ってください。
【注意事項】
■汗や埃で汚れた時は洗濯ネットを使用してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ ウィンディキャップ ブラック F7Z-452
19,000 円
シャネボウ「ウィンディキャップブラック」は帽子全体に遮熱材を使用しており、頭部の暑さに最も影響を及ぼす太陽からの輻射熱を80%以上カットする熱中症対策商品です。前面の通気のダクトにより頭部から発生する湿気や熱を排出します。また、輻射熱をカットすることでムレの要因である東部の発熱を抑えますので髪の毛はサラサラ感があります。
【産地・原材料名】
日本・ダクト(空気孔)ポリエステル、生地・ポリエステル
【使用方法】
後ろのアジャスターで調節して被ってください。
【注意事項】
■汗や埃で汚れた時は洗濯ネットを使用してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

シャネボウ メットキャップ F7Z-455
12,000 円
シャネボウ「メットキャップ」はヘルメットの外側からカバーすることにより、ヘルメット内に熱を入れず、頭の中が熱くならない熱中症対策グッズです。内側に滑り止めのゴムがついており、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。汚れた時は洗濯も出来て衛生的です。ヒーターによる実験ではカバーが有ると無しでヘルメット内側の温度が14.2度も差が出ました。
【産地・原材料名】
日本(足利製造)・アルミ蒸着布、生地・ポリエステル
【使用方法】
ヘルメットの外側に被せてお使いください
【注意事項】
■ヘルメット帽体の外側で遮熱する事により、太陽からの輻射熱の大半を阻止しますので、熱中症対策には非常に効果的です。
■帽体内側の温度と頭部の温度差が少ないのでムレを最小限にします。
■ワンタッチで着脱可能、取扱いが便利です。
■折りたたみ自由、コンパクトに収納出来ます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
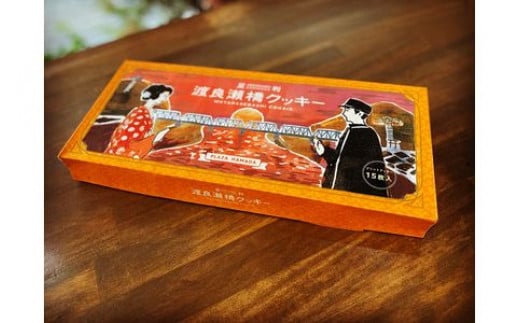
足利土産 渡良瀬橋クッキー 15枚入 洋菓子 焼菓子 菓子 プリント クッキー …
5,500 円
足利市の観光のシンボル「渡良瀬橋」。大正ロマン風のデザインで女性の着物にも足利銘仙柄を盛り込んでいます。
プリントクッキーには橋の橋梁の数と同じ6種類のイラストが描かれています。
さらに渡良瀬橋の歴史とデータが記載されている渡良瀬橋カードも1枚封入されています。
【産地・原材料名】
足利市観光商品
【使用方法】
○開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。
○クッキーは割れやすいので衝撃を与えないでください。
○製造工程においてプリント面以外にも着色する場合がございますが、安心してお召し上がりください。
【保存方法】
常温保存
【注意事項】
名称:クッキー●原材料名:小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、加糖凍結卵黄(卵黄、砂糖)、凍結卵白(卵白、食塩)、アーモンドパウダー、食塩/膨張剤、香料、
環状オリゴ糖、着色料(赤色102号、青色1号、黄色4号、赤色106号)、(一部に小麦-卵-乳成分大豆-アーモンドを含む) ●内容量:15枚●賞味期限枠外下部に記載●保存方法直射日光高温多湿を避けて、保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

足利土産 足利めぐ里プリントクッキー 15枚入 洋菓子 焼菓子 菓子 プリント …
5,500 円
国宝「鑁阿寺」、日本遺産「足利学校」、「織姫神社」、100年を超える「花火大会」、室的時代の刀工「堀川国広」の名刀「布袋国広」をモチーフにしたオリジナルプリントクッキー。
【産地・原材料名】
足利市観光商品
【使用方法】
○開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。
○クッキーは割れやすいので衝撃を与えないでください。
○製造工程においてプリント面以外にも着色する場合がございますが、安心してお召し上がりください。
【保存方法】
常温保存
【注意事項】
名称:クッキー●原材料名:小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、加糖凍結卵黄(卵黄、砂糖)、凍結卵白(卵白、食塩)、アーモンドパウダー、食塩/膨張剤、香料、
環状オリゴ糖、着色料(赤色102号、青色1号、黄色4号、赤色106号)、(一部に小麦-卵-乳成分大豆-アーモンドを含む) ●内容量:15枚●賞味期限枠外下部に記載●保存方法直射日光高温多湿を避けて、保存してください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ひもかわ うどん こだわり特製肉汁つゆ付 200g F7Z-481
4,000 円
コシの強さと絶品の喉越し 食べなきゃ損の もっちもち半生うどん 幅広のめんがツルッとして美味しい熟練職人の経験と技、風土に恵まれた有数の麦類の産地 足利の小麦100%からつくられる風味豊かな名物うどんです。 ざる、かけはもちろん、カレー、煮込み、お鍋のシメなど、温・冷どちらでも美味しくお召し上がりいただけます。 今日のレシピに迷ったときも、これさえあれば重宝します。
【産地・原材料名】
【めん】 小麦粉、水あめ、食塩/酒精、打ち粉(加工でん粉) 【つゆ】しょうゆ(本醸造)、水あめ、砂糖、砂糖混合異性化液糖、植物油脂、動物油脂、かつおぶし、ポークエキス、食塩、こんぶ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む)
【保存方法】
直射日光、高温多湿な場所を避けて常温にて保存して下さい。
【注意事項】
手作業で製造しておりますので、商品によっては、内容量に多少の誤差が生じる場合がございます。 誤差が生じた場合、麺の長さが短いもので調整されている場合もございます。商品の不足や、破損等ではございませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ひもかわ うどん こだわり特製肉汁つゆ付 200g×2袋セット F7Z-482
6,000 円
コシの強さと絶品の喉越し 食べなきゃ損の もっちもち半生うどん 幅広のめんがツルッとして美味しい熟練職人の経験と技、風土に恵まれた有数の麦類の産地 足利の小麦100%からつくられる風味豊かな名物うどんです。 ざる、かけはもちろん、カレー、煮込み、お鍋のシメなど、温・冷どちらでも美味しくお召し上がりいただけます。 今日のレシピに迷ったときも、これさえあれば重宝します。
【産地・原材料名】
【めん】 小麦粉、水あめ、食塩/酒精、打ち粉(加工でん粉) 【つゆ】しょうゆ(本醸造)、水あめ、砂糖、砂糖混合異性化液糖、植物油脂、動物油脂、かつおぶし、ポークエキス、食塩、こんぶ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む)
【保存方法】
直射日光、高温多湿な場所を避けて常温にて保存して下さい。
【注意事項】
手作業で製造しておりますので、商品によっては、内容量に多少の誤差が生じる場合がございます。 誤差が生じた場合、麺の長さが短いもので調整されている場合もございます。商品の不足や、破損等ではございませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ひもかわ うどん こだわり特製肉汁つゆ付 200g×6袋 ギフトセット F7Z-483
13,000 円
コシの強さと絶品の喉越し 食べなきゃ損の もっちもち半生うどん 幅広のめんがツルッとして美味しい熟練職人の経験と技、風土に恵まれた有数の麦類の産地 足利の小麦100%からつくられる風味豊かな名物うどんです。
ざる、かけはもちろん、カレー、煮込み、お鍋のシメなど、温・冷どちらでも美味しくお召し上がりいただけます。
もっちもち食感の美味しいひもかわうどん 12人前 ギフトセットです。
【産地・原材料名】
【めん】小麦粉、水あめ、食塩/酒精、打ち粉(加工でん粉)
【つゆ】しょうゆ(本醸造)、水あめ、砂糖、砂糖混合異性化液糖、植物油脂、動物油脂、かつおぶし、ポークエキス、食塩、こんぶ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む)
【保存方法】
直射日光、高温多湿な場所を避けて常温にて保存して下さい。
【注意事項】
手作業で製造しておりますので、商品によっては、内容量に多少の誤差が生じる場合がございます。
誤差が生じた場合、麺の長さが短いもので調整されている場合もございます。商品の不足や、破損等ではございませんので、予めご了承ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
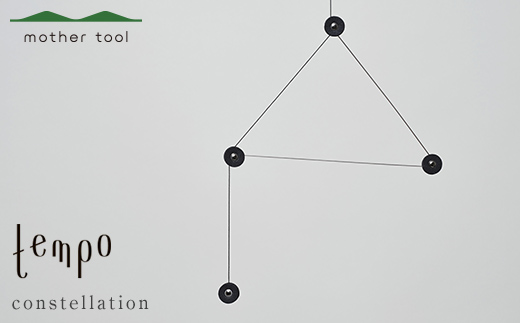
tempo モビール constellation レッド F7Z-1733
33,000 円
軽やかな星座のようなモビール。
天井から降りる1本の糸に「V」の形状をした3つのパーツを取り付けることで完成するモビールです。
パーツの重みで糸がカクンと折れ曲がり、
全体が角度をもったラインとなって現れます。
重力をそのままカタチにした、そんなモビールです。
パッケージには美しいプロポーションになるように、
糸の長さを調整して入れてあります。
箱から取り出して、説明書のように少し形を整えていただけるだけで、
写真のようなモビールを飾っていただけます。
少し大きく感じるかもしれませんが、線が細いのでお部屋に圧迫感を与えません。
モビールと影どちらも美しく、
お部屋で天体観測気分を味わうことができます。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:ステンレス・EVA
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-
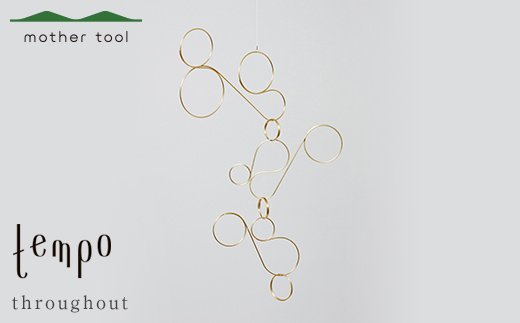
tempo モビール throughout 真鍮 F7Z-1734
55,000 円
アクセサリーを身に着けるように空間を飾るモビール
一本の細い線/ラインが円を描きながら連なるアクセサリーのようなモビールです。
一筆書きの柔らかな曲線の集まりは、
風のない空に浮かぶ雲、
あるいは日々成長していく植物といった、
少しづつ変化していく自然の現象を連想させます。
アクセサリーを身に付けるように空間に浮かべることで、
いつもの部屋に新しい表情が生まれます。
素材は真鍮と銅の2つ。
時間とともに変化していく金属の、
経年変化をたのしんでいただくため表面処理は施していません。
もし変化が気になる場合は金属磨きで磨いていただくともとの状態に戻ります。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:真鍮
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

モビール energyflow ブラック F7Z-1735
36,000 円
点線が浮いているように見えるモビール
細く弾力性のあるステンレス線材を構造にしたモビールです。
最下部のパーツが錘(おもり)となって6本の線材に重力を伝え、
それがそのままモビールの形となります。
重力をそのままカタチにした、
そんなモビールです。
角度によってステンレス線が見えなくなる時、
まるで点線が浮いているかのような不思議な錯覚をおこしてくれます。tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:ステンレス・シリコンガラスチューブ
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール I'm only sleeping ブルー F7Z-1736
55,000 円
万華鏡のような動きを楽しめるステップモビール
寝転んで眺めたいステップモビール。
長い棒が交差することで次々と表情が変わっていきます。
7本の棒がバランスをとりながらゆっくりと形を変化させていくステップモビールです。
ゆっくり動く姿は、夢の中でまどろんでいるようです。
「どうか起こさないで、揺すったりしないで、そっとしておいてよ、このまま眠っていたいんだ」
アクリルは上面のみに塗装していて、
下から見るとすべてに色がついたように、
斜めしたから見ると上下に色がついたように、
真横からみるとクリアに見えます。
瞬間瞬間で変わる万華鏡のような動きをおたのしみください。
栃木県足利市のmother toolの工房で製作しています。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:アクリル樹脂
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール circlewaltz ミックスカラー F7Z-1737
44,000 円
軽やかな動きとリズムを感じられるモビール
紙?いいえ違います金属です。
一見紙のように見える薄い金属の輪っかを吊り下げると、
輪っかの大きさや吊り元の位置によって形が変わります。
重力をうけてできた自然な形が、まるで重力がないかのようにフルフルと軽やかに浮かんでいます。
一番小さな輪はテンションがかかって張りのある円。
大きな輪は上から吊られることでできる下に広がった形、
真ん中のサイズの輪は中心を通り下を磁石で引き上げることでできる横長の円。
シンプルですが重力がなければできない形を視覚化させてくれるモビールです。
緑、黄色、ブルーの3色を組みあわせたMIXカラー。
MIXカラーはステンレス+アルミを用いたシルバーの金具。
栃木県足利市のmother toolの工房でパーツから製作しています。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:アクリル樹脂
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

モビール satellite ウォールナット F7Z-1738
43,000 円
宇宙を感じられるモビール
衛星という意味の木のモビール。
1枚の板をレーザーでカットしてできています。
絶妙なバランスで風をとらえゆらゆらと不思議な動きでゆれるさまはまさに小宇宙。
糸が見えなくなる場所からみると、
木の円板が自由に動くような不思議な浮遊感を味わえます。
栃木県足利市にあるmother toolの工房で1つ1つ丁寧に製作しています。
天然木の突板を使用しているので1つ1つ異なる木目をお楽しみください。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめです。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:天然木突板(ウォールナット)
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール brain レッド F7Z-1739
44,000 円
知恵の輪のように形を変えられるモビール。
同じカタチをした3つのパーツと、
1つのエンドパーツからなるモビールです。
「知恵の輪」あそびのように接続点の組み合わせをかえることで、
まったく違う形状のモビールをつくることができます。
走る犬のような、サンゴのような、鹿の角のようなフォルム。
何に見えるかいろいろ妄想するのも楽しく、想像力を掻き立てられます。
お子さんから大人になるまで楽しめるよう抽象的デザインが魅力です。
オレンジがかったレッドはとても美しい。
栃木県足利市にあるmother toolの工房で1つ1つ丁寧に製作しています。
ステンレス製のパーツに傷のつきにくいマットな粉体塗装を施しています。
時を超えて長く飾っていただけるモビールです。
箱から取り出したらすぐに飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐにお楽しみいただけます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめです。
【産地・原材料名】
素材:ステンレス・アルミニウム
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-
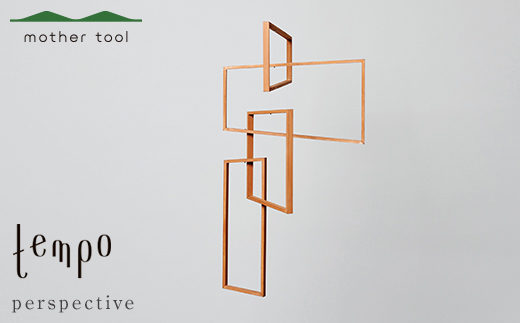
tempo モビール perspective ブラウン F7Z-1740
50,000 円
連続する窓枠のようなモビール
1つあるだけで空間がガラッと変わるモビール。
エアコンや人の動きなどわずかな風で瞬間ごとに形を変えます。
窓際のコーナーなどに飾っていただくと影もたのしんでいただけます。
窓枠1つ1つが空気の流れをとらえて変化する表情は、
角度や動きによって見る人の遠近感に不思議な錯覚を与えてくれます。
栃木県足利市にあるmother toolの工房で1つ1つ丁寧に製作しています。
素材は高知県の森林組合のヒノキを使用し、
木の木目を活かすよう浸透性の塗料で仕上げています。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐにお楽しみいただけます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめです。
繊細な組立て加工とパッケージのため取り出し時には、
糸が切れないようにお気をつけください。
【産地・原材料名】
素材:桧
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

モビール place to be Sサイズ ウォールナット F7Z-1741
22,000 円
小さな点で支えるデスクトップモビール
卓上型のモダンなやじろべえ。
とても小さなひとつの点で重力とつながるスタンドモビール。
繊細なバランスゆえに、
そっと触れるだけで不思議な動きがうまれます。
その存在感が、空間と時間に豊かな表情を与えてくれると考えています。
エアコンや人の動きなどの風でゆっくり動きます。
デスクトップやテレビボードや玄関になどの飾るのがおすすめ。
Sサイズは小さいので場所を選ばず置くことができます。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
素材は天然木突き板でウォールナット。
比重の異なるパーツを1つ1つ微調整しています。
細かなパーツから製作しています。
箱から取り出したら4つのパーツを組み合わせるだけ、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
【産地・原材料名】
素材:天然木突板(ウォールナット)
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール place to be Mサイズ ウォールナット F7Z-1742
35,000 円
小さな点で支えるデスクトップモビール
卓上型のモダンなやじろべえ。
とても小さなひとつの点で重力とつながるスタンドモビール。
繊細なバランスゆえに、
そっと触れるだけで不思議な動きがうまれます。
その存在感が、空間と時間に豊かな表情を与えてくれると考えています。
エアコンや人の動きなどの風でゆっくり動きます。
デスクトップやテレビボードや玄関になどの飾るのがおすすめ。
樹種は黄味がかったケヤキと、濃い茶のウォールナット。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
素材は天然木突き板でウォールナット。
比重の異なるパーツを1つ1つ微調整しています。
細かなパーツから製作しています。箱から取り出したら4つのパーツを組み合わせるだけ、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
【産地・原材料名】
素材:天然木突板(ウォールナット)
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール cliffs ゴールド F7Z-1743
50,000 円
海鳥を連想させるモビール
海鳥に思いを馳せるプロダクト。
素材そのものの重さによってたわんだ(曲がった)1本の線は、
まるで水平線に向かって静かに羽をはばたかせる海鳥を思い起こさせます。
カーボンスチール素材の柔軟性と釣り合いおもりによって動きがうまれるモビールです。
一番下の輪をやさしく真下に引いていただくとはばたきます。
他のものとは違い自分で動かすタイプのモビールになります。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
シンプルな見た目を生み出すのは繊細な手仕事。
色の結び目が目立たないように組み立てられています。
組立済みなので届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ
【産地・原材料名】
素材:高炭素鋼・ステンレス
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール sailaway グレー F7Z-1744
50,000 円
三角が連なるデスクトップモビール
三角が連なるオブジェクト。
このモビールは3つの三角形でできています。
アルミニウムフレームは最も大きいながら最も軽いパーツで、
小さなスチールのブロック(塊)が全体のバランスを保ち、
ウォルナット製のウッドベースがフレームとブロックの両方を支えます。
これら3つの三角形のパーツの比率は全て同じなのです。
三角形の3つの異なる素材がつくるリズムとバランスは、
あたかもあなたが洋上を航海しているかのような柔らかでおだやかな時を創造します。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
三角の錘に個体差があるため1つ1つのバランスを水平に微調整しています。
パーツを取り出し、バランスの位置の印にあわせ台座にのせるだけですぐに飾れます。
船出や出向を意味する縁起のよいモビールは、
新築祝いや開店祝いなどにもおすすめです。
【産地・原材料名】
素材:アルミ・スチール(真鍮メッキ)・ステンレス・木(ウォールナット)
サイズ:W300mm H210mm
生産地:日本
重さ:80g 栃木県足利市
栃木県足利市
-

モビール looping グリーン F7Z-1745
14,000 円
どこにでも持ち運べるデスクトップモビール
どこにいても風と光を感じることのできるモビール。
カラーやグラフィックの大小2つのチューブとそれを支える金属製のワイヤーパーツによって構成されています。
おだやかな風があればモビールはくるくると回りだします。
フラットなパッケージに収められるので、
あなたと一緒に世界中どこでも旅をすることができます。
わずかな風や静電気でアンテナのような動きをします。
カラーのタイプは撮影表のカラーフィルター光が当たることで色が透過し、
置いた場所の影も楽しめます。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
【産地・原材料名】
素材:ポリエステル(カラー)・鉄
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール looping ピンク F7Z-1746
14,000 円
どこにでも持ち運べるデスクトップモビール
どこにいても風と光を感じることのできるモビール。
カラーやグラフィックの大小3つのチューブとそれを支える金属製のワイヤーパーツによって構成されています。
おだやかな風があればモビールはくるくると回りだします。
フラットなパッケージに収められるので、
あなたと一緒に世界中どこでも旅をすることができます。
わずかな風や静電気でアンテナのような動きをします。
カラーのタイプは撮影表のカラーフィルター光が当たることで色が透過し、
置いた場所の影も楽しめます。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
【産地・原材料名】
素材:ポリエステル(カラー)・鉄
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール reverie メープル F7Z-1747
24,000 円
自分で形を変えられる木のモビール。
ひもに沿って木の葉型のパーツを上下にスライドさせることで、
形を自由自在に変えることができます。
紐部分を垂直にするとカタカタと民芸のおもちゃのように、
木のパーツが下に降りてきます。
触って楽しく眺めて癒されるいろいろな楽しみ方ができるモビールです。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
箱から取り出したらすぐ飾れるように組み立ててあるので、
届いてすぐに飾ることができます。
新築祝いや出産祝いなどにもおすすめ。
【産地・原材料名】
素材:天然木突板(メープル)
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

tempo モビール perfectinstance ブルー F7Z-1748
66,000 円
スリットをすれすれで通過するモビール
すれすれの動きが新しいアルミのモビール。
2つのプレートが風によってのびのび回転するモビールです。
染色アルマイト加工された水平と垂直の2つのプレートが交差する形となっています。
真鍮の水平バーによってプレート同士が触れ合わない距離を保ち、
各プレートの真鍮の錘によってプレートが安定してのびやかに回転します。
スリットをすれすれで動く姿は今までにはない動き。
アルミのグラデーションも美しい優雅なモビールです。
tempoのモビールはすべて栃木県足利市のmother toolの工房で製作。
ぶつからず動くようにするためには繊細な組み立て技術が必要となります。
【産地・原材料名】
素材:アルミニウム・真鍮
生産地:日本 栃木県足利市
栃木県足利市
-

アーミラリースフィア F7Z-564
19,000 円
アルミの柔らかい性質を活かして、フラットな状態からリングを交互に手で曲げて立体にします。リング同士の2ヶ所のジョイントをねじっていき、角度を調整すれば自分だけのカタチに。そのままオブジェに、花留めに、吊るして飾ったり色々楽しめます。
【産地・原材料名】
材質:アルミ(A5020)/アルマイト処理
【使用方法】
リングを交互に角度を調整しながら、手で曲げて立体にします。
【注意事項】
アルミはとても錆びにくい金属ですが、使用の状態や経年等で錆び状の汚れが出ることがあります。ご使用後は汚れや水分を十分に拭き取って保管することをおすすめします。金属特有の鋭利な部分がある場合がございます。怪我をされたり周囲のものを傷つけないよう取り扱いには十分お気をつけください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
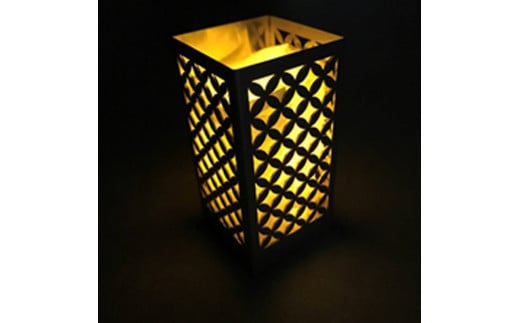
キャンドルスタンド(七宝柄) F7Z-565
17,000 円
スタイリッシュなステンレス製七宝柄キャンドルスタンドです。付属キャンドルの他にお好みのキャンドルやミニライトを入れてお楽しみください。
【産地・原材料名】
材質:ステンレス(SUS304ヘアライン)
【使用方法】
付属キャンドルまたは市販のお好みのキャンドルやミニライトをご使用ください。
【注意事項】
金属の風合いを生かすため、塗装をしていません。
ステンレスはとても錆びにくい金属ですが、使用の状態や経年等で錆び状の汚れが出ることがあります。ご使用後は汚れや水分を十分に拭き取って保管することをおすすめします。金属特有の鋭利な部分がある場合がございます。怪我をされたり周囲のものを傷つけないよう取り扱いには十分お気をつけください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

キャンドルスタンド(ネコ柄) F7Z-566
17,000 円
スタイリッシュなステンレス製ネコ柄キャンドルスタンドです。付属キャンドルの他にお好みのキャンドルやミニライトを入れてお楽しみください。
【産地・原材料名】
材質:ステンレス(SUS304ヘアライン)
【使用方法】
付属キャンドルまたは市販のお好みのキャンドルやミニライトをご使用ください。
【注意事項】
金属の風合いを生かすため、塗装をしていません。
ステンレスはとても錆びにくい金属ですが、使用の状態や経年等で錆び状の汚れが出ることがあります。ご使用後は汚れや水分を十分に拭き取って保管することをおすすめします。金属特有の鋭利な部分がある場合がございます。怪我をされたり周囲のものを傷つけないよう取り扱いには十分お気をつけください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

パワードエッグ力丸くん Mサイズ30個 〈12月受付分は翌年1月以降の発送とな…
7,000 円
コクのあるおいしい卵を求める方のために、鶏の健康とたまごのおいしさに徹底的にこだわりました。
トウモロコシを主原料に、高品質の魚粉や海藻、牧草、カキ貝や藻類の化石、きな粉、胡麻やニンニク、パプリカ、天然酵母や鶏の体に良い生きた菌類などさまざまな飼料を贅沢にバランス良く与えております。
この良質なエサが「日持ちが良く、コクがあるのに生臭く無い」 おいしい卵の理由です。
まずは一度お召し上がりいただき、違いをお確かめ下さい。
【産地・原材料名】
国産 栃木県
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
※商品到着後は冷蔵庫に保管し、生食の場合は賞味期限内にお召し上がりください。
※賞味期限経過後、又は卵の殻にヒビがある場合は、充分に加熱してお早めにお召し上がりください。
※非常に壊れやすい商品の為、運送中に破損してしまう場合ございます。万一破損があった場合には商品同封の連絡先までご連絡ください。
※受付順に順次発送いたしますが、生産状況により長くお待たせする場合もございますので、予めご了承ください。
※パッケージが変更になる場合がございます。
※夏場は冷蔵便でお届けいたします。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

パワードエッグ力丸くん Mサイズ60個 〈12月受付分は翌年1月以降の発送とな…
12,000 円
コクのあるおいしい卵を求める方のために、鶏の健康とたまごのおいしさに徹底的にこだわりました。
トウモロコシを主原料に、高品質の魚粉や海藻、牧草、カキ貝や藻類の化石、きな粉、胡麻やニンニク、パプリカ、天然酵母や鶏の体に良い生きた菌類などさまざまな飼料を贅沢にバランス良く与えております。
この良質なエサが「日持ちが良く、コクがあるのに生臭く無い」 おいしい卵の理由です。
まずは一度お召し上がりいただき、違いをお確かめ下さい。
【産地・原材料名】
国産 栃木県
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
※商品到着後は冷蔵庫に保管し、生食の場合は賞味期限内にお召し上がりください。
※賞味期限経過後、又は卵の殻にヒビがある場合は、充分に加熱してお早めにお召し上がりください。
※非常に壊れやすい商品の為、運送中に破損してしまう場合ございます。万一破損があった場合には商品同封の連絡先までご連絡ください。
※受付順に順次発送いたしますが、生産状況により長くお待たせする場合もございますので、予めご了承ください。
※パッケージが変更になる場合がございます。
※夏場は冷蔵便でお届けいたします。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

自家製燻製 スモークチーズ はまちいず2個 桜チップ 燻製 手作り 濃厚 スモ…
5,000 円
桜チップでいぶした手作りスモークチーズとろりとしたチーズが絶品です。 スタートは家族のために燻製していたものが、あまりの美味しさに商品化。秘伝のスモーク方法により、外は香ばしく中はトロリとした絶妙の味わいです。お客様からはチーズよりもチーズらしい!と大好評でリピーター拡大中です。そのままでも温めてもOK。薄くスライスしてカリカリになるまで電子レンジで加熱すると絶品のチーズスナックに早変わりです!コーヒーなどのおやつやお酒のおつまみにもぴったりです。
【産地・原材料名】
ナチュラルチーズ/乳化剤
栄養成分表示100gあたりエネルギー335kcal、たんぱく質20.9g、脂質27.4g、飽和脂肪酸16.5g、糖質0~3.9g、炭水化物0~3.9g、食物繊維0.0g、食塩相当量2.5g
アレルゲン(27品目中)乳成分
【使用方法】
自家製手作り燻製を行っています。開封後はお早めにお召し上がり下さい。
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
アレルゲン(27品目中)乳成分 栃木県足利市
栃木県足利市
-

自家製燻製 スモークチーズ はまちいず3個 桜チップ 燻製 手作り 濃厚 スモ…
7,000 円
桜チップでいぶした手作りスモークチーズとろりとしたチーズが絶品です。 スタートは家族のために燻製していたものが、あまりの美味しさに商品化。秘伝のスモーク方法により、外は香ばしく中はトロリとした絶妙の味わいです。お客様からはチーズよりもチーズらしい!と大好評でリピーター拡大中です。そのままでも温めてもOK。薄くスライスしてカリカリになるまで電子レンジで加熱すると絶品のチーズスナックに早変わりです!コーヒーなどのおやつやお酒のおつまみにもぴったりです。
【産地・原材料名】
ナチュラルチーズ/乳化剤
栄養成分表示100gあたりエネルギー335kcal、たんぱく質20.9g、脂質27.4g、飽和脂肪酸16.5g、糖質0~3.9g、炭水化物0~3.9g、食物繊維0.0g、食塩相当量2.5g
アレルゲン(27品目中)乳成分
【使用方法】
自家製手作り燻製を行っています。開封後はお早めにお召し上がり下さい。
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
アレルゲン(27品目中)乳成分 栃木県足利市
栃木県足利市
-

自家製燻製 スモークチーズ はまちいず4個 桜チップ 燻製 手作り 濃厚 スモ…
9,000 円
桜チップでいぶした手作りスモークチーズとろりとしたチーズが絶品です。 スタートは家族のために燻製していたものが、あまりの美味しさに商品化。秘伝のスモーク方法により、外は香ばしく中はトロリとした絶妙の味わいです。お客様からはチーズよりもチーズらしい!と大好評でリピーター拡大中です。そのままでも温めてもOK。薄くスライスしてカリカリになるまで電子レンジで加熱すると絶品のチーズスナックに早変わりです!コーヒーなどのおやつやお酒のおつまみにもぴったりです。
【産地・原材料名】
ナチュラルチーズ/乳化剤
栄養成分表示100gあたりエネルギー335kcal、たんぱく質20.9g、脂質27.4g、飽和脂肪酸16.5g、糖質0~3.9g、炭水化物0~3.9g、食物繊維0.0g、食塩相当量2.5g
アレルゲン(27品目中)乳成分
【使用方法】
自家製手作り燻製を行っています。開封後はお早めにお召し上がり下さい。
【保存方法】
要冷蔵(10℃以下)
【注意事項】
アレルゲン(27品目中)乳成分 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング レッド 180×195 脚付きマットレス F7Z-1091
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング イエロー 180×195 脚付きマットレス F7Z-1099
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
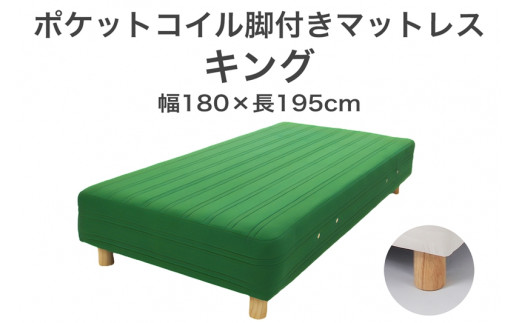
ザ・ベッド キング グリーン 180×195 脚付きマットレス F7Z-1107
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング オレンジ 180×195 脚付きマットレス F7Z-1115
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド キング ライトブラウン 180×195 脚付きマットレス F7Z-1123
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
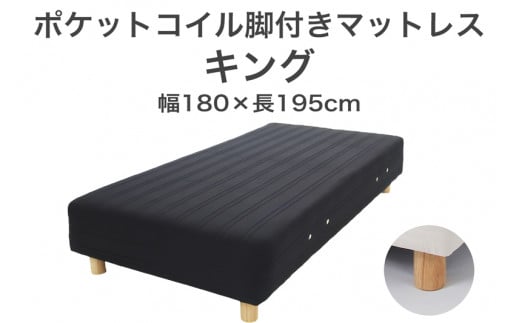
ザ・ベッド キング ブラック 180×195 脚付きマットレス F7Z-1131
350,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、キング/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 アイボリー 80×195 脚付きマットレス F7Z-1139
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 ブルー 80×195 脚付きマットレス F7Z-1147
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 レッド 80×195 脚付きマットレス F7Z-1155
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 イエロー 80×195 脚付きマットレス F7Z-1163
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 グリーン 80×195 脚付きマットレス F7Z-1171
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 オレンジ 80×195 脚付きマットレス F7Z-1179
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル80 ライトブラウン 80×195 脚付きマットレス F7Z-11…
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
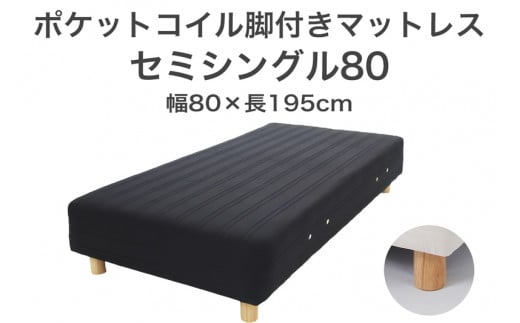
ザ・ベッド セミシングル80 ブラック 80×195 脚付きマットレス F7Z-1195
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル80/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 アイボリー 90×195 脚付きマットレス F7Z-1203
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 ブルー 90×195 脚付きマットレス F7Z-1211
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 レッド 90×195 脚付きマットレス F7Z-1219
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 イエロー 90×195 脚付きマットレス F7Z-1227
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 グリーン 90×195 脚付きマットレス F7Z-1235
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 オレンジ 90×195 脚付きマットレス F7Z-1243
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミシングル90 ライトブラウン 90×195 脚付きマットレス F7Z-12…
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
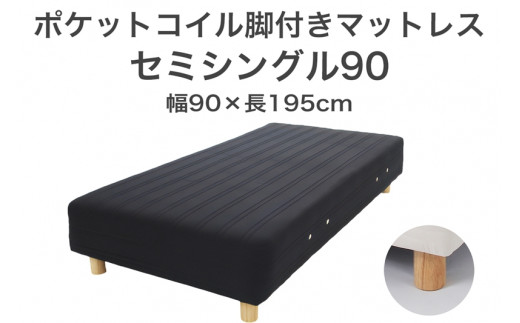
ザ・ベッド セミシングル90 ブラック 90×195 脚付きマットレス F7Z-1259
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 80サイズ 生成 80×50cm 脚付きマッ…
91,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅80×50cm。
セミシングル80サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 90サイズ 生成 90×50cm 脚付きマッ…
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅90×50cm。
セミシングル90サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ シングル サイズ 生成 97×50cm 脚付きマットレス …
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅97×50cm。
シングルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミダブル サイズ 生成 120×50cm 脚付きマットレ…
111,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅120×50cm。
セミダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ ダブル サイズ 生成 140×50cm 脚付きマットレス …
122,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅140×50cm。
ダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ クイーン サイズ 生成 160×50cm 脚付きマットレス…
150,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅160×50cm。
クイーンサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ キング サイズ 生成 180×50cm 脚付きマットレス …
172,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅180×50cm。
キングサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは7cm。低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【保存方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 80サイズ 生成 80×50cm 脚付きマッ…
91,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅80×50cm。
セミシングル80サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 90サイズ 生成 90×50cm 脚付きマッ…
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅90×50cm。
セミシングル90サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ シングル サイズ 生成 97×50cm 脚付きマットレス …
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅97×50cm。
シングルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミダブル サイズ 生成 120×50cm 脚付きマットレ…
111,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅120×50cm。
セミダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ ダブル サイズ 生成 140×50cm 脚付きマットレス …
122,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅140×50cm。
ダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ クイーン サイズ 生成 160×50cm 脚付きマットレス…
150,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅160×50cm。
クイーンサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ キング サイズ 生成 180×50cm 脚付きマットレス …
172,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅180×50cm。
キングサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは12cm。ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 80サイズ 生成 80×50cm 脚付きマッ…
91,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅80×50cm。
セミシングル80サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 90サイズ 生成 90×50cm 脚付きマッ…
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅90×50cm。
セミシングル90サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ シングル サイズ 生成 97×50cm 脚付きマットレス …
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅97×50cm。
シングルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミダブル サイズ 生成 120×50cm 脚付きマットレ…
111,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅120×50cm。
セミダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ ダブル サイズ 生成 140×50cm 脚付きマットレス …
122,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅140×50cm。
ダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ クイーン サイズ 生成 160×50cm 脚付きマットレス…
150,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅160×50cm。
クイーンサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ キング サイズ 生成 180×50cm 脚付きマットレス …
172,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅180×50cm。
キングサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは18.5cm。ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ シングル サイズ 生成 97×50cm 脚付きマットレス …
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅97×50cm。
シングルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 80サイズ 生成 80×50cm 脚付きマッ…
91,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅80×50cm。
セミシングル80サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミシングル 90サイズ 生成 90×50cm 脚付きマッ…
93,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅90×50cm。
セミシングル90サイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミシングル90用/生成のお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ ダブル サイズ 生成 140×50cm 脚付きマットレス …
122,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅140×50cm。
ダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ セミダブル サイズ 生成 120×50cm 脚付きマットレ…
111,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅120×50cm。
セミダブルサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ キング サイズ 生成 180×50cm 脚付きマットレス …
172,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅180×50cm。
キングサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド 延長用 ベンチ クイーン サイズ 生成 160×50cm 脚付きマットレス…
150,000 円
ベッドベンチは身長の高い方が、お好みでベッドの長さを延長できるベンチです。
ウレタンチップの寝心地は、椅子やマットレスのクッション材として幅広く使用されており、へたれにくく、型崩れしない、耐久性に優れた性質を持っています。
ベッドの延長用や腰掛けベンチとして使用したい方にもおすすめです。
また、張り生地は、心地よいふんわり感をだすため、フェルトの上にウレタンをキルト加工。JIS規格に基づく耐久試験をクリアした、安心の品質です。
ベンチのサイズは幅160×50cm。
クイーンサイズのベッド用で、長さが50cm延長できます。
~脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄です。
高さは22cm。高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
・ベッドの足元に配置してご利用ください。使用前にベンチが安定して固定されていることを確認し、安全に使用してください。
・木脚はネジ式となっており、まっすぐに無理なく差し込んで下さい。斜めに無理に差し込んだ場合、破損の原因となります。入りにくい場合には一度抜いて、まっすぐに入っているかご確認下さい。
・製造完了後すぐにお客さまに商品をお届している都合上、開梱直後、木枠で使用している木材特有の香りや臭いがする場合があります。その際は、風通しの良い場所に1~3日置いて頂けると自然に香りは消えていきますのでご安心ください。
【注意事項】
〇荷受けの際の注意点
・掲載画像を参考に間口の広さをご確認ください。
・お届けは玄関先までとなります。
〇お届けに関する注意点〈お届け日について〉
・納期は目安です。
・お届け日の指定はできません。
・出荷日が確定次第、事前にご連絡させていただきます。
・お届け日当日に運送会社からご連絡します。
・離島への配達はできません。予めご了承ください。
〈搬入ができず返送になった場合の送料負担について〉
・搬入ができず返送になった場合には、往復の送料は寄付者様のご負担となります。
※間口の広さや搬入先までの経路について、お申込み前にご確認ください。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス シングル 97×195cm 厚さ20cm ポケットコイル スプリング ア…
80,000 円
ザ・マットレス (THE MATTRESS)は、「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”
人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
あなたはマットレスに、何を求めますか?
快適な寝心地
深い眠り
爽やかな目覚め
全てを叶えたいあなたには、
“シンプルに眠る”をテーマに作り上げた、ポケットコイルスプリングマットレス「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」がおすすめです。
世の中には様々なマットレスがありますが、シンプルなものが一番使いやすい。
身体への負担をより少なくし、睡眠の質を上げるために開発された「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」は、あなたの睡眠に欠かせないものになるでしょう。
【おすすめのポイント】
・シンプルなデザインなので、インテリアやライフスタイルに調和します。
・ポケットコイルスプリングを使用。ストレスのない寝返りをサポートします。
・たっぷり厚み20cmマットレス。ベッドフレームの上に乗せて使用することも可能。
・床や畳に敷いて、マットレス1枚でもご使用可能。いま流行の低めベッドとしてオシャレな寝室を演出したり、お子さまやご年配の方の安全を配慮した寝具としてもご使用いただけます。
・ザ・マットレスシリーズは、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングと、サイズを豊富に取り揃えています。
・圧縮梱包でお届け。マットレスの受け取りから、部屋への設置も楽々。また、密封梱包なので、衛生面も安心です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
マットレスの復元には開封してから1~2日程度かかります。
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【内容・サイズ】
ポケットコイルマットレス シングル(97×195cm)
コイル数:465個(並行配列)
圧縮梱包タイプ 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス セミダブル 120×195cm 厚さ20cm ポケットコイル スプリング …
100,000 円
ザ・マットレス (THE MATTRESS)は、「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”
人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
あなたはマットレスに、何を求めますか?
快適な寝心地
深い眠り
爽やかな目覚め
全てを叶えたいあなたには、
“シンプルに眠る”をテーマに作り上げた、ポケットコイルスプリングマットレス「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」がおすすめです。
世の中には様々なマットレスがありますが、シンプルなものが一番使いやすい。
身体への負担をより少なくし、睡眠の質を上げるために開発された「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」は、あなたの睡眠に欠かせないものになるでしょう。
【おすすめのポイント】
・シンプルなデザインなので、インテリアやライフスタイルに調和します。
・ポケットコイルスプリングを使用。ストレスのない寝返りをサポートします。
・たっぷり厚み20cmマットレス。ベッドフレームの上に乗せて使用することも可能。
・床や畳に敷いて、マットレス1枚でもご使用可能。いま流行の低めベッドとしてオシャレな寝室を演出したり、お子さまやご年配の方の安全を配慮した寝具としてもご使用いただけます。
・ザ・マットレスシリーズは、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングと、サイズを豊富に取り揃えています。
・圧縮梱包でお届け。マットレスの受け取りから、部屋への設置も楽々。また、密封梱包なので、衛生面も安心です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
マットレスの復元には開封してから1~2日程度かかります。
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【内容・サイズ】
ポケットコイルマットレス セミダブル(120×195cm)
コイル数:589個(並行配列)
圧縮梱包タイプ 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス ダブル 140×195cm 厚さ20cm ポケットコイル スプリング アイ…
120,000 円
ザ・マットレス (THE MATTRESS)は、「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”
人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
あなたはマットレスに、何を求めますか?
快適な寝心地
深い眠り
爽やかな目覚め
全てを叶えたいあなたには、
“シンプルに眠る”をテーマに作り上げた、ポケットコイルスプリングマットレス「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」がおすすめです。
世の中には様々なマットレスがありますが、シンプルなものが一番使いやすい。
身体への負担をより少なくし、睡眠の質を上げるために開発された「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」は、あなたの睡眠に欠かせないものになるでしょう。
【おすすめのポイント】
・シンプルなデザインなので、インテリアやライフスタイルに調和します。
・ポケットコイルスプリングを使用。ストレスのない寝返りをサポートします。
・たっぷり厚み20cmマットレス。ベッドフレームの上に乗せて使用することも可能。
・床や畳に敷いて、マットレス1枚でもご使用可能。いま流行の低めベッドとしてオシャレな寝室を演出したり、お子さまやご年配の方の安全を配慮した寝具としてもご使用いただけます。
・ザ・マットレスシリーズは、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングと、サイズを豊富に取り揃えています。
・圧縮梱包でお届け。マットレスの受け取りから、部屋への設置も楽々。また、密封梱包なので、衛生面も安心です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
マットレスの復元には開封してから1~2日程度かかります。
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【内容・サイズ】
ポケットコイルマットレス ダブル(140×195cm)
コイル数:682個(並行配列)
圧縮梱包タイプ 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス クイーン 160×195cm 厚さ20cm ポケットコイル スプリング ア…
250,000 円
ザ・マットレス (THE MATTRESS)は、「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”
人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
あなたはマットレスに、何を求めますか?
快適な寝心地
深い眠り
爽やかな目覚め
全てを叶えたいあなたには、
“シンプルに眠る”をテーマに作り上げた、ポケットコイルスプリングマットレス「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」がおすすめです。
世の中には様々なマットレスがありますが、シンプルなものが一番使いやすい。
身体への負担をより少なくし、睡眠の質を上げるために開発された「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」は、あなたの睡眠に欠かせないものになるでしょう。
【おすすめのポイント】
・シンプルなデザインなので、インテリアやライフスタイルに調和します。
・ポケットコイルスプリングを使用。ストレスのない寝返りをサポートします。
・たっぷり厚み20cmマットレス。ベッドフレームの上に乗せて使用することも可能。
・床や畳に敷いて、マットレス1枚でもご使用可能。いま流行の低めベッドとしてオシャレな寝室を演出したり、お子さまやご年配の方の安全を配慮した寝具としてもご使用いただけます。
・ザ・マットレスシリーズは、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングと、サイズを豊富に取り揃えています。
・圧縮梱包でお届け。マットレスの受け取りから、部屋への設置も楽々。また、密封梱包なので、衛生面も安心です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
マットレスの復元には開封してから1~2日程度かかります。
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【内容・サイズ】
ポケットコイルマットレス クイーン(160×195cm)
コイル数:775個(並行配列)
圧縮梱包タイプ 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス キング 180×195cm 厚さ20cm ポケットコイル スプリング アイ…
300,000 円
ザ・マットレス (THE MATTRESS)は、「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”
人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
あなたはマットレスに、何を求めますか?
快適な寝心地
深い眠り
爽やかな目覚め
全てを叶えたいあなたには、
“シンプルに眠る”をテーマに作り上げた、ポケットコイルスプリングマットレス「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」がおすすめです。
世の中には様々なマットレスがありますが、シンプルなものが一番使いやすい。
身体への負担をより少なくし、睡眠の質を上げるために開発された「ザ・マットレス (THE MATTRESS)」は、あなたの睡眠に欠かせないものになるでしょう。
【おすすめのポイント】
・シンプルなデザインなので、インテリアやライフスタイルに調和します。
・ポケットコイルスプリングを使用。ストレスのない寝返りをサポートします。
・たっぷり厚み20cmマットレス。ベッドフレームの上に乗せて使用することも可能。
・床や畳に敷いて、マットレス1枚でもご使用可能。いま流行の低めベッドとしてオシャレな寝室を演出したり、お子さまやご年配の方の安全を配慮した寝具としてもご使用いただけます。
・ザ・マットレスシリーズは、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングと、サイズを豊富に取り揃えています。
・圧縮梱包でお届け。マットレスの受け取りから、部屋への設置も楽々。また、密封梱包なので、衛生面も安心です。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
マットレスの復元には開封してから1~2日程度かかります。
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【内容・サイズ】
ポケットコイルマットレス キング(180×195cm)
コイル数:868個(並行配列)
圧縮梱包タイプ 栃木県足利市
栃木県足利市
-
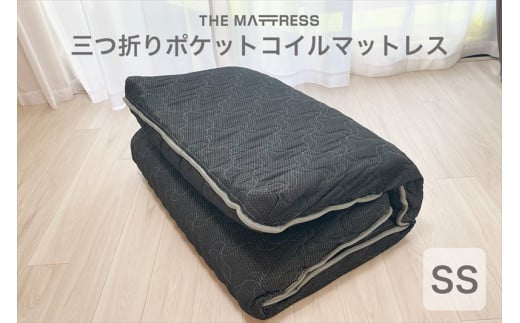
ザ・マットレス 三つ折りポケットコイルマットレス セミシングル 83×195cm …
70,000 円
「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
【おすすめポイント】
1.収納や持ち運びが簡単!
一度マットレスを広げた後も、簡単に三つ折りをすることができます。
引っ越しでマットレスを持ち運びたい場合や、
ご家庭での限られたスペースに収納したい場合などにもおすすめです。
2.ほどよい硬さのマットレスで寝心地が抜群!
マットレスの硬さは、ほどよく弾力性があるため、
沈み込みすぎず、しっかりと身体を支えてくれます。
3.銀イオンの力による抗菌効果も!
使用している側生地には抗菌効果のある銀糸を使用しています。
こまめなお手入れが難しい、という方にもおすすめです。
◆ポケットコイルスプリングマットレスとは・・・
コイルをひとつずつ小さな袋に入れて敷き詰めたマットレスです。
それぞれのコイルが独立し、点で身体を支えるので、体圧分散性が高まりスムーズな寝返りが打てます。
使用中は身体にかかる圧力を分散させることで、
背中やお尻、かかとなどの圧力がかかりやすい部分の負担を和らげることができ、身体へのストレスが少なくなります。
また、コイルの1つ1つが独立していることで、隣に寝ている人の寝返り振動は伝わりにくく、
身体の凹凸にフィットするため、自然な寝姿勢を保つことができ、快適におやすみいただけます。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【注意事項】
※再度三つ折りにする場合は、三つ折りの形はキープされません。紐などで固定していただくことをおすすめいたします。
※配達員による設置は行いません。お届けは玄関先までとなっております。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス 三つ折りポケットコイルマットレス シングル 100×195cm 厚さ…
80,000 円
「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
【おすすめポイント】
1.収納や持ち運びが簡単!
一度マットレスを広げた後も、簡単に三つ折りをすることができます。
引っ越しでマットレスを持ち運びたい場合や、
ご家庭での限られたスペースに収納したい場合などにもおすすめです。
2.ほどよい硬さのマットレスで寝心地が抜群!
マットレスの硬さは、ほどよく弾力性があるため、
沈み込みすぎず、しっかりと身体を支えてくれます。
3.銀イオンの力による抗菌効果も!
使用している側生地には抗菌効果のある銀糸を使用しています。
こまめなお手入れが難しい、という方にもおすすめです。
◆ポケットコイルスプリングマットレスとは・・・
コイルをひとつずつ小さな袋に入れて敷き詰めたマットレスです。
それぞれのコイルが独立し、点で身体を支えるので、体圧分散性が高まりスムーズな寝返りが打てます。
使用中は身体にかかる圧力を分散させることで、
背中やお尻、かかとなどの圧力がかかりやすい部分の負担を和らげることができ、身体へのストレスが少なくなります。
また、コイルの1つ1つが独立していることで、隣に寝ている人の寝返り振動は伝わりにくく、
身体の凹凸にフィットするため、自然な寝姿勢を保つことができ、快適におやすみいただけます。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【注意事項】
※再度三つ折りにする場合は、三つ折りの形はキープされません。紐などで固定していただくことをおすすめいたします。
※配達員による設置は行いません。お届けは玄関先までとなっております。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス 三つ折りポケットコイルマットレス セミダブル 123×195cm 厚…
100,000 円
「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
【おすすめポイント】
1.収納や持ち運びが簡単!
一度マットレスを広げた後も、簡単に三つ折りをすることができます。
引っ越しでマットレスを持ち運びたい場合や、
ご家庭での限られたスペースに収納したい場合などにもおすすめです。
2.ほどよい硬さのマットレスで寝心地が抜群!
マットレスの硬さは、ほどよく弾力性があるため、
沈み込みすぎず、しっかりと身体を支えてくれます。
3.銀イオンの力による抗菌効果も!
使用している側生地には抗菌効果のある銀糸を使用しています。
こまめなお手入れが難しい、という方にもおすすめです。
◆ポケットコイルスプリングマットレスとは・・・
コイルをひとつずつ小さな袋に入れて敷き詰めたマットレスです。
それぞれのコイルが独立し、点で身体を支えるので、体圧分散性が高まりスムーズな寝返りが打てます。
使用中は身体にかかる圧力を分散させることで、
背中やお尻、かかとなどの圧力がかかりやすい部分の負担を和らげることができ、身体へのストレスが少なくなります。
また、コイルの1つ1つが独立していることで、隣に寝ている人の寝返り振動は伝わりにくく、
身体の凹凸にフィットするため、自然な寝姿勢を保つことができ、快適におやすみいただけます。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【注意事項】
※再度三つ折りにする場合は、三つ折りの形はキープされません。紐などで固定していただくことをおすすめいたします。
※配達員による設置は行いません。お届けは玄関先までとなっております。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・マットレス 三つ折りポケットコイルマットレス ダブル 143×195cm 厚さ10…
120,000 円
「シンプルに眠る」をテーマにしたポケットコイルスプリングマットレスの日本製ブランドです。
“身体にかかる地球の重力を、ポケットコイルが点で支える”人生の3分の1の時間、身体を支えているマットレス。
1日の疲れを回復させ、心と身体を整えるためにも、質の良い睡眠は欠かせません。
【おすすめポイント】
1.収納や持ち運びが簡単!
一度マットレスを広げた後も、簡単に三つ折りをすることができます。
引っ越しでマットレスを持ち運びたい場合や、
ご家庭での限られたスペースに収納したい場合などにもおすすめです。
2.ほどよい硬さのマットレスで寝心地が抜群!
マットレスの硬さは、ほどよく弾力性があるため、
沈み込みすぎず、しっかりと身体を支えてくれます。
3.銀イオンの力による抗菌効果も!
使用している側生地には抗菌効果のある銀糸を使用しています。
こまめなお手入れが難しい、という方にもおすすめです。
◆ポケットコイルスプリングマットレスとは・・・
コイルをひとつずつ小さな袋に入れて敷き詰めたマットレスです。
それぞれのコイルが独立し、点で身体を支えるので、体圧分散性が高まりスムーズな寝返りが打てます。
使用中は身体にかかる圧力を分散させることで、
背中やお尻、かかとなどの圧力がかかりやすい部分の負担を和らげることができ、身体へのストレスが少なくなります。
また、コイルの1つ1つが独立していることで、隣に寝ている人の寝返り振動は伝わりにくく、
身体の凹凸にフィットするため、自然な寝姿勢を保つことができ、快適におやすみいただけます。
【産地・原材料名】
日本製 栃木県足利市
【使用方法】
直接床に置くと、通気が悪くなりカビが生える原因になります。通気性の良い、すのこやベッドをご利用ください。
数カ月に一度、立てかけて風を通し、マットレスの上下を逆にして、同じ場所に負荷がかかり続けないようにしてください。
【注意事項】
※再度三つ折りにする場合は、三つ折りの形はキープされません。紐などで固定していただくことをおすすめいたします。
※配達員による設置は行いません。お届けは玄関先までとなっております。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル アイボリー 97×195 脚付きマットレス F7Z-755
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル ブルー 97×195 脚付きマットレス F7Z-763
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル レッド 97×195 脚付きマットレス F7Z-771
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル イエロー 97×195 脚付きマットレス F7Z-779
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル グリーン 97×195 脚付きマットレス F7Z-787
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル オレンジ 97×195 脚付きマットレス F7Z-795
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド シングル ライトブラウン 97×195 脚付きマットレス F7Z-803
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
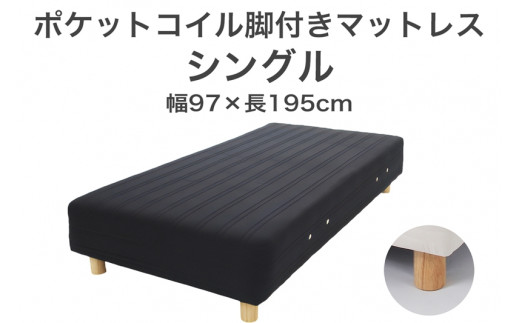
ザ・ベッド シングル ブラック 97×195 脚付きマットレス F7Z-811
150,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、シングル/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル アイボリー 120×195 脚付きマットレス F7Z-819
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル ブルー 120×195 脚付きマットレス F7Z-827
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル レッド 120×195 脚付きマットレス F7Z-835
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル イエロー 120×195 脚付きマットレス F7Z-843
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル グリーン 120×195 脚付きマットレス F7Z-851
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル オレンジ 120×195 脚付きマットレス F7Z-859
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド セミダブル ライトブラウン 120×195 脚付きマットレス F7Z-867
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
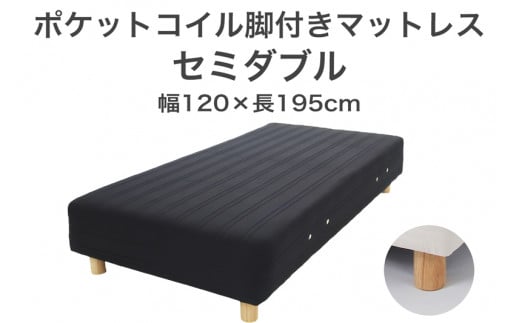
ザ・ベッド セミダブル ブラック 120×195 脚付きマットレス F7Z-875
200,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、セミダブル/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル アイボリー 140×195 脚付きマットレス F7Z-883
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル ブルー 140×195 脚付きマットレス F7Z-891
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル レッド 140×195 脚付きマットレス F7Z-899
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル イエロー 140×195 脚付きマットレス F7Z-907
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル グリーン 140×195 脚付きマットレス F7Z-915
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル オレンジ 140×195 脚付きマットレス F7Z-923
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ダブル ライトブラウン 140×195 脚付きマットレス F7Z-931
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-
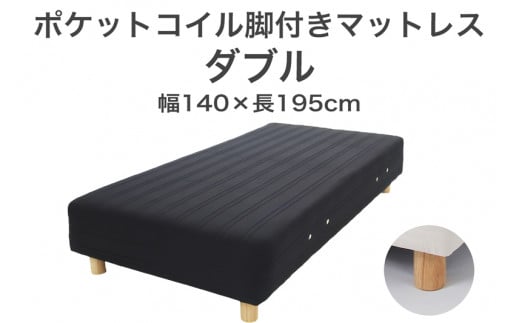
ザ・ベッド ダブル ブラック 140×195 脚付きマットレス F7Z-939
250,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ダブル/ブラックのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル アイボリー 152×195 脚付きマットレス F7Z-947
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/アイボリーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル ブルー 152×195 脚付きマットレス F7Z-955
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/ブルーのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル レッド 152×195 脚付きマットレス F7Z-963
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/レッドのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル イエロー 152×195 脚付きマットレス F7Z-971
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/イエローのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル グリーン 152×195 脚付きマットレス F7Z-979
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/グリーンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル オレンジ 152×195 脚付きマットレス F7Z-987
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/オレンジのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
-

ザ・ベッド ワイドダブル ライトブラウン 152×195 脚付きマットレス F7Z-995
300,000 円
ナチュラル素材のシンプルなベッド。
国内製造にこだわり、生地の裁断から縫製、仕上げまですべて熟練の職人が
一つひとつ手作業で作っています。
いろいろなベッドが世の中には世の中にはありますが、「シンプルなものが1番使いやすい!」
そうして出来上がったのが”THE BED”。
”THE BED”は、寝返りの振動を与えにくいポケットコイルを使用。
ポケットコイルの寝ごこちは、体重や体の凹凸にそれぞれのコイルが反応して、
カラダを優しくサポートし、フィット感があります。
1日8時間、人生の3分の1と言われている睡眠時間。その時間をともにするベッドだから、
清潔で安心してお使いいただける品質の良いものだけをお届けしたい、という職人の願いが込められています。
~張り生地について~
"THE BED"の張り生地は、天然由来コットン100%です。優しい風合いで、しっかりとした生地です。コットンは吸湿性がよく、柔らかくサラリとした感触で肌触りが良いのが特徴です。
優しいナチュラルな風合いを出すために、綿花の素材を繊維に織り込んでいるのが特徴です。
~選べる脚の色と高さ~
暖かみのあるナチュラルな木目柄と
濃厚で高級感のあるブラウンの2色からお選びいただけます。
〇7cm
低めのベッドなので、落ち着いたお部屋のコーディネートが可能です。
〇12cm
ほどよい高さのベッドなので、圧迫感のない落ち着いたお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇18.5cm
ゆとりのある高さのベッドなので、ベッド下のスペースも有効活用したお部屋を
コーディネートすることも可能です。
〇22cm
高めのベッドなので、ベッド下の空間も収納スペースとして利用でき、
すっきりしたお部屋をコーディネートすることも可能です。
※こちらは、ワイドダブル/ライトブラウンのお申込みページです。
脚の高さと色をお選びいただけます。 栃木県足利市
栃木県足利市
現在進捗情報はありません。
栃木県足利市
足利市(あしかがし)は、栃木県南部に位置し、東京から北へ80キロメートルほどの位置にある、歴史と文化の香り高いまちです。北部を足尾山地の緑に囲まれ、南部には関東平野が広がり、中央部には渡良瀬川の美しい流れがあります。
日本遺産に認定された日本最古の学校「足利学校」や、国宝「鑁阿寺」、米国CNNによる「世界の夢の旅行先10カ所」に選ばれた「あしかがフラワーパーク」などの歴史的な建造物や観光資源も数多くあり、多くの観光客で賑わいます。
産業では、古くから織物のまちとして知られ、現在も新たな視点で織物産業の活性化を図ろうとする事業者が多くいます。また、アルミや自動車部品、プラスチック工業などを中心に、総合的な商工業都市となっています。
年間を通じた日照量の多さと肥沃な土壌のおかげで、市内全域で生産される農産物も自慢のひとつで、栃木県産いちごの発祥の地でもあります。




























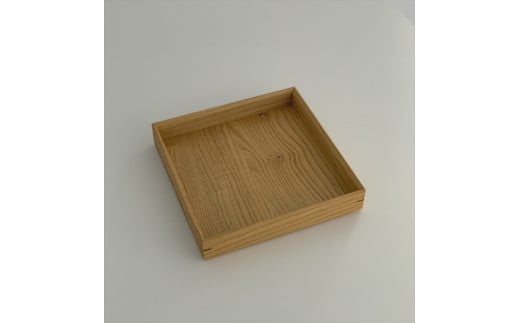

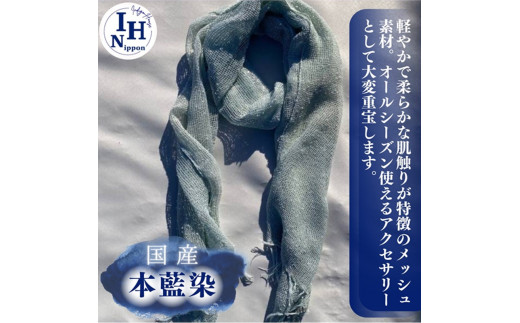

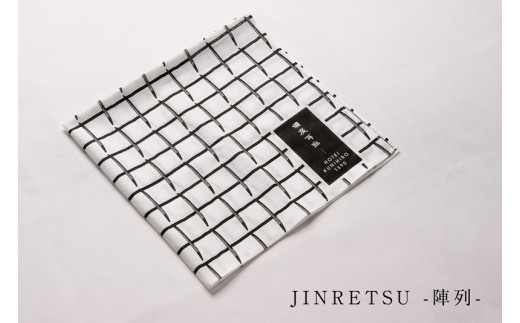

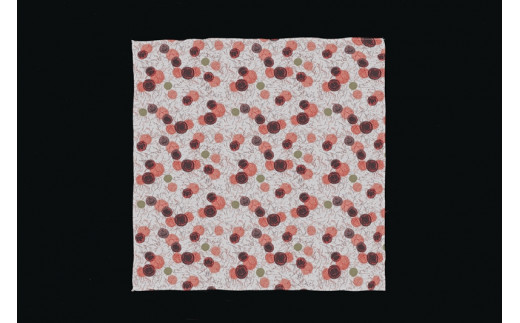
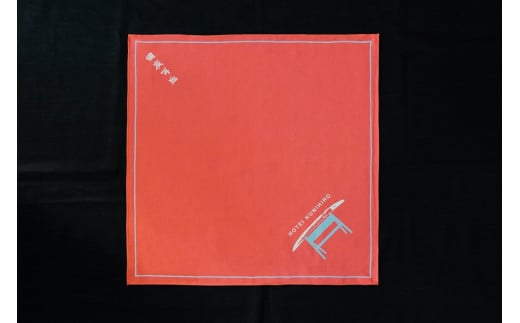













































































コメント投稿をありがとうございます!
あなたのその想いが
プロジェクトを動かしています。
投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。
反映まで数日かかることがあります。