【ネクストゴール800万円に挑戦中!】豊かな漁村「通浜」を後世に残したい!水産資源を活用した新たな価値創造プロジェクト始動!!
カテゴリー:食・農林水産業・商工業
寄付金額 8,698,000円
目標金額:5,000,000円
- 達成率
- 173.9%
- 支援人数
- 356人
- 終了まで
- 受付終了
宮崎県川南町(みやざきけん かわみなみちょう)
寄付募集期間:2025年9月12日~2025年12月10日(90日間)
宮崎県川南町

川南町唯一の漁村である通浜地区。そこで水揚げされる水産物は宮崎県内でも高い評価を得ています。その理由の1つに、40年以上も前に全国で初めて撒き餌を禁止し、持続可能な漁法を取り入れたことにあります。しかし、時代が変わるとともに海洋環境も変化し、獲れる魚の量や、日本人の魚の消費量は激減しました。追い打ちをかけるように漁業従事者の高齢化、後継者不足など様々な問題に直面しています。そのような環境にありながらも、昔ながらの漁法を守り、継承し、漁村「通浜」を後世に引き継いでいくために、令和7年8月に、業種を超えた団体で組織する「通浜ブランド創出協議会」を設立しました。今回のこのプロジェクトでは、この協議会が主体となって取り組んでいく通浜で水揚げされた品質の高い水産物のブランド化、水産資源を活用した商品開発をする際の運用資金に充てさせていただきます。宮崎県の小さな漁村の挑戦を是非ご支援ください。
豊かな漁村「通浜」を後世に残したい!
川南町内の唯一の漁村「通浜」
川南町は宮崎県のほぼ中央部に位置し、東は日向灘、西は尾鈴山に囲まれ、温暖な気候と豊かな自然の中で、全国有数の食糧生産基地となっています。
そのような町の最東端にあるのが「通浜地区」です。この地区には約800人が住み、その住民のほとんどが水産業に従事し、この地区にある川南町漁業協同組合の水揚げ場から宮崎県内外に新鮮な魚介類を供給しています。

減り続ける漁業者、進む高齢化
日本における漁業従事者の数は一貫して減少傾向にあります。水産庁のデータによると漁業従事者の数は、昭和63(1988)年から平成30(2018)年までの30年間で61%減少して15万1,701人となっています。その後も漁業従事者の数は減り続けているのが現状です。
本町においてもその減少傾向は同じで、なおかつ組合員の高齢化も顕著に進行しています。川南町漁業協同組合の第44事業年度(令和6年度)業務報告書によると、全組合員に占める60歳以上の割合は約50%(49.6%:正組合員155人中60歳以上が77人)に達しています。

不足する漁業後継者
漁業後継者についても、驚く数値が発表されています。宮崎県の2023漁業センサス速報によると、後継者のいない個人の経営体は全体の9割を占めていると結果が示されています。その数値からも今後持続可能な漁業を継続し、魚食という日本の伝統的な食文化を維持・継承していくことが極めて困難な時代に入ったと言えます。

時代とともに変化する流通のシステム
自然を相手にしている漁業ですが、全国のスーパーに流通させるには、「規格」というものが存在します。消費者が通年を通して求めるものを一度に、しかも大量に運ぼうとすると、大きさや重さ、更には見た目がいいものが良いとされ、安定供給が望まれます。その他は「規格外」として値段が付かなかったり、最悪の場合、破棄されてしまうことも多くあります。(このように扱われる魚を「未利用魚・低利用魚」などと呼びます。)
実は、あまり知られてはいませんが、FAO(国際連合食糧農業機関)が2020年に出した報告書によると、世界の大半の地域では全漁獲量の約30~35%が廃棄されているといいます。
農林水産省が発表した日本における2024年の「漁業・養殖業生産量」は363万4800トンですので、おおよその数字で換算すると約120万トンもの魚が廃棄されている可能性があるというのです。

日本食という文化
日本は、南北に長く、四季が存在します。その季節ごとに日本各地で水揚げされるいわゆる「旬な魚」も異なります。そのような各地で地域に根差した多様な魚たちが日本食の四季豊かな表現の幅を広げています。
また、平成25年12月に和食(日本人の伝統的な食文化)がユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、多くの方が記憶に新しいことだと思います。
しかしながらこの背景には、日本人が和食についてもっと知識を深め、守り、後世に引き継いでいかなくては和食という文化がなくなってしまう危険性も同時にはらんでいるということを理解しておく必要があります。
特に地域に根差した魚は現代の流通規格に当てはめることは難しい場合が多く、いつの間にか「未利用魚・低利用魚」としてその価値を失っているケースも多く存在します。

通浜での常識
川南町の漁港がある通浜一帯の海は昔から宮崎中部の有数の漁場でした。この漁場で40年以上続く常識があります。それは「撒き餌をしないこと」です。通常、漁をする際には魚を寄せて捕獲するため撒き餌をします。その方が一度に大量の魚を捕獲することができ、効率がよく漁獲高が上がるからです。しかしながら通浜一帯の地区はその「撒き餌」を自ら禁止しています。
その理由はシンプルです。漁場を守り、獲りすぎない漁業を維持することで将来に豊かな漁場を残すことを見据えていたからです。背景には、昔この漁場一帯が遊漁による撒き餌で死滅しかかった時期があります。撒き餌を放置すると海の中にアミなどの餌が蓄積し海水は腐敗し、海藻も育たず結果として魚も寄り付くことはありません。そのような未来を危惧した通浜の漁師たちが立ち上がり昭和58年川南町漁業協同組合が高鍋遊漁者組合との間で全国で初めて「撒き餌」を禁止しました。
それ以降、40年以上もその漁法を続け、年号が令和に代わった現代(いま)では通浜での常識となっています。この常識になった漁法こそが通浜で水揚げされる魚の付加価値と言えます。

「通浜」というブランドを全国へ
このような漁法を用い、先見の目をもちながら漁業に真摯に、そしてひたむきに取り組んできた漁業者が水揚げした水産物を、全国の方々に届けるために令和7年8月に「通浜ブランド創出協議会」を設立しました。
この協議会は、川南町、川南町漁業協同組合、川南町商工会、川南町観光協会、川南まちづくり株式会社の5者が、業種の垣根を越え組織した宮崎県内でも例のない団体です。
具体的な取組としては、通浜ブランドの創出、未利用魚の利活用などを検討し、具体的な製品化、業務用での流通なども視野に入れ活動していきます。
40年以上前に漁業者の方々が描いた未来、「持続可能な漁業と豊かな漁村通浜」を後世に残していくために、現代に生きる私たちもその思いと当時の熱量を引き継いでいきたいと考えています。
現在の取り組みの一例
宮崎を代表するリゾート「フェニックス・シーガイア・リゾート」にて2025年5月7日(水)から9月28日(日)までディナーメニューとして川南町漁港で水揚げされた鱶を使用し、フィッシュバーガーを提供しています。

鱶(サメ)は、地元では湯がきやあらいとしてごく普通に食されていた魚です。
しかし現在では、値段のつかない未利用魚として扱われ、漁師の漁具を荒らす厄介者です。値段が付かない魚は、漁業者も経費をかけて市場には出荷しないため、海洋に戻されることがほとんどです。そのためサメの数とサメによる漁具被害は年々増加し、大変深刻な問題となっています。このような未利用魚を、現代の調理技術を用い、美味しく加工し、漁業者から安定した価格で買い取れるような仕組みづくりも行っていきます。その結果、海洋環境の改善と漁具被害の軽減、漁業者の所得向上につなげていきたいと考えています。

目標金額と寄付の使い道
いただいた寄付は以下の目的に使用します。
●通浜ブランド創出協議会の運営費
先進地視察や最新の加工技術を学ぶ機会を作り、現代の漁業のあり方を模索する機会を創出します。
●試作品開発のための原材料購入費
試作品を開発する段階から漁業者から安定価格で未利用魚を買い取り、漁業者が当事者として問題に向き合う仕組みを作ります。
●製品化した際のパッケージ等のデザイン費
全国の消費者の皆様と通浜の漁師の思いが感じられるデザインでコミュニケーションを図りたいと考えています。
●通浜ブランドの広報費
町内、県内はもとより全国の皆様に通浜の常識となっている漁法で水揚げされた魚を知ってもらうためのPR活動を積極的に行っていきます。
●上記に付随する事務経費
【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】
目標金額に達しなかった場合は、本プロジェクトの運用経費に活用させていただきます。
また、目標金額以上の寄付を頂いた場合も、上記の寄付の使い道のほか本プロジェクトの運用経費に活用させていただきます。
寄付者の皆さまへ
このプロジェクトは、「ふるさと納税」の仕組みを活用しています。寄付者の皆さまには、税控除の対象となるほか、川南町の自慢の返礼品もお届けします。
命を懸けて毎日漁に臨む漁業者の明るい未来のために、どうか温かいご支援をお願いいたします。
関係者からのメッセージ

全国の皆様、本町のクラウドファンディングをご覧頂き誠にありがとうございます。川南町長の宮崎 吉敏です。
川南町の水産業におきましては、まぐろ延縄漁業をはじめとする水揚げの実績が顕著である一方、水産資源の減少や魚価・消費の低迷、就業者の高齢化、国際的な漁業制限、さらには災害や原油高騰など、漁業を取り巻く環境は厳しさを増しております。
こうした中、令和7年1月27日に締結しました5者連携協定のもと、水産ブランド創出から未利用魚の活用、地魚の消費拡大、観光との連動、流通体制の構築に至るまで、新たな価値創造に向けた取り組みを進めていくために各関係機関の方々と協力体制を築いて参りました。
「宮崎県川南町の唯一の漁村を後世に残したい」「川南町通浜発の最高の水産物を全国に届けたい」という想いを胸に、この挑戦に取り組んでいます。地域の未来のため、そして漁業者の所得向上を図るため、皆さまからのご支援を心よりお願い申し上げます。
川南町長 宮崎 吉敏

今回のこのプロジェクトは、漁業の問題解決に取組むため業種の垣根を超え、漁協・役場・商工会・観光協会、民間企業が同じ方向を向いて協議会という形で立ち上がりました。川南町漁業協同組合がある通浜という地区で水揚げされる魚は魚種に富み、四季折々の旬の魚が多く水揚げされます。加えて近海漁業は、1本釣り漁師が多く、撒き餌をしないその漁法はそれだけで付加価値となる可能性も多く含んでいます。そういった付加価値となり得る魅力の原石を皆様のお力を借りながら発掘し、丁寧に磨き上げていくことができればと考えています。どうか皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
川南町漁業協同組合 代表理事組合長 俵 伸二
ふるさと納税で
このプロジェクトを応援しよう!
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。
控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
控除上限額かんたんシミュレーション
お礼の品一覧
※このプロジェクトへのご寄付はふるさと納税制度の対象となります。このため、川南町にお住まいの方は、ご寄付をいただくことは可能ですが、お礼の品をお贈りすることができません。何卒ご了承ください。

-
2025年12月15日 09:35
【募集終了】温かいご支援ありがとうございました。
12月10日をもってガバメントクラウドファンディングの寄付募集が終了となり、全国より355名の方々から、合計8,684,000円のご寄附をいただくことができました。
当初設定しておりました目標金額5,000,000円を大きく上回る結果となり、関係者一同大変ありがたく感じております。
皆様、誠にありがとうございました。
今後も、活動の節目には進捗状況を更新したいと考えておりますので、温かく見守っていただけると幸いです。もっと見るまだコメントはありません
コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。
-
2025年10月10日 17:25
【目標金額達成】温かいご支援ありがとうございました!
宮崎県川南町です!
全国の皆様の温かいご支援のおかげで、目標金額を達成することができました!心より感謝申し上げます。
通浜の水産物のブランド化、水産資源を活用した商品開発等の運営資金に大切に活用させていただきます。
しかしながら、このプロジェクトを継続的に運営していくためには、より多くの資金が必要となります。
つきましては、次へのステップとしてネクストゴール「8,000,000円」を設定させていただきました。
引き続き、皆様の温かいご支援・ご協力をお願いします。
もっと見るまだコメントはありません
コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。
宮崎県川南町
日本のひなた、宮崎県の中央部にある川南(かわみなみ)町は農林水産業が盛んな町です。
「日本の食の供給地」
まずは、「肉」。
和牛のオリンピック3連続内閣総理大臣賞受賞の牛、多くのブランドを擁する豚、日本有数のシェアを誇る鶏。
その全てが、味に、質に追及され、大切に育てられています。
また、「魚」は川南町通浜漁港でたくさんの旬の魚が水揚げされ、全国各地に発送されています。
他にも野菜や果物は、全国各地から集まった移住者により、昔から先進的な技術を取り入れ、美味しい特産物を作っています。
肉、魚、野菜すべての食材が光り輝くまち川南。「日本の食の供給地」としてこれからも皆様の食卓を彩ります。
「川南気質~この町の″気質″から生まれる″品質″」
川南町には全国トップクラス、世界基準の美味しい食材がたくさん生産されています。
それらを生産する生産者さんは、こだわりの強い個性のある方ばかり。この背景にはやはり戦後、
全国各地から農業を志す人々が集まり拓かれたことから生まれた″こだわりの強さ″にあります。
このこだわりの強い″町の人″たち自体が川南の魅力で、この魅力を「この町の気質から生まれる品質=川南気質」という言葉で表現しました。

















































































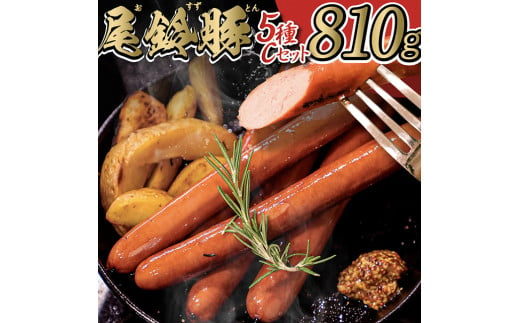
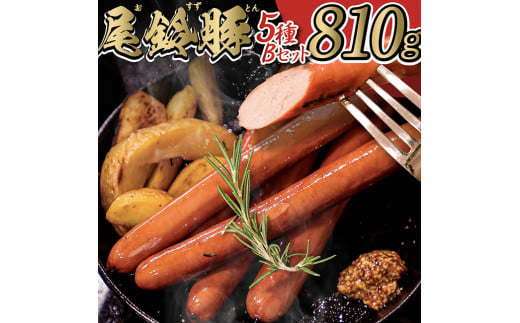














































































































































































































































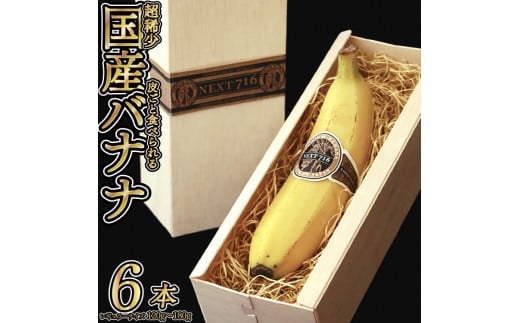
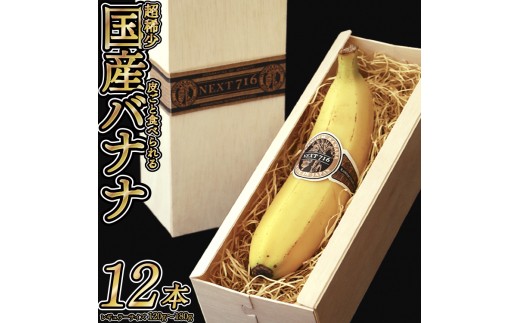





























































































































































































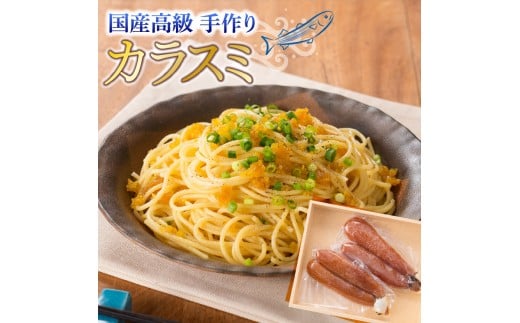











































































































































































































































































































































































































































コメント投稿をありがとうございます!
あなたのその想いが
プロジェクトを動かしています。
投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。
反映まで数日かかることがあります。