7月豪雨で農作物が壊滅。めげずにコメ作りで農業を再生したい
カテゴリー:災害
寄付金額 1,130,000円
目標金額:1,000,000円
- 達成率
- 113%
- 支援人数
- 70人
- 終了まで
- 受付終了
広島県神石高原町(ひろしまけん じんせきこうげんちょう)
寄付募集期間:2018年11月13日~2019年2月28日(108日間)
神石高原町×中ちゃん農園

神石高原町地域創造チャレンジ基金(以下、チャレンジ基金)の支援先の一つである「中ちゃん農園」は、神石高原町の農作物生産拡大を目指して新規起業されたビジネスチャレンジ事業者です。平成30年7月豪雨災害でダメになったしょうが畑に代えて、地元休耕田を復活させる稲作づくりにふるさと起業家としてプロジェクトを開始したいと思います。
※頂きました個人情報は、神石高原町より寄附先の起業家へ提供し、お礼の品の発送等へ活用させていただきます。
平成30年7月豪雨、一瞬にして「しようが畑」が流されてしまった。
小さな町の農業被害の実態を知ってください!!

西日本の各地で甚大な被害をもたらせた「平成30年7月豪雨」。
広島県でも100名以上の死者をだし、数多くの人が避難所での暮らしを余儀なくされ、いまだに県内の鉄道は復旧せずに代替バスによる運行が続いています。
神石高原町では死者はでませんでしたが、600mの高地であるため、土砂崩れなどの被害が甚大で、その数は300か所以上にも及びました。
もとの生活基盤に戻していくには何年もの月日が必要となります。
中山間地の神石高原町において、新しいビジネスチャレンジ事業者を支援する神石高原チャレンジ基金で、サポートしている事業者の一つ「中ちゃん農園」では大きな農作物の被害を受けました。
代表の細川さんは、「しょうが」を新たな神石高原の特産物にしようと取り組み、これまでの2年間で数々の試行錯誤を重ねて、いよいよ3年目の今年、本格的な成育を図るために神石高原町和宗(わそう)地区で400平方メートルのしょうが畑を3月末から整備し、4月20日植え付けするなど着実に生育させてきました。
マルチフィルムでの保護、害虫対策など手間をかけて取り組み、しょうがの芽が順調に生育して一番長いものでは約60cmにまで成長、途中の農業担当者による視察では「細川さんのところが今年は一番生育が良い」と言っていただけるまでになっていました。
7月5日午後からの大雨は7日午前中まで降り続き、しょうが畑に至る3kmほどの道沿いの帝釈川(たいしゃくがわ)も氾濫、土砂崩れも4か所以上も発生して通行不能になりました。
ようやく4日後の11日になって、道路途中の土砂を重機でかき分けて、途中まで分け入り、そこから徒歩で20分ほど歩いてしょうが畑にようやくだとりつきました。

「やっとたどり着いたら、すべてが無くなっていました。まさに開いた口がふさがらなかったです」と細川さんは語ります。
あれだけ順調に育っていたしょうがたち。これまでの2年間、改良を重ねて、ようやく本格的な成育をともくろんでいたのが、70日あまりをかけてようやく育ててきた約60cmの芽がいっさい無くなってしまいました。
細川さんの落胆ぶりは察するに余りあります。本来であれば、8月下旬から9月中旬にかけて刈り取り出荷となり、40-50万円の売上が全て無くなってしまったのです。
立ち止まってばかりはいられないと、前を向いて歩みだした
捨てる神あれば拾う神あり

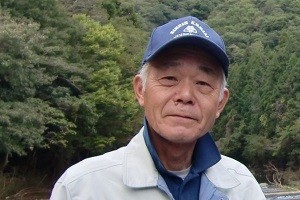
しかしうつむいてばかりいられません、前を向かねばと細川さんは次のチャレンジを決意します。それはちょうど「しょうが畑」の近くで休耕田として眠っていた田んぼを復活させることです。
7000平方メートルにも及ぶ田んぼが眠っているのは忍びないと土地所有されている方が細川さんに「ここで稲作をもう一度しないか」と呼びかけたのでした。休耕田の再生は細川さんにとっても自身の姿と重なります。「やろう」と決意を固めました。
休耕田を復活させていくために
初年度は下準備、田植えができるのは次年度から

休耕田の大きさは約7反(7000平方メートル)あります。これまでの3年間、まったく手入れ管理がされておらず、1メートルも長く伸びた「セイタカアワダチソウ」が生い茂る、まさに草むらといっていい場所になっていました。まずはこれを取り除くための草刈りが必要です。
細川さんは一計を案じて、田植え機の後部を取り外し、トラクターの摩耗した爪を取り付けて応急の「草集め機」を作り、猛暑の続く2日間で刈り取った草を集めて整備しました。次は開墾です。休耕田は土壌が稲作に適した状態になっていないので、深耕化するなど手を入れる必要があります。
また堆肥などを入れてバランスの崩れた土壌改良も必要となってきます。美味しい収穫はまず土づくりから。細川さんの挑戦は続いています。

休耕田の復活が細川さんにとっても挑戦
神石高原の美味しさを届けるためにあきらめない
これからも休耕田を復活させていくためには、農地改良としての土壌の改良や手入れ、イノシシなどの農獣被害対策も必要となってきます。
また実際の水稲も必要となります。これらへの支援を必要としています。
■今後のスケジュール
今後のスケジュール
【2018年】
・8月:事業支援決定
・9月:ふるさと起業家プロジェクト開始/休耕田の農地改良の開始
【2019年】
・2月:プロジェクト修了
・5月:田植え
・7月:草取り
・10月:収穫、順次、返礼品の発送
事業に携わる方の思い
神石高原町 入江 嘉則町長
■人と自然が輝く高原のまち・神石高原町

神石高原町は、「人と自然が輝く高原のまち」として、新たな注目を集めている地域でもあります。
またこれまでも、課題解決型のふるさと納税においても、広島県内で最も多く21000人以上の方からご支援を頂くなど小さな町とは言えないことが続々と広がっています。これは日本中からその地域に対して熱い注目、高い期待の現れだと受け止めております。
しかしながら、豪雨災害によって甚大な被害が引き起こされました。町一丸となってこれに取り組み、生活再建に尽力しているところですが、まだまだ時間がかかります。
その中で被災された事業者自らが窮状を訴えかけ、皆様からのご支援を得て立ちあがっていく姿は「挑戦のまち・神石高原町」としても応援したいし、私たちも元気が出てきます。
どうぞ、今後も引き続き、皆様からのさらなるご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。
神石高原地域創造チャレンジ基金 上山 実代表理事
■新しいビジネスチャレンジを支援しようと意気込んでいます!

地域で話を伺っておりますと、いままでの助成金・補助金だけでなく、この地域における新規起業や新分野への進出については、少なくなく、生活していくために様々な資源や知恵を投入していくことが望まれています。
その点を踏まえて、単に資金提供だけで留まることもなく、経営サポートの面まで踏み込んで取り組みすることで支援対象が支援を受けなければならないところから、自律的な経営ができるように、まさに文字通り「サポート」していく体制で、これから新しいビジネスチャレンジを支援しようと意気込んでおります。
話題をあつめ、期待の場所となっているという町長の紹介の中にもありましたが、ふるさと納税などをみておりましても、地域の中では9400人しかいない町に、その倍以上の全国の方々からご支援をいただき、神石高原町の返礼品が全国に届くようになってきたわけです。
このように、ふるさと納税は地域の課題解決プラットフォームであると共に、地方の事業者を育てて地域経済を活性化させる制度でもあります。
いわば、その気になればどこにいても日本中が市場になった中で、地域にビジネスチャレンジを生み出すエンジンとして、チャレンジ基金を地域の皆さんとともに活用してまいりたいと思います。
あなたのふるさと納税で災害の事業再生支援が行えます
地域で循環するお金を増やし、地域を元気にしていきたい
豪雨災害から立ち上がり、新しいチャレンジをしようとする農業者への支援をお待ちしております。
お礼の品は、来年この田んぼから収穫したお米を、寄附額10,000円で5㎏お礼の品としてお送りさせていただく予定です。
その他、寄附額に応じて何かしらのお礼をしたいと思っています。
-
2019年04月16日 09:00
米栽培(コシヒカリ)スタート!!
「中ちゃん農園」から寄附者の皆様へ報告と御礼のメッセージが届きました。
是非ご覧ください!
↓以下、メッセージ↓
たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございました。
いよいよ、秋の収穫に向けて本格的に米作りがスタートしました。
これから、段階ごとに状況を報告させていただきます。
昨年、約7,000平方メートルの農地を借り受けました。農地は自宅から約3kmの所なので、トラクターで移動して、15分ほどかかります。
昨年秋、1000平方メートルあたり約2tの堆肥を入れました。土壌改良の「ケイ酸加里」を1000平方メートルあたり40kgも入れました。
そして4月に入り、トラクターで耕作しています。写真の通り、自撮りなので、圃場とトラクターの頭しか見えませんが、7000平方メートルを耕作するのにまる2日程度かかりました。
今後は水を入れて、代かき作業に移ります。
今後も私たちの取組を応援いただけますと幸いです。
※写真1:耕作中の農地
※写真2:耕作完了した農地もっと見るまだコメントはありません
コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。
広島県神石高原町
神石高原町は広島県の東部に位置し、中国地方第2位の規模を誇る381.98km2の面積(東京都23区の6割強にあたる)をもつ、森林面積が81%、標高400~500mの高原地域です。清流では毎年至るところでホタルを見ることができるなど、自然豊かな美しい景観をなしています。夏期には昼夜の温度差が大きく、比較的に湿度の少ない爽やかな気候のため、高い糖度で品質の良い高原野菜などの生産や質の良い肉用牛の育成が行われています。




コメント投稿をありがとうございます!
あなたのその想いが
プロジェクトを動かしています。
投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。
反映まで数日かかることがあります。