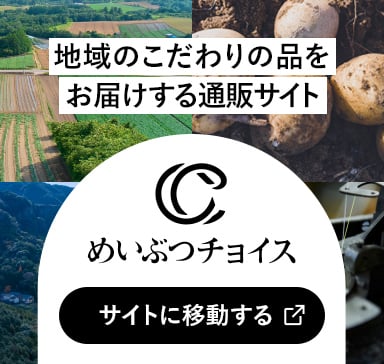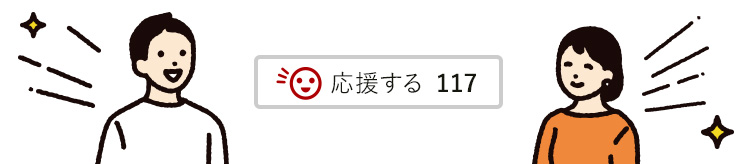2025/09/24 (水) 10:31
人気返礼品をつくる職人《ひと》 ~鹿嶋市ふるさと納税 特別編 Vo.6(前編)~

この記事について
鹿嶋市ふるさと納税は、鹿嶋市にふるさと納税(ご寄附)をいただく皆さんはもちろん、返礼品を用意していただく市内生産•事業者の皆さんのご協力があって成り立っています。
そこで、ふるさと納税ポータルサイトなどでは伝えきれない、生産•事業者の皆さんが「どんなこだわりや想いを抱いて作っているのか」などをご紹介します。
※最下部にもリンクがあります。
1.vol.6 鹿嶋パラダイス・唐澤 秀さん
自然栽培で野菜・お米、それらの加工品を自分たちで作り、自分たちのレストランで提供し、クラフトビールも醸造する「鹿嶋パラダイス」をご存知ですか?

(写真)鹿嶋パラダイスで作り出された商品
ビールやジェラートに加え、鹿島神宮の参道にあるレストラン「パラダイス・ビア・ファクトリー」の料理が好評で、鹿嶋への観光客や、国内のおいしいもの好きの方々からだけでなく、目下、世界からも注目を集めています。
●日本だけでなく世界からも評価されている「パラダイス・ビア」
・2018年 世界五大ビール審査会のひとつ「インターナショナル・ビアカップ」で2018年に見事銀賞を受賞。
・2020年 世界3大ビールコンペ、International Beer Cup Bronze Medal 受賞
・2023年 G7サミット内務・安全担当大臣会合・各国大使館員70名参加の晩餐会選抜コンペにて第一位を獲得し、晩餐会ビールとして採用
・2024年 世界最大のオーガニック展示会「Biofach」に出展 ドイツ、フランスへの輸出を開始

今回は、その「鹿嶋パラダイス」で代表を務める、唐澤 秀さんにお話を伺いました。
自然栽培をはじめたきっかけ、パラダイス・ビアのこだわり、美味しいものを食べることで地球環境をよくすることにつながること・・・・
たっぷり語っていただいたので、前半・後半の2つに分けてインタビューを掲載します。
2.2.「美味しいもの」を追い求め、縁あってたどり着いた鹿嶋
2-1「美味しいものが食べたい」
唐澤さんは静岡県浜松市出身。大学は農学部に進んだ後、茨城県古河市にある農業法人で働き始めました。そしてその後、2008年に鹿嶋市で農業を始めます。
「そもそも、出身が農家というわけではなかったんです。なのになぜ農学部に行ったかというと、「美味しいものが食べたい」っていう基本的な欲求がありました」
じっくりと言葉を選びながら、子供時代に思いをはせる唐澤さん。
「食べることにすごい執着がありました。なので、子供のころは元々、シェフになりたかったんです」
しかし、中学生になって、世界的な食糧危機について書かれた本に出会い、「素材がないならシェフになって料理するどころではないな、『つくる』側に行くしかない」という想いに至りました。
「シェフになる夢をいったん脇において」、唐澤さんは大学卒業後、農業法人で働き始めました。そこでの9年間で、農業の現場を肌で感じながら、自身の「美味しいもの」への探求心をさらに深めていきます。
2-2 美味しいものをつくる「3つの要素」との出会い
唐澤さんは農業法人に勤務する中で、さまざまな経験をして、美味しいものをつくるには3つの要素があると気づきました。
1つめは、「その作物が生まれながらに持っている遺伝子が大切」であるこということ。
「勤務していた法人が、遺伝子的においしくなる品種を作って販売していたこともあって、作物は遺伝子によって、味が全然違うということを実感しました。昔からずっと作られている品種には理由があると思います。」
2つめは、「最初から最後まで一貫して行う」ということ。
「農業法人で働いていた時、毎年、2週間お休みを取って、世界でナンバーワンの評価を受けている各国の生産者に会いに行ったんです。1年に1か国ずつ回りました。そうした農家には共通点がありました。
それは、全部自分たちでやる、ということでした」
通常、農業は分業で成り立っています。たとえば、ハムなどの食肉加工であれば、餌を作る会社からエサを買い、別で豚を育てるところがあって、と殺や解体も依頼します。解体されたあと部位に分かれた後の肉を買い取って、自分たちは塩漬けにするだけ、というような流れです。
「パルミジャーノ・レッジャーノやモッツアレラ、イベリコ豚を生産しているところを訪ねて行ったのですが、豚とか牛とかの餌を作るところから始まり、それで育てる。母豚や子豚の管理をする。イベリコ豚だったら最後の半年はどんぐりの林を放たないといけないので、その林も所有し管理する。最後の と殺・解体、塩漬け・熟成についても当然自分たちの会社で全部行うんです」
世界ナンバーワンの生産者たちは、外から何かを仕入れて、ものを作るというようなことは、ほぼやっていませんでした。
「全部、自分たちのコントロール下においてやっていることを知りました。
それを知って、僕もそれを、日本でやりたいというふうに感じました。そうしたら、最高のものができるのではないかと」
3つめは「自然栽培」。
「木村秋則さんというリンゴ農家の方がいらっしゃって、その方のエピソードは『奇跡のリンゴ』」という、本や映画にもなっています。会社員時代に、その木村さんにお会いすることがあって、そこで『自然栽培」』を知りました」
自然栽培農法とは、農薬や化学肥料はもちろん、有機・オーガニック肥料、家畜の糞などの堆肥さえも一切用いない農法。種を蒔いた後に与えるのは太陽の光と水、畑にある土だけです。
「自然栽培でつくられたもので、初めて食べたものは小松菜だったんですけど、ものすごい…格段の美味しさというか、ちょっと身震いするぐらい感動したんですよ。それは、甘いとか濃いとこじゃなくて、食べたときに、体が本当に喜ぶのはわかるんです。「これ。待ってました。」って」

「匂い」ではなく「香り」という表現がぴったりで、味も噛めば噛むほど滋味深い味が伝わってきたそうです。
「たとえば、お米を自然栽培で作ってみたところ、本来、糠はこういうにおい、玄米はこういう風なにおいなんて思ってるものが、実は玄米とか糠の部分の匂いじゃなくて、肥料とか堆肥の匂いだったっていうことが分かりました。」
「作物のその遺伝子に組み込まれた、本来の野菜の味とか香りが、ほぼほぼ、何の影響も、後天的な影響を受けずに生産されたものが自然栽培になります。」

自然栽培で育つチンゲン菜(Paradise Beer FactoryのInstagramより)
自然栽培の魅力にとりつかれた唐澤さんは、仕事をしながら、自分で畑を借りて実際に自然栽培を始めてみることにしました。
たくさんの量は収穫できませんでしたが、自分で作ってできた作物を食べてみたら「すっごい美味しかった。ああ、もう、ほんとに、やっぱすげえな」と感嘆の声が漏れ出たとか。
知り合いの経験豊富なバイヤーさんたちに食べさせてみても、誰もがおいしさに感激して「売ってほしい」というほどでした。
「美味しいものをつくる3つの要素」を知った唐澤さん。
自然栽培によって素材づくりから一貫してやっていけるような場所を探したい、となった時に、たまたま鹿嶋市で会社を経営していて、自然栽培でお米作りを始めていた方と出会いました。
その方による畑や家の手配などの助けもあり、唐澤さんは鹿嶋市で自然栽培を始めることになりました。2008年6月のことでした。
3.自然栽培に必要なふたつの作物、そしてパラダイス・ビア
鹿嶋の地で「鹿嶋パラダイス」を立ち上げた唐澤さん。
日本でやりたかった「一貫して素材作りからやる」ということは決めてはいたものの、まずは少しずついろんな品目を試しに栽培して、どんな味になるか調べたり、いい遺伝子の作物を見つけるために吟味していました。
そして、2012年、鹿島神宮参道に自然栽培素材を使ったレストランをオープン。ビール醸造の修行をはじめます。
3-1 「大豆で肥料をやり、麦で耕す」
現在、鹿嶋パラダイスの代表的な商品となっている「パラダイス・ビア」を作ろうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。

(写真)パラダイス・ビア セゾン「弥栄楽園」
「実は、視点が逆なんですよ。自然栽培をやるうえでの必須の素材に麦があったということなんです」と唐澤さん。

「自然栽培って、肥料や堆肥を何もやらないって言っていますが、何もあげない代わりにポイントとなることがあります。それは土です。」
「昔から言われている言葉に、「大豆で肥料をやり、麦で耕す」というものがあります。
大豆と麦を、その畑で育てると、肥料や堆肥をやらなくても育つ畑になるんです」
「大豆で肥料をやり、麦で耕す」のしくみ
大豆の根には根粒菌(こんりゅうきん)という微生物がいて、作物の生育に欠かせない栄養分である窒素を供給します。そして、麦は深く根を張ることで土を柔らかくします。
「つまり、自然栽培をやるには、土づくりのために、麦と大豆をどうしても、栽培しないといけないんです。」
ただし、そのまま出荷しても、値段の安い麦では、農家としては経営が成り立ちません。そこで唐澤さんは、麦をビールに加工して、「価値を上げる」ことにしました。

麦だけでなく大豆ももちろん、味噌や豆腐・豆乳に加工したり、その豆乳を使ったジェラートをつくって販売しています。こちらも店舗で大人気。味噌とジェラートは鹿嶋市ふるさと納税の返礼品にもございます。

そもそもはビールはそんなに好きではなかったと笑いながら語る唐澤さんですが、2006年にドイツワールドカップが開催されたとき、ちょうどドイツにいて、地ビールを飲んでみる機会があったそうです。
その時に、地ビールのおいしさに感動し、「こういう地ビールなら普段から飲みたい」と感じたそうです。
そして、鹿嶋パラダイスでつくったお米が原料の「パラダイ酒」を醸造してもらっている千葉の寺田本家さんにビールづくりを依頼したところ、「唐澤さんが作ってみたら」と逆に言われたこともきっかけのひとつ。
ビール醸造は一般的には大きな機材が必要になりますが、小規模なビール醸造所(マイクロブルワリー)としてならばビールづくりを始められることがわかり、挑戦することにしました。
3-2 失敗から改めて気づかされた「自然栽培のおいしさ」
2016年にビールの醸造免許を取り、その1年目のこと。
ビール用に自然栽培でつくった麦を収穫後、少し時間を置いてしまったところ、気温もせいもあって全部ダメになってしまいました。その量、約1.5トン。言うならば1年目の収穫量の全部でした。
ビールの醸造免許を取得したら、免許取得後の3年間は最低製造数量をクリアしなければなりません。その量を下回ると、免許はく奪になってしまうのです。
唐澤さんたちは、とにかく作るしかないと、その年は海外から麦を買ってビールを作りました。
2年目は自然栽培で麦が無事に収穫でき、ビール用の麦芽にすることができました。
1年目とまったく同じ手順で、同じ種類のビールを作ります。違うのは自分たちがつくった麦が原料であるということだけ。

鹿嶋パラダイスで育った麦(Paradise Beer FactoryのInstagramより)
自分たちで作った麦でできた2年目のビールと、1年目に作った輸入の麦芽を使用したビールと飲み比べをしてみることにしました。
ビールの醸造には、麦汁を作って絞って、それを沸騰させ、煮沸して90分。発酵タンクの中に入れて、イースト入れて、発酵させて、ホップを入れる。さらに2ヶ月ぐらい熟成させることが必要で、多くの加工が入ります。
「こんなに加工が入るのに、麦ひとつでどこまで味が変わるんだろう?と思っていました。『自然栽培で麦を自分たちで作る』ということは、ストーリー的には替えがたい付加価値ではあるのですが、実際、味でそんな変わるのか?と懐疑的でした。」
その試飲を、スタッフ全員で行いました。
その時のことを、唐澤さんは思い出しながら声を弾ませます。
「みんなが、目を丸くして、ビビるぐらい違ったんです。『全く違う』って」

「ビールの味自体というか、麦汁というか、ベースの味が全然違うんですよね。雑味みたいなのが一切ないっていうか、すごいピュア。」
「自然栽培全体に言えるんですけど、『えぐみ』も含めて、いやなところっていうか、違和感を感じることが、もうほとんど感じられない。もう飲み比べたら歴然と違うんですよ」
もともと、飲み比べる機会がなかったから、しかも自然栽培でつくられたビールが世に存在しないから知らないだけだったけれど、ここまで味が違うということが明らかになり「自然栽培でビールを作って良かった」と思ったと語る唐澤さん。
「「野菜だけでなく、ビールにおいても自然栽培でつくればすごくおいしくなる」という、確信に変わった瞬間だったんです。」

パラダイス・ビアのテイストは、ベルジャンホワイトエール/セッションIPA/IPA/ペールエール/ダークエール/酒粕ホワイトエール/ラガー/セゾンの8種類。
★「パラダイス・ビア」の特徴
・仕込み水には、鹿島神宮の御神水を使用。自然栽培農家としてビール原料である麦やオレンジピール、コリアンダーシード、山椒なども自分たちの畑で生産しています。
次回予告
「美味しいものを食べることで、環境を守り、地球を良くする」───そんなこと、実現できる?
「美味しいものを食べることで、環境を守り、地球を良くする」…そんな楽園のようなことが、実現できる?
後編では、私たちの「美味しいものを食べたくて、選ぶ」という行為が、ただの個人的な満足を超えて、地球をよくすることに貢献できる未来について、唐澤さんに語っていただきます。
店舗情報

Paradise Beer Factory
所在地:茨城県鹿嶋市宮中1-5-1
営業日:毎週木・金・土・日曜日(祝日の場合ランチタイムのみ営業、翌日休業。その他、農作業のため臨時休業あり)
ランチ:11:30~16:00/Beer Bar:火~土曜日 17:30〜22:00
ショップ:11:30〜21:00(時間帯によりスタッフが対応できない場合があります)
【鹿嶋市ふるさと納税の返礼品ページ】
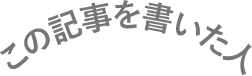
しかふる3号
鹿嶋市ふるさと納税の担当者です。生産者の皆さんの知られざる情熱やこだわりをご紹介します。