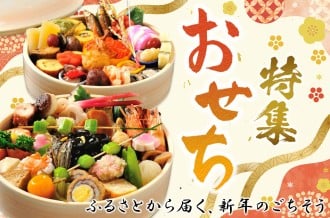お問い合わせ先
内容によりお問い合わせ先が異なる場合がございます。
申し込み後の内容変更・寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書
内容によりお問い合わせ先が異なる場合がございます。
申し込み後の内容変更・寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書
《お問合せについて》
お電話及びメールは、LR株式会社がご対応いたします。
■お問い合わせ先
TEL:0570-012658
MAIL:uji@lrinc.jp
営業時間:平日9時~17時
※土日祝祭日はお休みをいただきます。メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。
【寄付金受領証明書・ワンストップ特例申請書に関しては】
宇治市役所政策戦略課 TEL:0774-20-8698
ふるさとチョイスの使い方
ふるさとチョイスのよくある質問でご案内しています
アプリでは使用できない機能になります。ブラウザ版からお試しください。
年末年始の配送
ワンストップ特例申請書の郵送
アプリでは使用できない機能になります。ブラウザ版からお試しください。
自治体メルマガに登録
このメールアドレスを、自治体メルマガに登録しますか?
自治体メルマガを解除
このメールアドレスを、自治体メルマガから解除しますか?
- この自治体のお礼の品一覧へ
-
お礼の品なしの寄付
お礼の品なしの寄付
はじめての方へ
-
ふるさと納税とは
誰もが簡単にふるさと納税できるよう、寄付の仕方や税金控除など仕組みを紹介しています。
-
控除金額シミュレーション
ふるさと納税を実質2,000円でするために、あなたの控除上限額を調べてみましょう。
-
ふるさとチョイスの特長
76万点以上のお礼の品を紹介する「掲載数No.1※」のふるさと納税総合サイトです。
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2024年10月28日時点 大手ふるさと納税ポータルサイト4社対象の市場調査 -
よくある質問
ふるさと納税制度や寄付の方法、さらにサイトの利用方法まで、あなたの疑問を解決します。
-
サイトの使い方でお困りの方
サイトの操作手順や手続きについて、寄付の流れに沿ってご案内します。
宇治市からのご案内
| 2023/11/16(木) 11:41 |
年末年始の配送とコールセンターのご対応について
≪配送について≫ ・お礼の品の送付までにお時間を頂く場合や着日指定等のご希望にそえない場合がございます。 ・長期不在等によりお礼の品を受け取れなかった場合などの、寄附者様のご都合による再送等の対応は出来かねますので予めご了承ください。 ≪お問い合わせについて≫ ・LR株式会社 メール:uji@lrinc.jp 電話番号:0570-012658 (平日9時~17時)祝祭日・特定休業期間を除く |
|---|
宇治市の人気ランキング
※ 人気ランキングに表示されている情報は集計時のものになります。
特集記事
京都府宇治市の情報を
メールで受け取ってみませんか?

旬な情報やお知らせを、メールでいち早くお届けします!
旬な情報やお知らせを、
いち早くお届けします!
選べる使い道
-

源氏物語のまちづくり
宇治市は、平安時代には貴族の別業の地として栄え、日本の誇る世界最古の長編小説『源氏物語』の最後を飾る宇治十帖の主要な舞台です。この『源氏物語』をまちづくりのテーマとしてさまざまな事業に取り組んでいます。
観光と生涯学習の拠点である「源氏物語ミュージアム」では、常設展示のほか、平安時代の貴族社会や文化、『源氏物語』の成立などを描いたオリジナルアニメの上映や『源氏物語』について学ぶ講座の開催などを行っています。
また、毎年秋には、イベント「源氏ろまん」を開催し、市民のアイデアから誕生した「紫式部文学賞」「紫式部市民文化賞」の贈呈式、平安時代に栄えた田楽の復活をテーマとした「宇治田楽まつり」、『源氏物語』の古跡を巡る「宇治十帖スタンプラリー」などを実施しています。 -

貴重な歴史的文化的遺産の保護と活用
宇治市は、ユネスコの世界遺産に登録されている「平等院」、「宇治上神社」をはじめとする数々の史跡に恵まれています。 中でも「史跡宇治川太閤堤」は、平成19年に発見された治水遺跡で、遺跡の保存と併せて歴史公園の整備や隣接地には観光拠点も整備するなど、貴重な歴史的文化的遺産の保護と活用を行っています。
-

宇治茶の普及
宇治市では「宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例」を制定し、宇治茶の普及に向けた事業に取り組むとともに、宇治茶を気軽に味わっていただける茶室「対鳳庵」を運営しています。さらに、宇治茶ブランドの向上に向けて、京都府やお茶の京都DMOなどの関係団体と広域的な取組を進めています。
2015年には、京都府南部8市町村に所在する宇治茶の歴史と文化、美しい茶畑の景観を通じたストーリーが「日本茶800年の歴史散歩」として日本遺産第1号に認定されました。宇治市内においては、「黄檗山萬福寺」「中宇治の街並み」、「白川地区の茶畑」など19件が構成文化財となっています。 -

観光振興
宇治市は、ユネスコの世界遺産に登録されている「平等院」、「宇治上神社」をはじめ、日本の三禅宗の1つである黄檗宗の大本山萬福寺、つつじやあじさい等のお寺として名高い三室戸寺、その他にも宇治神社や興聖寺など多数の寺社仏閣があり、国内外から多くの観光客に来ていただいています。
観光客のみなさんが安全・快適に観光できる環境の整備や歩いて楽しめるまちづくりを推進しています。また、さらに多くの方に宇治市を訪れていただけるよう、宇治市の魅力をあらゆる手段や機会を通じて、国内外に効果的に情報発信していきます。 -

未来を担う子どもたちを育む事業
宇治市の子育て支援は、子育てを担う父母等の「家庭」のみではなく、「子ども」自身の利益を最優先に考えるとともに、行政だけではなく、「地域」とともに取り組んでいます。子どもの健やかな成長・発達への支援、安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援、地域で子育て支援ができる環境づくり、仕事と子育てを両立できる環境づくり、配慮を必要とする家庭へのきめ細やかな取組を推進しています。
-

その他まちづくりに関する事業
アンケートフォームの記載欄に、具体的な使い道をご記入ください。
-

指定はしません
市政全般に対する寄附として、市において使い道を選択させていただきます。