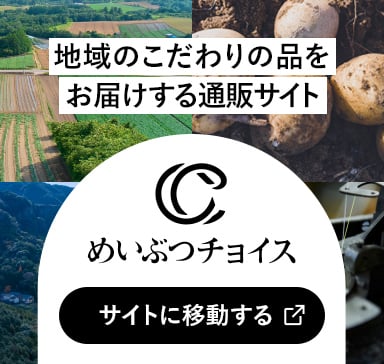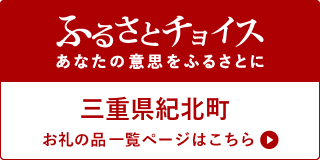小さな湖育ちの幻と呼ばれる「渡利かき」
「渡利かき」を知っていますか? 三重県紀北町の小さな湖”白石湖”で獲れる牡蠣です。わずか周囲5㎞しかないため、生産量も限られており、”幻の牡蠣”という人もいるほどです。 白石湖は淡水と海水が混ざり合う汽水湖。塩分濃度が極限まで抑えられ、牡蠣独特の生臭さが少ないのが特徴です。
わずか周囲5㎞の白石湖
大台山系からの山の豊かな養分と熊野灘の海の恵みが混ざり合う汽水湖です。
この小さな湖で、渡利かきを養殖しています。

白石湖の全体像です。左から船津川が流れ込み、大台山系に囲まれ山の恵みもたくさん。透明度が高いことで知られる奇跡の川”銚子川”と合流し、熊野灘へと繋がっています。

厳しい環境で育つ「渡利かき」とは?
日本でも有数の多雨地帯。通常海で育つ牡蠣が、川からの水や雨水がどんどん入り込む厳しい環境に耐えながら、じっと我慢して育つことにより牡蠣独特の臭みが少ないおいしい牡蠣に成長します。
他と比べて少し小ぶりで、少し黄色っぽくみえるのは、厳しい環境に耐える中で、旨味成分をギュッと凝縮するからだとか。周囲5㎞の白石湖でしか生産されていないため、生産量が極めて少なく、幻のかきと呼ばれることもあります。

産まれてからずっと白石湖
筏式養殖で育てられる渡利かき。種から白石湖で天然採苗し、白石湖で育てられます。子どもの牡蠣は真水に弱いため、雨が降り真水が増えると筏に縛り付けたロープの長さを一本一本変え、なるべく海水の位置にくるように調節しています。雨の多い地域特有の手間暇をかけて大事に育られるからこそ、旨味をたくさん詰めこんだ牡蠣に成長します。他の場所で産まれた稚貝を白石湖で養殖しようとしても育たないくらい汽水湖という厳しい環境で耐えられる牡蠣なのです。


地元では生牡蠣より「焼き」
生食用ですが、加熱して食べるのも旨味が増しておすすめ!
牡蠣の旨味をストレートに味わえる「焼き牡蠣」

味噌との相性はバッチリ!

イチオシは「カキフライ」!

甘辛く炊いて酢飯と合わせた郷土寿司「渡利かき寿司」。
辛子で食べるのが地元流。

この時期にしか食べられない白石湖産の「渡利かき」。 ぜひ一度食べてみてください。