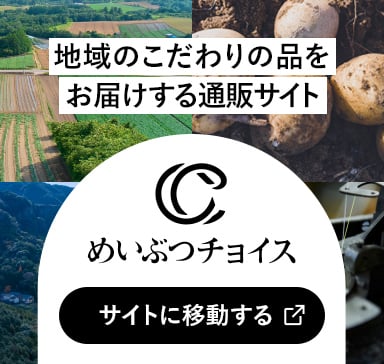歴史好きの方にもおすすめ! 100年の時を超えた「クラフトサケ」特集
今からおよそ250年前の1772年、岩手県紫波町にて平井六右衛門は酒造りを始めました。これは岩手県最古の歴史を誇ります。 時は流れ1920年代に盛岡市へ移転し、その後100年眠っていた紫波町平井邸の造り蔵。クラフトサケとしてよみがえった平六醸造(ひらろくじょうぞう)の返礼品をご紹介します。
【平六醸造】 平井 佑樹さん

1991年、岩手県盛岡市出身。岩手県最古の歴史を持つ「菊の司酒造」を営む両親のもとに長男として誕生。大学卒業後、実家の酒蔵でお酒に関わるすべての業務に取り組んできました。より広く全国、世界の日本酒愛飲家に楽しんでいただけるよう品質向上に取り組み、国税局鑑評会に加えてIWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)等の市販酒コンペティションにおいても上位受賞する等、全力を尽くしてきました。しかしながら、2021年3月「菊の司酒造」は経営難のため事業譲渡。2022年1月に同社を退職。ルーツのあった平井邸で活動を始め、2023年1月株式会社平六醸造を創業。
紫波町日詰(ひづめ)商店街のシンボル 平井邸とは?


このお酒を語るには、まずは日詰(ひづめ)商店街にある平井邸を説明しなければなりません。
かつて北上川舟運の要衝として栄えた郡山駅(※1)に、豪商の平六商店(現在の菊の司酒造)の第12代平井六右衛門が約3年の歳月をかけて1921(大正10)年に完成し、内閣総理大臣に就任した原敬を接待するために新築された屋敷です。岩手県内でも数少ない大正の邸宅で、2016年国指定重要文化財に指定されました。
(※1)参勤交替の往来で奥州街道の宿駅として繁栄し、北上川水運による物流拠点となって発展した、この地域の象徴でもあります。
平井邸と酒造り 岩手県最古の酒蔵

平井家が酒造りを始めたのは、平井邸完成よりもおよそ250年前の江戸時代中期の1772年。6代目・平井六右衛門の代のことでした。大正期には屋号を「平六商店」とし、清酒や醤油、味噌の醸造・販売をおこなってきました。1920年代には販路拡大のため盛岡市に移転し、1968(昭和43)年に「菊の司酒造」へ名前を変えました。
この平井邸にあった造り蔵は、盛岡市へ移転してから約100年、その役目を終え眠り続けていました。
100年の歴史よ、よみがえれ 「平六醸造」


2022年、酒造りから離れた平井さんは、平井邸で活動を始めました。人々が交流できる場所として、平井邸の一般開放を行い、イベントの開催等も始めました。並行して酒米作りも始め「自分の造ったお米でお酒を造ってみたい」という情熱が芽生えていました。
そして、平井邸に遺されていた造り蔵がよみがえる時がきました。造り蔵に息をひそめ、およそ一世紀もの間眠り続けてきた酵母・アカツキ。2023年、醸造所工事前に採取した200本以上のサンプルから奇跡的に発見されました。日本酒から新たな時代を歩む、クラフトサケへ形を変えてよみがえった「平六醸造」。醸造所の復活によってその時は再び動き始めました。
おすすめ返礼品
平六醸造 Re:vive Origin アカツキ 720ml (EA001)
40,000円以上の寄付でもらえる
やわらかく搾り落された滴は、ありのままの柔らかな光沢を放つ。和梨や甜瓜を想わせる果実香と穀物のようなニュアンスが調和し、どこか懐かしくも、モダンな洗練された香りが感じられます。口になめらかに滑り込むと、白桃のような甘味を膨らませながら、涼しげな酸味と小気味よい苦味が交互に弾けます。終盤に掛けてそれらはボリュームを増し、ノスタルジックな余韻を残しながら清楚に流れ消えていきます。
平井邸の現在

紫波の人々に守られてきた家なのだから、一族だけではなく、“みんなの家”として活用したい。
日本の歴史ある暮らしや季節の移ろいに触れながら人々が交流できる場所として、朝市の憩いの場や地元のカフェや飲食店、アーティストなどを招いてイベント開催等。ヨガ教室や古本市など、地域のコミュニティ活動の場として活用されるほか、フォトウェディングのロケーションとしても重宝されています。
「大切にしているのは、この家で“過ごしてもらう”こと。いわゆる観光地として、ただ眺めて帰るのではなく、たくさんの人に過ごしてもらって、そこでご縁やコミュニケーションが生まれるということが、この家をよみがえらせるということなんだと思っています」と平井さんは語ります。