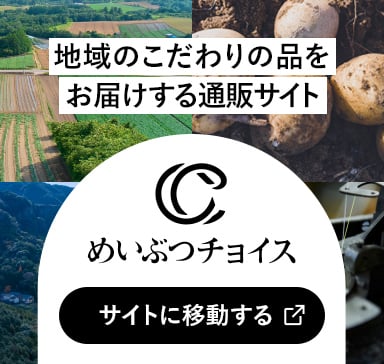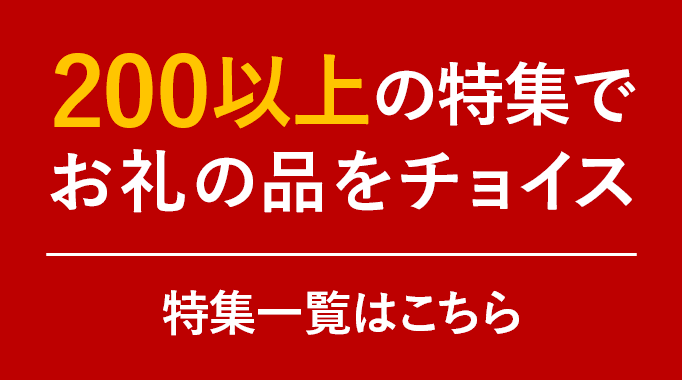【地域活性化】少子高齢化の進む町が長期的視点で対応
少子高齢化が進んでいた、佐賀県太良町。この町では、農業振興として農地整備やシニア活用を進める一方、ふるさと納税を活用することで、町に好循環が生まれています。

少子高齢化に危機感を持ち、長期スパンで戦略人口を想定
佐賀県の西南端に位置する太良町は、古くから農林水産物に富み、土地も肥沃で食料が豊かなことで知られています。中でも、多良岳を頂点になだらかな傾斜の地形を生かしたミカンの栽培が盛んで、県内有数の産地でした。しかし、時代の変化とともに、ミカンの消費の減少や価格低下などにより、ミカン産業は低迷。それに加えて、少子高齢化による「後継者不足」が深刻な問題となっています。
人口減少率、高齢化率が県内ワースト1、2を争うほど高く、今のペースでいくと町の人口は30年後には半減。2060年には3,000人台になることが見込まれており、このままでは町も第一次産業もどんどん先細っていってしまいます。
これらのことを踏まえ、町では長期的視点からこの問題に取り組むことを決め、目標とすべき戦略人口を設定。まずは高齢化で先細りとなっている第一次産業の底上げに着手しました。とりわけ主要産業のミカン農家は高齢世帯が多く、中山間地域にあるミカン畑での作業は重労働で効率が悪いことから、年々減少していました。そこで2011年から「農地基盤整備事業」を始めました。「急傾斜地をなだらかに整備し、収穫しやすい畑に作り変えて、高齢になっても働けるように改良してきました。従来、国や県の予算で行われることが多いのですが、それを待っていては間に合わないので、町独自で制度を作り、スタートさせました」(岩島正昭町長)
また、農業従事者の高齢化や減少を食い止め、「持続可能な力強い農業」を実現するため、若い農業者の育成・生産技術の習得や経営継承を目的に、親元就農者や新規就農者に対する給付金を開始しました。しかし、これらの事業や制度を利用するのは、一握りの事業者だけでした。この流れを大きく変えたのが、ふるさと納税です。
農地基盤整備事業とは?
農地基盤整備事業は、太良町の主要産業の一つである農業が、従事者の高齢化や担い手不足などにより衰退していることを受け、2011年より町が独自に開始した事業です。農業従事者からの申請により、町の建設課が1軒1軒ヒアリングして現状を把握し、整備費用の8割を町が補助するというもの。整備により荒廃地防止、農作業の省力化・効率化が図れ、農業振興を推進。昨年度までに132件、累計補助額約1億8840万円の利用がありました。
「ミカン王国」再建へ はじまりは4事業者のみ

町がふるさと納税にお礼の品を導入したのは、2015年9月から。「他自治体の動きを見て、一定の効果を感じていたので、導入に踏み切りました。自分が小さい頃はミカン栽培が盛んだったので、個人的にも『いつか“ミカン王国・太良町”を再建したい』という思いがありました。でも、最初の募集に応募したのはたった4事業者のみ。そこからのスタートでした」と、財政課の織田渉良さんは振り返ります。
その最初の募集に応募したのが、町内でミカンを栽培する農業法人かねひろの川崎豊洋さんでした。
「面白そうだからやってみようと思いました。農地基盤整備事業を利用して畑も拡大していたので、自慢の『黒酢みかん』を知ってもらうきっかけになれば、と思ったんです」と川崎さん。
いざ始まってみると、またたく間にその味のよさが口コミで評判を呼び、予定数をはるかに超える申し込みがありました。さらに出品を重ねた結果、「ふるさとチョイス」お礼の品・果物類部門全国1位を3年連続で獲得。それまで赤字だった経営も黒字に転換しました。手ごたえをつかんだ川崎さんは、町の基盤整備事業をさらに利用して畑を再拡大し、着手していた新品種の生産やネット通販、さらにはジュースやゼリーなどの六次産業化にも本腰を入れることができました。
「お礼の品の事業は受注生産のように見通しが立てやすいので、計画的に事業や雇用を拡大する決断ができました。おかげでようやく町にも税金が納められるようになりました」(川崎さん)
人気お礼の品ミカンの栽培を支えるのはベテラン女性たち

実は、この快進撃を支えたのは、地元のシニア層の労働力でした。かねひろではこの道30~40年という70代、80代のベテラン女性13人が、ミカンの摘果や収穫の作業を担っています。改良前の急傾斜地での作業は身体的負担も多く、歳を重ねると辞める人も少なくありませんでした。しかし、基盤整備事業によって急傾斜地が整備されたことで、シニア層が働きやすくなり、その雇用につながっているのです。
「畑がなだらかになったので、とても作業しやすくなりました。うちでもミカンを作っていますが、ここのミカンが一番甘いですね(笑)」と話すのは、最高齢の川口コソエさん(86歳)。
今や作業することは生活の一部になっていて、仲間と集まっておしゃべりできるのも、楽しみの一つだといいます。 さらに、かねひろ以外のミカン農家もふるさと納税のお礼の品事業に参入。今では21のミカン農家がお礼の品を出品し、互いに切磋琢磨しています。
寄付額が爆発的に増加して事業者の意識も変化
「ふるさと納税を始めて一番変わったのは農家の皆さんです。最近は皆さんから『これとこれを組み合わせては?』とか『パッケージをこう変えたらどうだろう』とか、いろいろ提案してくれるので、ありがたいですね」(織田さん)
意識が変わっただけでなく、「もっと畑を広げよう」と農地改良に取り組む事業者も増えてきました。そして、親元就農者や新規就農者も増えており、その証拠に給付金の申請者数は確実に増加中です。
「太良のミカン産業を盛り返そう」という流れを、町はさらに特産品のブランド力強化や新品種研究などで後押しします。これらの取り組みにはふるさと納税の寄付金が活用されています。
2016年以降、太良町のお礼の品は徐々に充実。現在ではミカン農家だけでなく、55事業者による佐賀牛や竹崎カニ、野菜、能面など、400品以上が並びます。導入前の2014年に約64万円だったふるさと納税額は、導入した年に約2億2,400万円、翌年には約7億4,200万円を計上。自主財源約25億円の太良町にとってこれは大きな収入源となっています。
開始当時は1人だったふるさと納税担当も、今では臨時職員を含め4人に増えました。寄付金は農業振興のほか、戦略人口達成に向けて小学校入学時と中学卒業時の祝い金支給など、子育て支援にも充てられています。
ふるさと納税を活用した結果、それが起爆剤となって農業振興、シニアの活用、税収増加など、いい循環が生まれてきた太良町。「ミカン王国」再建へ、一歩ずつ前に進んでいます。
【生産者インタビュー】農業法人 有限会社かねひろ社長 川崎豊洋さん

私は父からミカン畑を引き継いだ後、各地の生産者に教えを請い、黒酢アミノ酸を利用した栽培と出合いました。黒酢エキスを散布することにより、アミノ酸の効果で甘さが増したミカンが収穫できます。それを「かねひろの黒酢みかん」としてブランド化しました。 生産性を高めるため、2012年から町の農地基盤整備事業を活用し、畑の平地化に取り組みました。通販や六次産業化の事業にも着手しましたが、販路を広げるのは並大抵ではありませんでした。そんなとき町がお礼の品を募集すると知り、早速応募してミカンの提供を始めました。すると、すぐに評判を呼び、補充しても生産が追いつかない状態が続き、初年度だけで3000万円以上の売り上げとなりました。
そこで、再び整備事業を活用し、1300万円の補助を受けて畑を広げ、生産や雇用を拡大。さらにジャバラのスカッシュやミカンのゼリーなどの加工、ネット通販にも本腰を入れました。お礼の品の事業は生産のメドが立てやすく、赤字が続いていた会社の経営も劇的に改善しました。昨年度は法人として約1200万円の税金を納め、そのうち約72万円を市町村民税として町に恩返しすることもできました。今後は若手就農者を呼び込んで、次世代の生産者を増やすことも目指しています。