アプリでは使用できない機能になります。ブラウザ版からお試しください。
年末年始の配送
ワンストップ特例申請書の郵送
アプリでは使用できない機能になります。ブラウザ版からお試しください。
自治体メルマガに登録
このメールアドレスを、自治体メルマガに登録しますか?
自治体メルマガを解除
このメールアドレスを、自治体メルマガから解除しますか?
- この自治体のお礼の品一覧へ
-
お礼の品なしの寄付
お礼の品なしの寄付
はじめての方へ
-
ふるさと納税とは
誰もが簡単にふるさと納税できるよう、寄付の仕方や税金控除など仕組みを紹介しています。
-
控除金額シミュレーション
ふるさと納税を実質2,000円でするために、あなたの控除上限額を調べてみましょう。
-
ふるさとチョイスの特長
76万点以上のお礼の品を紹介する「掲載数No.1※」のふるさと納税総合サイトです。
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2024年10月28日時点 大手ふるさと納税ポータルサイト4社対象の市場調査 -
よくある質問
ふるさと納税制度や寄付の方法、さらにサイトの利用方法まで、あなたの疑問を解決します。
-
サイトの使い方でお困りの方
サイトの操作手順や手続きについて、寄付の流れに沿ってご案内します。
古河市のすべての寄付金の活用報告
保育ニーズの多様化に対応するため、民間保育施設に補助金を交付し、保育の質向上を目指しています。
2025/11/06(木) 12:00
保護者の働き方や生活様式の多様化に対応した延長保育や一時預かりなどの事業を行う民間保育事業者や、支援が必要な子どもを受け入れるために配置基準を超えて保育士を雇用する民間保育事業者、また保育業務の効率化のためにICTを活用する民間保育事業者に対し財政支援を実施しました。
保育士の確保が課題となっているなかで、ICTによる業務の効率化等により、保育士の負担を軽減し、働きやすい環境づくりにつながり、保育士の就業継続、離職防止、新規雇用の促進が図られ、よりよい保育の提供を行うことが出来ました。
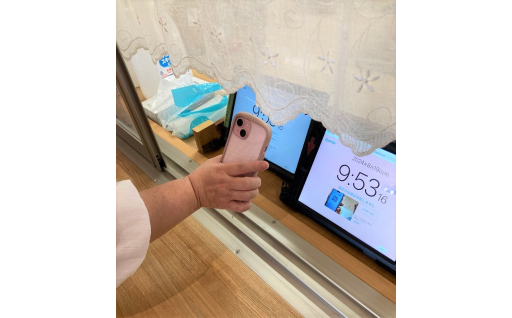
市内の移動性を高め、燃料費・修理費など、コミュニティバスの運行を維持するための費用として活用しました。
2025/11/06(木) 11:48
コミュニティバス(ぐるりん号)は、どなたでも気軽に利用でき、日常生活を快適に過ごせる移動手段として、7コースを運行しています。今年度は「Googleマップ」に登録し、利用者がバス停の位置や運行ルート、時刻表などの情報を簡単に確認できるようになり、初めてぐるりん号を利用される方も、効率的な移動方法を一目で把握することができます。また、走行中のバスの位置やバス停到着予定時間等の情報を提供するバスロケーションシステムも活用し、利用者の利便性の向上を図っています。
ぐるりん号は古河市への来訪者に認知されやすくなりました。また、紙の時刻表に頼った情報提供がデジタル化されることにより、経費の削減や環境負荷の軽減につながりました。

防犯カメラの新規設置や老朽化機器の更新、また防犯教室や防犯キャンペーン等を実施し、広報・啓発活動を行いました。
2025/11/06(木) 11:32
「犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり」を目指し、「自分のことは自分で守り、自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防犯意識の向上を図っています。地域住民、市、事業所、警察等が一体となり、犯罪防止に取り組んでおり、今後も警察や防犯団体と連携し、防犯意識の啓発や防犯カメラ設置などを計画的に進めています。
また、防犯教室やキャンペーンを通じて広報活動を実施。特に、防犯協会女性部が主体となり、小学校低学年児童を対象に防犯教室を行い、学校でも防犯意識の啓発が進んでいます。さらに、地域では防犯診断や町内見回り、警察署員による講話を通じて、地域ぐるみで犯罪防止に取り組む自治会が増加しています。

グローバルに活躍できる人材を育てます~ALTの派遣、英語検定料の補助、英語特区事業の推進~
2025/11/06(木) 11:30
子どもたちの英語でのコミュニケーション能力を高め、国際社会や地域で活躍できる人材を育成するため、英語特区事業として、小学1年生から外国語活動を実施しています。また、「イングリッシュアドベンチャー」や「ジョイタイム」などで、コミュニケーションに必要な「聞く」「話す」能力を育てています。さらに、小学5年生から中学3年生には、英語検定料の半額補助を行い、学習意欲の向上をサポートしています。
アンケート結果では、イングリッシュアドベンチャーに99.4%が「楽しかった」、98%が「英語が話せたと実感」、英語特区取組では93%が「外国人の先生との勉強は楽しい」と回答。オンライン英会話では、96.4%が「もっと英語を話したい」と回答し、学んだことが役立ったと答えた中学生は95.5%に達しました。
これらを踏まえ、今後も効果的な学習環境を提供し、英語力向上を目指します。

市民主体のまちの魅力発信を推進しています。
2025/11/06(木) 11:30
古河市では、市に対する愛着や誇りが向上し、「住んでみたい」「住み続けたい」と思われるまちになることを目的として、SNS等を活用した市民主体のまちの魅力発信を促進する取り組みを行っています。
昨年度は、市公式Instagramへの投稿を任せている市民ボランティア「こがキラphotoクラブ」の運営や、動画を使った魅力発信を促進するためのワークショップなどを実施しました。また、市公式Instagramには「こがキラphotoクラブ」メンバーから約130件の投稿があり、閲覧数は延べ50万回を超えました。行政の立場では伝えきれない魅力を市民目線で発信してもらうことで、まちをより身近に感じ、自分ごととして考えていただくきっかけになっています。
今後も取り組みを継続し、市民と協働してまちの魅力発信に努めます。

恒例の桃まつりや伝統の提灯竿もみまつりなど、各種イベントを実施しました。
2025/11/06(木) 11:25
恒例の「古河桃まつり」や関東の奇祭と言われる「古河提灯竿もみまつり」をはじめ、「古河さくらまつり」や「古河菊まつり」を開催し、たくさんの皆様にご来場をいただきました。
また、5年ぶりとなる「第19回古河花火大会」を無事開催することができました。令和7年度は20回の記念大会となりますので、さらに皆様に楽しんでいただけるプログラムを計画しています。
「桃まつり」や「提灯竿もみまつり」など、様々なお祭りを開催することで、四季を彩る花々の美しさや、竿と出場者が激しくぶつかり合う迫力など、多くの皆様から好評をいただいております。市内外の多くの皆様に古河市の魅力を発信できました。今後も地域の活性化に向けて、取組みを進めます。

市民主体によるまちの魅力発信を行っています。
2024/09/20(金) 09:26
古河市では潜在する市の魅力を市民に掘り起こしSNS等で発信してもらうことにより、市民の市に対する愛着度を向上させるとともに、市内の活性化を図ることを目的として、こがキラphotoクラブ(市民記者)の運営やローカルWebマガジンの掲載を行っています。
昨年は、こがキラphotoクラブによる公園MAPの作成や、市民記者がまちの魅力を発信する古河市公式Instagramにおいて31万回を超える記事の閲覧がありました。
行政からの視点では伝えきれないまちの魅力を市民記者が発信することで、よりまちを身近に感じ、まちのことを考えていただくきっかけになったと感じています。
今後もまちへの愛着を持つ人を増やすため、市民と協働した魅力発信を継続します。

市内の移動性を高め、市民ニーズに合った運行になるよう、持続可能なぐるりん号の運行を推進します。
2024/09/20(金) 00:00
誰もが自由に外出でき、日常生活を快適に過ごせる環境づくりとして、市内を循環する7コースを運行しています。このたび、カーボンニュートラル社会実現への取り組みを啓発することを目的に、環境に配慮したEVバスを導入しました。
また、スマホ定期券・スマホ回数券の導入やスマホなどの端末に、走行中のバスの位置やバス停到着予定時間等の情報を提供するバスロケーションシステム「Bus Go!」を導入しました。
バスロケーションシステム「Bus Go!」では、乗車したいバスの現在位置とバス停での待ち時間の目安をリアルタイムで地図上に表示され、時間的ロスがなく「ぐるりん号」を利用できることにより、利用者がぐるりん号を利用しやすくなりました。

防犯カメラの新規設置や保守点検、更新、防犯教室や防犯キャンペーン等の実施による広報・啓発活動を実施しました。
2024/09/20(金) 00:00
「犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり」のために、「自分のことは自分で守り、自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防犯意識の高揚と地域の実情に即した地域住民、市、事業所、警察等が一体となった安全に向けた取組を推進しています。
警察や防犯関係団体と連携し、防犯教室や防犯キャンペーン等による広報・啓発活動を実施しています。特に防犯教室は、防犯協会女性部が主体となり小学校低学年児童等を対象に実施しており、年間を通して市内小学校から申込がきている状況で、学校側も児童の防犯意識啓発を重視しています。
また、地域によっては防犯診断と称し、定期的な町内の見回りや警察署員に講話を依頼するなど、地域ぐるみによる犯罪防止策に取組む自治会等も増加しています。
今後も、警察や防犯関係団体と連携し、防犯意識の高揚に向けた意識啓発や、防犯カメラの設置等を計画的に促進し、総合的に犯罪防止策を強化します。

恒例の桃まつりや伝統の提灯竿もみまつりなど、各種イベントを実施しました。
2024/09/20(金) 00:00
恒例の「古河桃まつり」や関東の奇祭と言われる伝統の「古河提灯竿もみまつり」をはじめ、「古河さくらまつり」や「古河菊まつり」を開催し、たくさんの皆様にご来場をいただきました。
ここ数年、渡良瀬川の堤防改修工事により「古河花火大会」を開催することができませんでしたが、令和6年度は5年ぶりに開催しました。
「桃まつり」や「提灯竿もみまつり」など、様々なお祭りを開催することで、四季を彩る花々の美しさや、竿と出場者が激しくぶつかり合う迫力など、多くの皆様から好評をいただいています。
新型コロナウイルスの5類移行に伴い、来場者が大幅に増加したことから、市内外の多くの皆様に古河市の魅力を発信できたと考えています。今後も地域の活性化に向けて、様々なイベントの実施や情報を発信します。

古河城主土井利位が愛用した刀及び雪華模様を散らした刀装具一式を購入しました。
2024/09/20(金) 00:00
江戸後期の古河城主、土井利位は、40年余りの歳月をかけて雪の結晶を観察、日本ではじめて『雪華図説』正続として刊行しました。利位は観察した雪華模様を意匠とする多くの品々をプロデュースしたものの、現在そのほとんどが散逸しています。
このたび購入した刀及び刀装具一式は、利位が監修、雪華模様入りの品として現存唯一の品であり、きわめて貴重。古河の重層的で多様な歴史と文化力を雄弁に物語ることができる文化財であり、次世代の古河を担う子供たちに、古河の優れた歴史文化を教え伝える教育財産として有用であると評価を得ています。
令和7年3月の企画展「雪華の刀装」にて公開するほか、今後、修理を行い古河を象徴する文化財として活用していく予定です。

保育ICTシステムを導入しました。
2024/09/20(金) 00:00
保護者の利便性の向上や保育士業務の効率化と負担軽減により保育の質を高めることを目的とした保育ICTシステムの導入に向けて、必要となる機器の購入や設備環境の整備を実施しています。
また、公立保育所の施設や備品の突発的な不具合に備え、計画的に維持管理や施設等の修繕を行ったことで、子ども達が安全に保育所で過ごすことができています。
保育ICTシステムを導入したことで、欠席やお迎えなどの連絡をスマートフォンの専用アプリから行うことができるようになり、保護者の利便性が向上しました。また、登降所管理も含めてさまざまな情報をシステム上で確認することができるようになり、施設内での情報共有が効率的に図れるようになりました。
さらには、紙の配布物などが不要となり、保育士業務の負担軽減が図られています。これらのことから子どもと向き合う時間や、保護者との保育に関する会話の時間が増えています。

多様な保育のニーズに対応した様々な保育サービスの支援を実施しています。
2023/09/01(金) 00:00
保護者の働き方や生活様式の多様化に対応した延長保育や一時預かり、病児保育などの事業を行う民間保育事業者に対しICT活用や保育支援員の確保といった支援を行っています。
保育士の負担を軽減し働きやすい環境を作ることで、保育を必要とする人が保育施設を利用しやすくなっています。なお、古河市では令和4年10月1日現在で待機児童数は0人です。

市内の移動性を高め、市民ニーズに合った運行になるよう、持続可能なぐるりん号(コミュニティバス)の運行を実施
2023/09/01(金) 00:00
誰もが自由に外出でき、日常生活を快適に過ごせる環境づくりとして、今年度から1コースを増便し、7コースで運行しています。また、スマホ定期券・スマホ回数券の導入やスマホなどの端末に、走行中のバスの位置やバス停到着予定時間等の情報を提供するバスロケーションシステム(Bus Go!)を導入し、利用者の利便性の向上を図っています。
令和5年4月より古河大使を務める浅野恭司さんがデザインしたキャラクター「桃香(9歳)」と「万寿王丸」をラッピングした循環バス「ぐるりん号」(大型ワゴン)が運行を始めました。

市民のために災害用備蓄品を購入しました。
2023/09/01(金) 00:00
古河市地域防災計画に基づき、災害時の体制及び防災施設の整備を強化することを目的に災害用備蓄品を購入しました。備蓄品は災害時に役立つ物資のため、直接的な変化や反応はありませんが、非常時に活用します。また、多岐に渡る防災情報の発信により、市民が自ら安全に避難行動を取れる環境を整え、指定避難所等の充実を図ります。

古河市農村地域におけるランドマークとなる農泊施設(山川邸)を改修しました。
2023/09/01(金) 00:00
古河市の農村地域のランドマーク的な宿泊・体験施設を目指すために、農泊施設(山川邸)の改修を行いました。山川邸は豪農の特色を色濃く残す歴史的にも価値のある古民家です。今後は、宿泊を含めた本格的な利活用を行い、誘客を図ります。

古河歴史博物館の企画展示や常設展示における展覧会を実施しました。
2023/09/01(金) 00:00
「かえってきた堀川國廣」、「雪の殿さま土井利位」等の企画展、2ヶ月毎にテーマ設定して常設展示室2部屋の陳列替えを行うテーマ展の開催などを通して、来館者が古河関係文化財を観覧できる環境を提供しています。企画展来館者の満足度を向上させるために、刀剣乱舞ONLINEコラボスタンプラリー企画管理運営や企画展時の警備業務などにも活用しました。
刀剣乱舞ONLINEとコラボレーションを行った企画展「かえってきた堀川國廣」は、古河ゆかりの文化財を通じて多くの方にご来館いただきました。展覧会に付随して実施した関連スタンプラリーでは、古河あきんどの会の協力を仰ぎ、企画展入館券の半券提示による特典を設けたことにより、大勢の来館者が市内の商店を利用しまちなかの活性化につながりました。

公共施設へのFreeWi-Fiの設置や高齢者向けスマホ教室の開催で地域のデジタルデバイドの解消を目指します。
2023/09/01(金) 00:00
地域BWA制度を活用し、地域のケーブルテレビ事業者と協働して市内の公共施設に対して、FreeWi-Fiの整備を進めています。また、高齢者のデジタルデバイドの解消を目指すため、スマホ教室を開催しました。スマホを使用するのがはじめての高齢者でも対応できるように、手厚くサポートできる体制で運営しました。
公共FreeWi-Fiは市内の10施設で利用が可能となっており、年間のべ約1万4千人の市民に利用していただいております。
スマホ教室については、定員の3倍もの応募があり、高い需要があることが分かりました。参加いただいた高齢者の方にも好評をいただいており、今年度は開催回数を2倍に増やすなど、引き続き市民の声にこたえていきたいと考えています。

18件中1~18件表示














