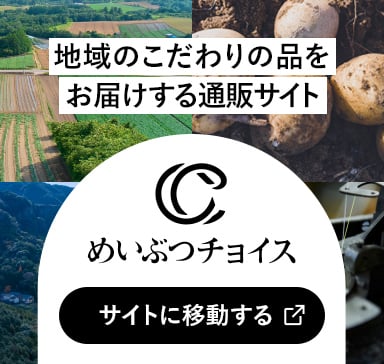【寄附金の使い道】\若者のUターンを促す!/長島町の支援制度「ぶり奨学金」
あなたの寄附が若者の未来とふるさとの希望をつなぐ— 「ぶり奨学金」は、ふるさと納税の寄附金を活用して、若者の進学とUターンを支援する長島町独自の奨学金制度です。

若者たちが進学をきっかけに町を離れ、そのまま帰ってこなくなる。
地方の多くの町が抱える課題に長島町も直面していました。
人口約9,000人の小さな島・長島町は、豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、特に養殖ブリの生産量は日本一。この町から全国に出荷されるブランド魚「鰤王」は、食卓を彩る自慢の逸品です。
そんな誇るべき地元資源と、若者の将来を結びつけた制度が、「ぶり奨学金」です。
『ぶり奨学金』とは?

「ぶり奨学金」は、ふるさと納税の寄附金を活用して、若者の進学とUターンを支援する長島町独自の奨学金制度です。
名前の由来は、町を代表する特産品「ぶり」。出世魚であるブリが、成長の過程で名前を変え、最終的にふるさとに戻る姿に、地元を巣立つ若者たちを重ね合わせています。
この制度の大きな特徴が2つあります。
●進学時に利用した奨学ローンの利息分は町が全額補填
→ 長島町に戻らなくても対象。進学を経済的に支援する。
●元金分も卒業後10年以内に長島町にUターンすれば町が補填
→ Uターンすれば返済額はゼロに。
つまり、「町外で学び、いずれふるさとに戻ってくれるなら、奨学金の返済は必要ない」という、地域ぐるみの若者支援制度なのです。
なぜ必要だったのか? “学び”が町を遠ざけていた

長島町には高校や大学などの進学先がなく、中学校卒業と同時にほとんどの子どもたちが島外へ。その後は進学先で就職し、そのまま地元に戻らない若者も少なくありません。
長島町では、特に20〜30代の若年層の転出が顕著で、「町の将来を担う世代」が少しずつ減り続けていました。このままでは「消滅可能性自治体」と呼ばれるリスクさえある——。そんな強い危機感が、ぶり奨学金の導入を後押ししました。
導入後、若者のUターンが増加

この制度は2016年(平成28年)にスタート。これまでに延べ360人以上が奨学金制度を利用し、60人以上が実際に長島町へUターンを果たしています。初年度に制度を利用した高校生が、大学を卒業して社会に出る年齢になったことで、今まさにその効果が本格的に現れ始めているのです。
「地元に戻ってきた若者が地域づくりの担い手となり、町に新しい風を吹き込んでいる」という声も少なくありません。
ふるさと納税を「ありがとう」で終わらせない

ふるさと納税は、ただの制度ではありません。
「ふるさとを応援したい」「未来を支えたい」という皆さまの温かい想いを、長島町は確かに受け取り、かたちのある支援として実行に移しています。ぶり奨学金は、そのひとつの成果です。皆様のご寄附があってこそ、「教育」、「Uターン」、「地域活性化」と、すべてがつながるこの制度が実現し、効果が出てきています。
これからも寄附という形で、若者たちの夢とふるさとの希望を応援いただけますと幸いです。